ユーザーインタビューのやり方と目的を徹底解説!手順/設計のコツ/質問例まで
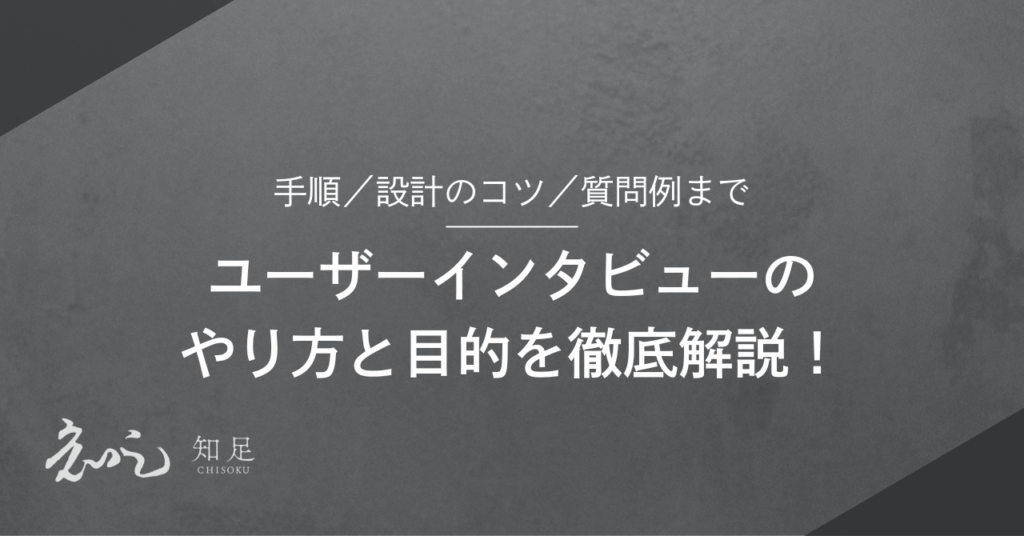
「ユーザーの本当の課題が分からない」「データだけでは製品改善の方向性が見えない」と感じていませんか。
多くの開発者やマーケターが、数値の裏に隠された顧客の深層心理を掴めずにいます。
その解決策が、ユーザーの生の声から核心的なヒントを得る「ユーザーインタビュー」です。
本記事では、目的設定から具体的な手順、質問設計のコツまでを網羅的に解説します。
初めての方でも、この記事を読めば自信を持って実践できるので、ぜひ最後までご覧ください。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
>>新規顧客獲得の方法10選!手順や成功のポイントをわかりやすく解説
目次
ユーザーインタビューがなぜ重要なのか?
ユーザーインタビューは、顧客の「生の声」を直接聞けるため、非常に重要です。
アンケートやアクセス解析といった定量データでは把握できない、ユーザーの感情や行動の背景にある「なぜ」を深く探求できます。
実際に、ユーザーが製品をどのように使い、何に満足し、どこに不満を抱えているのかを具体的に知ることが可能です。
このような定性的な情報こそが、本当に価値のある製品開発やサービス改善の源泉となり、ビジネスを成功に導きます。
ユーザーインタビューの目的
ユーザーインタビューにはさまざまな目的があります。
ここでは代表的な目的として、ユーザーのニーズ把握、製品やサービスの改善、そしてUXリサーチ(ユーザー体験調査)の一環としての役割について解説します。
ニーズの把握
ユーザーインタビューではユーザーの潜在ニーズを深く把握することができます。
数字では見えない本質的な要求や不満を対話の中から引き出し、真の課題を明らかにするのが狙いです。
例えば、インタビュー対象者の体験に着目し、「なぜそう感じたのか?」と掘り下げていくことで、ユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズや課題(インサイト)を発見できます。
このようにユーザーの裏にある本音を聞き出すことで、新たな視点や仮説を得られるため、ユーザーインタビューは企画段階から改善まで広く活用されています。
製品/サービスの改善
インタビューで得られたユーザーの声は、製品やサービスの具体的な改善アイデアにつながります。
どの部分が良く、どこに不便さを感じているかなど直接質問を投げかけることで、ユーザー目線での改善点が見えてきます。
ユーザーから寄せられる「ここが使いづらい」「こうなったら嬉しい」といった要望は、開発チームにとって貴重なヒントです。
実際にユーザーインタビューは新規開発時だけでなく、リリース後の評価や継続的な改善フェーズでも活用できる汎用的な手法です。
定期的なインタビューによりユーザー満足度を維持・向上させ、サービスの解約防止にも役立てることができます。
UXリサーチの一環
UX(ユーザーエクスペリエンス)リサーチの一環として、ユーザー体験全体の質を高めるために行われます。
ユーザーが製品やサービスを利用する全過程で、どのような感情を抱き、どのような思考を巡らせているのかを深く理解することが目的です。
この深い理解が、より直感的で快適な操作性の実現や、満足度の高い体験設計につながります。
データだけでは決して測れない、心地よさや感動といった価値を創造する上で不可欠なプロセスです。
ユーザーインタビューの種類
ユーザーインタビューにはいくつかの種類があります。
大きく分けると、インタビューの形式(誰に・何人で行うか)と構造化の度合い(質問の決め方)によって分類できます。
それぞれの特徴を理解し、目的に合った手法を選ぶことが大切です。
インタビュー形式
インタビュー形式は、実施する場所や方法によって分類されます。
対面形式は、相手の表情や仕草といった多くの非言語情報を得られる点が大きなメリットです。
一方、オンライン形式は、場所の制約を受けず遠隔地の対象者にもアプローチできる手軽さが魅力でしょう。
グループインタビューでは、参加者同士の相互作用から、個人インタビューでは得られないような新しい発見が生まれることもあります。
構造化の度合い
質問の自由度によって、インタビューは3つに分類されます。
具体的には、事前に決めた質問を順番通りに行う「構造化インタビュー」がまず挙げられます。
次に、大まかな質問項目は決めつつ会話の流れで深掘りする「半構造化インタビュー」があります。
そして、テーマだけを決めて自由に話してもらう「非構造化インタビュー」です。
仮説を検証したい場合は構造化、探索的な調査には非構造化が向いています。
実施前の準備:ゴール設定と設計
インタビューの成否は、事前の準備で8割が決まると言っても過言ではありません。
本パートを理解することで、効果的なインタビューの土台を築けます。
目的の明確化
まず最初に行うべきは、「このインタビューで何を明らかにしたいのか」という目的(ゴール)を具体的に設定することです。
目的が曖昧なままでは、聞くべき質問がぼやけ、得られる情報も散漫になってしまいます。
「〇〇という仮説を検証したい」「△△という機能の課題を発見したい」「新規事業のアイデアを探したい」など、チーム内で共通認識を持ち、インタビューのゴールを明確に言語化しましょう。
対象者(ペルソナ)の選定
次に、目的に基づいてインタビューの対象者を選定します。
ここで重要なのは、調査したい内容について最も詳しく、かつ代表的な意見を持っていると考えられる人物を選ぶことです。
事前に設定したペルソナ(架空のユーザー像)に合致する人を探すのが効果的です。
例えば、「子育て中の母親向けの時短家電」に関するインタビューであれば、実際にそのターゲット層に合致する人に話を聞く必要があります。
対象者の選定を誤ると、得られる情報が目的とずれてしまい、インタビュー自体が無駄になる可能性もあります。
リクルーティング会社を利用したり、自社の顧客リストから探したりする方法が一般的です。
質問項目の設計
目的と対象者が決まったら、具体的な質問項目を設計します。
このとき、「インタビューガイド」と呼ばれる台本を作成すると、当日の進行がスムーズになります。
質問は、相手が「はい/いいえ」で答えられない「オープンエンディッドクエスチョン(開かれた質問)」を主体に構成するのが基本です。
「この機能は使いやすいですか?」ではなく、「この機能を使ったとき、どのように感じましたか?」と尋ねることで、より具体的なエピソードや感情を引き出せます。
また、相手の回答に対して「それはなぜですか?」「具体的に教えていただけますか?」といった深掘りの質問を挟むことで、インサイトに近づくことができます。
準備物/環境設定
最後に、当日に必要な物品の準備と環境設定を行います。
オンラインであれば、ビデオ会議ツールのURL発行や接続テストは必須です。対面の場合は、参加者がリラックスして話せる静かな会議室などを確保しましょう。
共通して必要なものとして、作成したインタビューガイド、ICレコーダーや録画機材(許可を得る場合)、PC、筆記用具などが挙げられます。
また、参加者への謝礼(現金やギフト券など)も忘れずに準備します。
当日に慌てないよう、チェックリストを作成して、機材の動作確認を含め、前日までにすべての準備を完了させておくことが理想です。
ユーザーインタビューの実施方法
入念な準備ができたら、いよいよインタビューの実施です。
本パートを理解することで、当日の流れを把握し、参加者から価値ある本音を引き出すための心構えができます。
インタビューの進め方
インタビューは、大きく「導入」「本題」「クロージング」の3つのパートで進めます。
まず導入部分(アイスブレイク)では、自己紹介や簡単な雑談を交え、参加者の緊張をほぐすことに集中します。
インタビューの目的や所要時間、録音・録画の許可などを丁寧に説明し、安心して話せる雰囲気を作りましょう。
次に本題では、準備したインタビューガイドに沿って質問を進めますが、相手の話を遮らず、深く頷いたり相槌を打ったりして「傾聴」の姿勢を保つことが重要です。
最後にクロージングでは、インタビュー協力への感謝を伝え、言い残したことがないかを確認します。
約束通り謝礼をお渡しし、気持ちよく終了しましょう。
柔軟な対応
インタビューガイドはあくまで進行の指針であり、厳密に守る必要はありません。
参加者の回答から、当初想定していなかった重要なテーマが浮かび上がることがあります。
その際は、ガイドから少し脱線してでも、そのテーマを深掘りする柔軟性が求められます。
インタビュアーの役割は、質問を消化することではなく、目的達成につながるインサイトを得ることです。
相手の話の流れに乗りながら、「なぜそう思うのか」「具体的にはどういうことか」といった質問を投げかけ、会話を広げていくスキルが大切になります。
計画通りに進めることよりも、目の前の参加者との対話を重視する姿勢が、思わぬ発見につながります。
倫理と配慮
ユーザーインタビューは、参加者の善意と協力があって初めて成り立つものです。
そのため、倫理的な配慮は絶対におろそかにしてはいけません。
インタビューの目的、内容、所要時間、データの利用範囲などを事前に明確に説明し、必ず同意を得るようにします。
特に、録音や録画を行う場合は、その旨を伝え、書面や口頭で明確な許諾を得なければなりません。
また、インタビューで得られた個人情報は厳重に管理し、プライバシー保護を徹底することが求められます。
高圧的な態度を取ったり、回答を誘導したりするような言動は厳禁です。常に対等な立場で、相手への敬意と感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
ユーザーインタビュー後の分析とインサイト抽出
インタビューで得た情報を整理し、次のアクションに繋がる「インサイト」を抽出する工程は非常に重要です。
本パートを理解することで、膨大な発言ログから価値ある気づきを見つけ出す方法を学べます。
記録とトランスクリプト作成
インタビューの録音・録画データは、分析のためにテキスト化(トランスクリプト作成)します。
発言内容を文字で可視化することで、客観的な分析が可能になり、チーム内での情報共有も容易になります。
全文を書き起こすのが理想ですが、時間がなければ重要な発言を要約する形でも問題ありません。
最近は、AIを活用した自動文字起こしツールもあり、作業を効率化できます。
テーマのグルーピング
次に、書き起こした発言の中から、ユーザーの課題、ニーズ、印象的な言葉などを付箋やカードに一つずつ書き出していきます。
そして、書き出したカードを眺めながら、似た内容や関連するテーマごとにグループ分けを行います(KJ法など)。
この作業を通じて、断片的だった個々の発言が整理され、全体の構造や共通するパターンが見えてくるのです。
インサイトの発見
グルーピングによって可視化されたテーマを眺め、それらが「なぜ」起きたのかを深く考察することで、インサイト(洞察)を発見します。
インサイトとは、単なる事実の要約ではなく、ユーザーの行動の背景にある隠れた欲求や価値観を言語化したものです。
例えば、「多くのユーザーが商品の詳細スペックを確認している」という事実から、「ユーザーは購入の失敗を恐れており、自分の選択を正当化するための情報を求めている」といったインサイトを導き出します。
このインサイトこそが、次の製品改善や新しいサービスのアイデアにつながる、最も価値のある発見といえるでしょう。
ユーザーインタビュー設計のポイント
最後に、ユーザーインタビューを効果的に行うための設計上のポイントをまとめます。
これまで述べてきた内容の中でも特に重要な点を再確認しましょう。
事前準備の徹底、一対一インタビューの活用、そして進行時の柔軟な姿勢という3つの観点からポイントを紹介します。
事前準備の重要性
ユーザーインタビュー成功のカギは事前準備にあります。
インタビュー自体も重要ですが、始まる前の段取りで勝負は半分決まっています。
目的設定から質問設計、参加者リクルーティング、リハーサルまで、やりすぎかなと思うくらい入念に準備しましょう。
インタビューの事前準備と設計は最も重要な工程であり、一度の機会を最大限活かすには慎重な準備が不可欠だと強調されます。
準備不足で臨むと「聞きたいことを十分聞けなかった」「そもそも対象者の選定を間違えた」という事態にもなりかねません。
逆にしっかり準備しておけば、多少イレギュラーなことが起きても落ち着いて対応できます。
準備に時間をかけることが、結果的にインタビューの質を高める最短ルートなのです。
1対1のインタビューの効果
グループインタビューにも利点はありますが、ユーザーの深い本音や個人的な体験談を引き出したい場合は、1対1のデプスインタビューが非常に効果的です。
他の参加者の目を気にする必要がないため、対象者はよりリラックスして、率直な意見を話しやすくなります。
インタビュアーも一人の対象者に集中できるため、話の流れを追いやすく、微妙な表情の変化や声のトーンから感情を読み取りながら、的確な深掘りの質問を投げかけることが可能です。
時間とコストはかかりますが、質の高いインサイトを得るためには、1対1の形式が最も適しているといえるでしょう。
柔軟に進行する姿勢
インタビューガイドは重要な道しるべですが、それに固執しすぎるのは禁物です。
インタビューは生き物であり、対話の流れの中でこそ、予期せぬ重要な発見が生まれることがあります。
対象者の話に真摯に耳を傾け、もし想定外の話題が出ても、それがインタビューの目的に関連する重要なことであれば、勇気を持って深掘りしていく柔軟な姿勢が大切です。
ときには、用意した質問をすべて聞けなくても構いません。
計画通りに進めることよりも、目の前のユーザーから本質的な情報を引き出すことを最優先に考え、臨機応変に対応することが成功の鍵となります。
ユーザーインタビューの質問例
効果的な質問は、ユーザーから具体的なエピソードや本音を引き出すための鍵となります。
以下に、状況別の質問例を挙げます。
これらを参考に、ご自身の目的に合わせてアレンジしてみてください。
- アイスブレイクで使う質問
「本日はお忙しい中ありがとうございます。まず、〇〇について、普段どのようにされているか簡単に教えていただけますか?」
「最近、〇〇に関して何か気になったニュースなどはありましたか?」 - 行動に関する質問(過去の経験を尋ねる)
「前回、〇〇(タスク)をされた時のことを、最初から順を追って教えていただけますか?」
「その時、特に時間がかかったり、難しいと感じたりした点はどこでしたか?」 - 課題やニーズに関する質問
「〇〇という作業について、もっとこうなれば良いのに、と感じる点はありますか?」
「もし魔法が使えるとしたら、〇〇をどのように変えたいですか?」 - 深掘りするための質問
「なぜ、そのように思われたのでしょうか?」
「『便利だった』とのことですが、具体的にどのような点が便利だと感じましたか?」
インタビューの対象者の募集方法と費用相場
インタビューの対象者を見つけるには、いくつかの方法があります。
| 募集方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| リクルーティングサービス | 条件に合う対象者を効率的に集められる | 費用が高め(1人あたり数万円) |
| 自社の顧客リスト | 自社サービスへの理解度が高い | 意見が好意的になりやすい可能性がある |
| SNSやWebサイトでの公募 | 低コストで募集できる | 条件に合わない応募が多くなる可能性 |
| 友人・知人からの紹介 | 信頼性が高く、協力も得やすい | 人間関係に配慮が必要、意見が偏る可能性 |
費用相場について
参加者への謝礼は、インタビューの時間や対象者の専門性によって変動しますが、一般的には1時間のインタビューで5,000円〜10,000円程度が相場です。
医師や経営者など、希少性の高い専門家を対象とする場合は、さらに高額になることもあります。
リクルーティングサービスを利用する場合は、この謝礼に加えて、募集代行手数料が別途発生します。
ユーザーインタビューに役立つツール
インタビューの実施から分析まで、各プロセスを効率化してくれる便利なツールが数多く存在します。
これらを活用することで、より本質的な作業に集中できます。
- オンライン会議ツール
Zoom, Google Meet:オンラインインタビューの実施に不可欠です。録画機能を使えば、後から見返すこともできます。 - 自動文字起こしツール
Vrew, Notta:録音データをアップロードするだけで、AIが自動でテキスト化してくれます。分析作業の時間を大幅に短縮できます。 - オンラインホワイトボードツール
Miro, FigJam:インタビューで得た気づきを付箋のように貼り出し、オンライン上でチームメンバーとリアルタイムに整理・分析できます。 - リクルーティングサービス
ビザスク, クラウドワークス:条件に合うインタビュー対象者を募集・管理できるプラットフォームです。
ユーザーインタビューに関してよくある質問
最後に、ユーザーインタビューに関して頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめました。
ユーザーインタビューは何人に聞けば十分?
ユーザーインタビューは3〜5人程度に聞けば十分です。
一度の調査サイクルにつき、最低でも3名、多くても5名程度インタビューすれば主要な問題やテーマは明らかになるとされています。
少数のインタビューでもユーザー体験に関する主要なパターンが見えてくることが多く、それ以上は似た内容の繰り返しになる傾向があります。
ただし得られた知見をもとに仮説検証を進める際は、別のユーザーグループでもう一度3〜5名に聞くなど小規模な調査を繰り返し行うことが望ましいです。
極端にサンプルが少ないと偏る可能性もあるため、対象ユーザー像ごとに数名ずつ実施していくのが理想的でしょう。
1回のインタビュー時間はどのくらい?
1回のインタビュー時間は30〜60分程度が目安です。
一般的にはインタビューは1人当たり30分から長くとも1時間程度で設定することが多いです。
60分あれば大半のテーマはカバーできますし、それ以上長くなると参加者の集中力が切れ、負担も大きくなります。
実際の謝礼相場も60分を基準に設定されている場合が多く、90分実施するケースでもせいぜい1.5倍程度に留めるのが一般的です。
初めてのインタビューで勝手が分からないうちは、45〜60分前後を目安にしておくと安心でしょう。
時間内で終わらなかった質問は、後日メールフォローするなど別途対応する方法もあります。
なおグループインタビューの場合は意見交換に時間がかかるため、1.5〜2時間ほど取ることもありますが、それでも休憩を挟むなど配慮して進めます。
アンケートとの違いは?
アンケートは、多くの人から定量的なデータを集める「仮説検証」に適した手法です。
一方、インタビューは、少数の人から定性的な情報を深く掘り下げる「仮説探索」に適しており、「なぜ」を解明することを目的とします。
録音や録画はしても良い?同意はどう取る?
録音や録画は分析のために推奨されますが、必ず事前に参加者の同意を得る必要があります。
「分析目的以外では使用しない」ことなどを明確に伝え、口頭および書面で許可を取りましょう。
ユーザーインタビューのまとめ
ユーザーインタビューは、数値データだけでは分からない顧客の「なぜ」を解明し、製品やサービスを飛躍させるための強力な手法です。
成功の鍵は、目的を明確にし、適切な対象者を選び、練り上げられた質問を用意する「事前準備」にあります。
当日は参加者に敬意を払い、柔軟な姿勢で対話に臨むことが重要です。
この記事で解説した手順やコツを参考に、ぜひユーザーの生の声に耳を傾け、ビジネスの次の一歩につながる貴重なインサイトを発見してください。













