ラテラルシンキングの鍛え方とは?ビジネスに活かす実践方法を解説
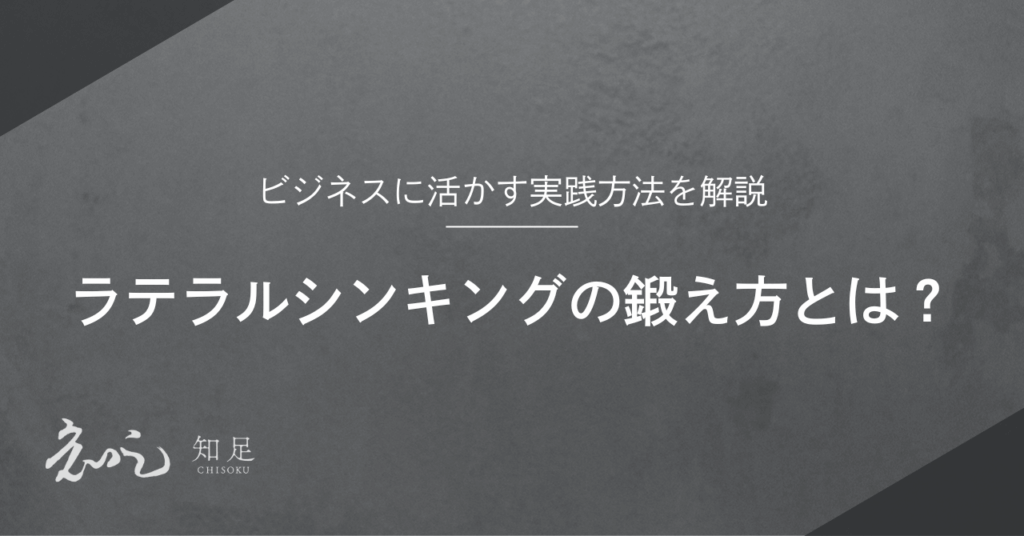
ラテラルシンキングは「どう鍛えればいいのか」「どんな場面で効果が出るのか」と感じていませんか?
ビジネスでは、課題解決力や商品企画力、組織の創造性を高めるために、この思考法を取り入れる企業が増えています。
一方でといった疑問を持つ人も多いはずです。
本記事では、ラテラルシンキングの基本から鍛え方、ビジネス活用の成功事例・失敗事例、導入のコツやメリットまで網羅的に解説します。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
>>ビジネスモデルキャンバスとは?例を基に作り方をわかりやすく解説!
目次
ラテラルシンキングとは?
ラテラルシンキングは「水平思考」とも呼ばれ、論理的な道筋ではなく、直感やひらめきを重視して物事をとらえる思考法です。
従来のロジカルシンキングは、前提やルールに基づいて一つの正解を導き出す「垂直思考」に分類されます。
対してラテラルシンキングは、前提自体を疑い、全く異なる視点から新たなアイデアを引き出す発想法です。
正しい答えを導き出すことではなく、「新しい問いそのものを生み出す」力が問われます。
ロジカルシンキングとの違い
ビジネスの現場では、課題に対して「なぜ起きたのか」を分析する機会が多くあります。
そうした場面ではロジカルシンキングが有効ですが、答えが明確でない問題や、複雑で不確実な状況では限界もあります。
例えば、ラテラルシンキングは、原因や結果を追うのではなく、思考の切り口そのものを変えて、従来とは異なる選択肢をつくり出すアプローチです。
例えば、「どうやって売上を上げるか」ではなく、「本当に売上を上げる必要があるのか」と考え直すことができます。
両者は目的が異なるものの、相反する存在ではありません。
分析が得意なロジカル思考と、発想の飛躍が得意なラテラル思考を組み合わせることで、課題解決の幅は大きく広がります。
ビジネスにおける水平思考の意義
新しい価値を生み出すためには、既存の枠組みにとらわれないアイデアが必要です。
AIやデジタル技術の進化により、情報処理の多くは機械が代替可能となりました。
その一方で、人にしかできない創造的な思考の重要性が高まっています。
ラテラルシンキングは、こうした創造的思考力を育むための手法として注目されています。
実際に、広告業界や製品開発、戦略立案の現場では、すでに導入が進められています。
多様な視点を持ち寄ることで、新たな市場ニーズや潜在的課題の発見につながるからです。
また、チームでの議論やワークショップにおいても効果が期待されます。
一人ひとりの固定観念を外し、「発言しやすい空気」をつくることで、メンバー全体の創造性が引き出されます。
なぜラテラルシンキングが今必要なのか
ここからは、なぜ今ラテラルシンキングが必要なのか、説明していきます。
複雑化する課題への対応力
論理では太刀打ちできない課題が増えています。
例えば、ビジネスにおける問題は、単純な因果関係では説明できないことがほとんどです。
多様なステークホルダー、変化する市場、予測不能なリスクなど。
ロジカルシンキングでは一見「正しく」見える解決策も、現実では機能しないことが少なくありません。
「自分の考えが通じない」「問題が堂々巡りになる」。
そんな経験をしたことはありませんか?
例えばそれは、従来の分析的な思考だけでは突破できない壁にぶつかっている証拠かもしれません。
こうした混迷した状況でカギになるのが「枠を超えた発想」です。
ラテラルシンキングは、論理に縛られずに自由にアイデアを広げ、複雑な問題に対して新たな切り口で対応する力を育みます。
現代社会において、この柔軟な思考力こそが、企業や個人の競争力を左右する重要な要素となっています。
創造的な発想が求められる背景
創造力が、企業価値を決定づける時代に。
商品やサービスの差別化が難しくなった今、イノベーションを生み出すには、他とは違う「ひらめき」が不可欠です。
市場における優位性は、いかに斬新なアイデアを生み出せるかにかかっており、単なる改善や分析では限界があります。
AIの普及や自動化が進む中で、人間に残された強みは「創造する力」。
これは、論理的な正解を導く能力ではなく、今までになかった問いを立て、形にする力です。
そのためには、常識を疑い、枠組みを壊して考える思考法が求められます。
ラテラルシンキングは、まさにそうした創造性を刺激するトレーニングとして注目されています。
「誰もが気づかなかった解決策」を導くこの力こそが、これからの時代に求められる最重要スキルのひとつといえるでしょう。
ラテラルシンキングを鍛えるメリット
ラテラルシンキングを継続的に鍛えることで、思考の幅が広がり、ビジネスにおける柔軟な対応力が身に付きます。
従来の論理的な思考では見落とされがちな視点にも気付きやすくなり、課題に対して新たな解決策を導き出す力が養われます。
視点をずらす力を高めることで、状況に応じた適応力が格段に上がります。
例えばまた、周囲との議論においても建設的な発言ができるようになり、職場全体の思考レベルを引き上げるきっかけにもなります。
個人の創造力にとどまらず、組織全体の思考の質を底上げできる点も、見逃せない大きな効果です。
柔軟な発想力の習得
新しいアイデアが求められる場面で、論理に縛られた思考では突破口が見つからないことがあります。
そのようなときに重要なのが、既成概念から一歩離れて物事を見直す力です。
例えば、ラテラルシンキングを意識的に鍛えることで、思い込みにとらわれず自由に発想する力が高まります。
発想の切り替えが自然にできるようになれば、難題に直面したときにも、柔軟かつ多面的に考えることが可能になります。
これにより、従来の発想ではたどり着けなかった解決策を見つける確率が上がり、業務効率や成果にもよい影響を与えるようになります。
チームの創造性向上
個々の創造力だけでなく、チーム全体の発想力を引き出すことも、ラテラルシンキングの重要な役割です。
例えば、従来の会議では「正しさ」ばかりが重視されがちですが、この思考法を取り入れることで、正解のない問いに対する多様な答えを歓迎する姿勢が育ちます。
誰もが安心して自由に発言できる雰囲気が、チームの創造性を大きく伸ばす鍵になります。
例えば実際、ラテラルシンキングを取り入れた企業では、部署を越えた意見交換が活発化し、革新的なアイデアが次々と生まれています。
このような環境は、組織の競争力を高めるうえでも欠かせません。
ラテラルシンキングの鍛え方|5つの基本トレーニング
ラテラルシンキングを高めるには、意識的な思考訓練が欠かせません。
これは生まれつきの才能ではなく、日々の実践を通じて磨けるスキルです。
従来の枠にとらわれず、多様な視点から物事を見つめる姿勢が求められます。
ここでは、ビジネスや日常に応用できる5つの基本トレーニングをご紹介します。
各トレーニングはすぐに実践できる内容で、柔軟な発想力を習慣化することを目的としています。
前提を疑う視点を持つ
多くの人は、無意識に「これは当然」「これが常識」と思い込んで行動しています。
しかし、ラテラルシンキングでは既成概念を見直すことが大切です。
例えば「傘は手に持つもの」という認識を疑えば、手を使わない雨具の可能性にもつながります。
日々の生活や業務の中で、「本当にそうする必要があるのか」と問い直す習慣を持つことで、今まで見落としていたアイデアが浮かびやすくなります。
複数の切り口で考える練習
ひとつの課題に対して、異なる立場や視点から考える力を養うことも大切です。
例えば、新商品のアイデアを出すとき、消費者・販売員・競合・社会的影響といった切り口で検討することで、より実践的な着眼点が見えてきます。
一方向の思考に偏ると発想が固定化しがちですが、複数の視点を組み合わせることで、多角的かつ柔軟なアイデアが生まれやすくなります。
発想のフレームを壊す練習
私たちの思考には、過去の経験や文化によって形成された「枠」があります。その枠は便利である一方で、新たな発想の障害にもなります。
そこで、意図的に思考のパターンを崩す訓練が必要です。
例えば、問題を逆から考えたり、あえて常識を否定したりすることで、制限のない発想が可能になります。
型を破る勇気が、創造的なアイデアの突破口となります。
ブレインストーミングで発想の量を重視する
例えば発想力を鍛えるには、まずアイデアを出す「量」を重視する姿勢が欠かせません。
特にブレインストーミングは、質よりも数を出すことを目的とした思考法です。
重要なのは、他人の意見を否定せず、自由に出し合うことです。
否定や評価が入ると、思考の流れが止まってしまいます。
多様な視点を受け入れる姿勢が、新しい気付きや方向性につながります。
SCAMPER法で既存のアイデアを変化させる
例えば、新しいアイデアをゼロから考えるのが難しい場合は、SCAMPER法を活用して既存の発想を変化させることが有効です。
これは、代用・結合・応用・変更・削除・置換・逆転といった7つの視点で、既存のものを再構成して新しい形を生み出す手法です。
例えば、「素材を変えたらどうか」「使い方を変えたら?」など、問いを重ねることで、自然と視野が広がり、実用的なアイデアにつながります。
思考力を伸ばす具体的な例題・クイズ
固定観念を崩すトレーニングには、クイズ形式の問題が非常に有効です。
実際に答えを導き出す過程で、「前提を疑う」「視点を変える」思考が自然に鍛えられていきます。
ここでは、ラテラルシンキングの典型的な例題を2つ紹介します。
バスの進行方向問題
あなたは、窓が描かれていない左右対称のバスのイラストを見せられ、「このバスはどちらに進んでいるか?」と問われます。
ヒントは絵の中にはありません。「日本ではどちら側にドアがあるか?」という常識を逆手にとった観察力と日常知識の応用が求められる問題です。
この問題は、「情報が不足しているように見えて、実は身近な前提に気付くこと」がカギです。正解は「ドアが見えない=進行方向は左」。
単純な問いほど、思考を横に広げる力が鍛えられます。
電球とスイッチ問題
ある部屋に3つのスイッチがあり、隣室にはそれぞれ対応する3つの電球があります。
ただし、電球の部屋に入れるのは1回だけ。
スイッチと電球の関係をどう突き止めますか?
この問題は、時間や順番といった要素を組み合わせる発想力を試すものです。
スイッチ1を入れて数分後に切り、次にスイッチ2を入れてすぐ部屋に入る。
光っている電球=スイッチ2、熱い電球=スイッチ1、冷たい=スイッチ3というように、視覚と触覚を利用して論理的に答えを導きます。
成功事例に学ぶラテラルシンキングの効果
「発想の枠を壊す」と聞くと抽象的に思えるかもしれません。
しかし、実際にラテラルシンキングを導入した企業は成果を上げています。
ここでは、ビジネスの現場でその効果を発揮した具体的な事例を紹介します。
広告業界での活用例
ある飲料メーカーは、既存の「水分補給=運動後」という常識を覆し、「仕事中のリフレッシュにスポーツドリンク」という新たな広告戦略を打ち出しました。
この発想は、対象シーンをずらすことで新市場を開拓するという水平思考の成果です。
また、コピーライティングでも「機能を直接訴求する」のではなく、「意外性」や「ズレ」を取り入れた表現で注目を集めることが増えています。
アイデア勝負の世界では、ラテラルシンキングが武器になるのです。
製品開発における導入事例
家電メーカーが開発した使い捨て掃除機は、従来の「長持ちする=高品質」という価値観から脱却して誕生した製品です。
「掃除道具は頻繁に交換するほうが衛生的」という視点に着目し、低価格でも使い勝手に優れる製品としてヒットを記録しました。
このように、価値観や常識に疑問を持ち、異なる視点を取り入れることがイノベーションにつながるのです。
水平思考は、ただ面白い発想をするためのものではなく、実務レベルで利益を生む思考法であることが分かります。
ラテラルシンキング導入に失敗した企業の例と注意点
ラテラルシンキングは創造性を高める思考法として注目されていますが、正しく導入しなければ逆効果になることもあります。
実際に失敗事例も少なくありません。
一過性のブームで終わった失敗例
社員の発想力を高めようとラテラルシンキングを導入したA社は、研修を一度きりで終了。
その結果、思考法が浸透せず「面白い講習会」で終わってしまいました。
本来は継続的な実践が必要であるにもかかわらず、「イベント扱い」で終えたことで、社員の定着率はほぼゼロ。
導入には組織内での継続支援体制が不可欠であることが、この事例から明らかになっています。
チーム内に定着しなかった要因
B社では、マネージャーがラテラルシンキングを推奨したものの、現場レベルでは否定的な声が多数でした。
その原因は、評価制度が従来型の「正解重視」に偏っていたこと。
発想の柔軟性を奨励しない環境では、水平思考は根付かないのです。
成功の鍵は、制度や文化の見直しを伴った導入であり、形だけのトレーニングでは効果が得られません。
ラテラルシンキングに関するよくある質問
導入を検討する際、多くの人が抱く疑問を解消しておきましょう。正しい理解があってこそ、実践の成果が得られます。
一人でもトレーニングできますか?
はい、一人でも効果的にトレーニングできます。
例えば「前提を疑う」練習として日常の選択を見直したり、「水平思考クイズ」を解くことで脳を刺激できます。
加えて、自分の発想パターンを記録する習慣をつけると、改善点が明確になります。
ただし、第三者の視点を得ることでさらに深まるため、定期的に他者と議論するのもおすすめです。
ロジカル思考と併用できますか?
ラテラル思考とロジカル思考は対立するものではなく、補完関係にあります。
ロジカル思考が筋道を立てて「答えを導く」のに対し、ラテラル思考は「そもそもの問いを変える」力に優れています。
発想段階ではラテラル、整理段階ではロジカルというように、両者を場面によって使い分けることで、思考の幅と深さが飛躍的に向上します。
まとめ|ラテラルシンキングを習慣にして発想を進化させよう
ラテラルシンキングは、ただの思いつきではなく「新たな視点から本質を見抜く力」を養う方法です。
変化の激しい時代においては、正解のない課題に立ち向かう機会が増えています。
その中で求められるのは、型にとらわれない自由な発想です。
日々の生活や業務の中で意識的に取り入れれば、自ら問いを立て、道を切り開く力が育ちます。
今こそ、ラテラルシンキングを習慣にし、あなた自身の思考を進化させてみませんか。










