チームビルディングとは?目的や手法とメリットから具体例まで網羅解説
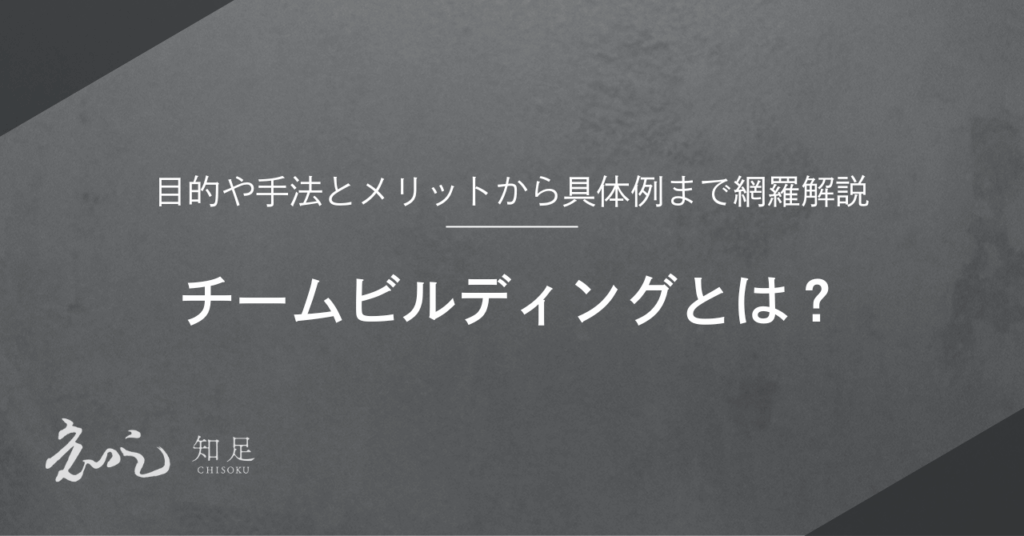
「多様なメンバーを一つにまとめたいのに、意見がかみ合わず思うような成果が出ない。」
そんな悩みを抱えていませんか。
人材の多様化が進むなか、上手に連携できるチームを作り上げることは大きな課題です。
そこで本記事では、チームビルディングの基本から具体的な手法、注意点やよくある質問まで丁寧に解説します。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
>>CFOのキャリアパスとは?なり方と年収、必要なスキル・役割まで徹底解説
目次
チームビルディングとは?
チームビルディングとは、複数のメンバーが力を合わせて目標を達成するために、環境や人間関係を整備しながら組織のパフォーマンスを高めるアプローチです。
個人の能力に依存しすぎる状態では、一時的な成果は得られても長期的な成長が難しくなる場合があります。
人間関係の摩擦や役割の曖昧さが生じると、チームとしての一体感が損なわれることもあるでしょう。
そこで必要なのがチームビルディングです。
役割の明確化やコミュニケーションの改善を行うことで、メンバーが心理的に安心して議論し合う雰囲気を育みやすくなります。
結果として、業績が上がるだけでなく、新しいアイデアや学びが生まれる土台を作れる点が大きなメリットです。
チームビルディングの目的
より高い成果を出せる組織に近づくために、どのような狙いが存在するか把握しておくことは有益です。
以下のサブトピックでは、チームビルディングで期待できる具体的な効果を深掘りします。
生産性や業績の向上
生産性や業績の向上とは、メンバー全員が同じ方向を向き、高いモチベーションを維持しながら成果を出す状態です。
個々がもつスキルセットを組み合わせ、互いを支え合うことが重要になります。
管理職やリーダーだけでなく、全員が主体的に動くとパフォーマンスが最大化しやすいです。
理由は、チーム内での情報共有や役割分担が円滑に機能すると、必要以上のコミュニケーションロスが減るからです。
加えて、一人がつまずいても仲間がフォローする仕組みがあれば、業務を前に進めやすくなります。
成果が目に見えて向上すれば、モチベーションも高まり好循環が生まれます。
実際のプロジェクトでは下記のような方法があります。
- 役割を明確にしたうえで、定期的に進捗共有
- タスク管理ツールで見える化し、だれでも状況が把握できる体制づくり
- 組織全体の目標からチーム単位での目標を連動させる
明確なゴールとそれを実現するプロセスが共有されると、組織全体の成果が向上しやすくなります。
離職率の低下と定着促進
チームビルディングがメンバーの定着につながる理由は、働く環境に対する安心感とやりがいが生まれるからです。
成長の機会やキャリアアップの可能性が見え、個人が尊重される空気感があると、組織に居続けたいと感じる人が増えます。
待遇や福利厚生だけに頼らない形で「ここで働きたい」と思わせる仕組みづくりができる点は、長期的な人材確保にも役立ちます。
イノベーションと学習の促進
チームビルディングを行うと、新しいアイデアや学習機会が増える可能性があります。
メンバーが積極的に意見を交わし、失敗を恐れず試行錯誤できる場が整えば、既存の手法にとらわれない発想が生まれやすいです。
従来の慣習では思いつかなかった方法を試してみる精神が育まれるため、市場の変化やテクノロジーの進歩にも柔軟に対応しやすくなります。
チームビルディングプロセスを理解する【タックマンモデル5段階】
人が集まって一つの組織を形成する過程には、段階的なステップがあります。
次の見出しでは、チームがどのように成熟し成果を出すかを理解するメリットを説明します。
形成期(Forming)
形成期は、メンバーが初めて集まり、互いの役割や人柄を探る段階です。
お互いに遠慮があるため、大きな衝突は起きにくいですが、実際の作業はまだスムーズに回りません。
役割が定まらないままだと業務が停滞しやすいため、早めにリーダーが方向性や目標を提示し、最低限のルールを共有することが望まれます。
混乱期(Storming)
メンバー各自が意見を出し始めるにつれ、衝突や意見の相違が顕在化することがあります。
衝突自体は悪いことではなく、むしろ組織として多様なアイデアを持つ機会です。
感情的な対立を放置すると溝が深まるリスクがあるため、調整役が対話の場を整えて合意形成を進める必要があります。
統一期(Norming)
混乱期を経た後、チーム内で共通の価値観やルールが確立し、協力体制が整うのが統一期です。
メンバーが互いの強みを理解し合い、相手に敬意を払った行動を取りやすくなります。
やりとりが円滑になることで、チーム全体のモチベーションも上がりやすいです。
機能期(Performing)
統一期で培ったルールや信頼関係が定着し、それぞれが自律的に動ける段階に入るのが機能期です。
指示や管理が細かくなくても、チームの方向性がぶれないため高い生産性が期待できます。
メンバー同士が助け合いながら柔軟に対応することで、難易度の高いタスクでも成果を出せる可能性が高まります。
散会期(Adjourning)
プロジェクトの終了や人事異動などの要因で、チームは解散する場合があります。
散会期では、これまでの成果や学んだことを振り返り、次のプロジェクトやキャリアに生かす準備をすることが重要です。
学びやノウハウを共有し合うことで、解散後の人材育成や社内知識の蓄積にも役立ちます。
チームビルディングの5つの手法【具体例】
複数のアプローチを理解すると、場面に応じた手法を選ぶヒントになります。
次の5つは代表的なもので、柔軟に組み合わせるのも効果的です。
① アイスブレイク/ゲーム型
ゲーム型のアイスブレイクは、初対面のメンバーが多い場合や、業務上のコミュニケーションが固くなりがちな職場で活用しやすいです。
簡単なクイズや体を動かすレクリエーションを行うと、緊張がほぐれ、お互いの人柄を知るきっかけになります。
短時間で導入できるものが多いので、定例会議の冒頭などに組み込むとチームの雰囲気が和らぎ、意見交換がしやすくなるメリットがあります。
② オフサイトミーティング
オフサイトミーティングとは、普段のオフィスや会議室を離れた場所で行うミーティングです。
社内で行う会議と違い、固定観念から解放されやすく、新鮮な環境で率直に意見を交換できます。
適度な非日常感が加わることで、仕事上の上下関係や立場の隔たりが薄まり、柔軟なアイデアが出やすくなるメリットがあります。
議題を決めて進める場合でも、自然とリラックスした雰囲気が作られやすいです。
レクリエーションや合宿形式でメンバー同士の親睦を深める例もあります。
③ プロジェクトベース学習(PBL)
実務に近い課題を解決するプロジェクトをチームで進める手法です。
学習内容を座学で終わらせるのではなく、実際のビジネスシーンを想定したタスクを設定し、メンバーが一体となって取り組みます。
アイデア出し、役割分担、スケジュール管理を全員で行うことで、協働による成果創出を実感しやすくなります。
新人社員の研修でも活用される事例が多く、目的達成に向けたモチベーションの高め方を学ぶ場としても有用です。
④ 1on1とフィードバックサイクル
定期的な1on1面談とフィードバックを取り入れることで、メンバーそれぞれの課題感や悩みを早期にキャッチできます。
上司が指示を下すだけではなく、メンバー自身が業務を振り返る場になると、主体的な成長意欲が高まりやすいです。
上司とメンバーの間で信頼関係が醸成されると、チーム全体のモチベーションを下支えする効果も期待できます。
⑤ ワークショップ型トレーニング
専門家やファシリテーターを招いて行うワークショップは、集中して学ぶ時間を確保できる手法です。
知識を得るだけでなく、ディスカッションやロールプレイで実践を積むことで、アウトプット中心の学習が可能になります。
自分の意見を伝える練習や他者との協力方法を学び、最終的には業務に直結するスキルを習得できます。
チームビルディングのやり方
ここでは具体的なステップを3つの視点で整理します。
目的に沿った手順を踏むと、チームの結束力を高めやすくなります。
現状診断とゴール設定(組織サーベイ活用)
まずは現状診断が欠かせません。
組織内のメンバーにアンケートやヒアリングを行い、どの程度コミュニケーションが活発か、人間関係に課題はないかを洗い出します。
最近は、オンラインで手軽に実施できる組織サーベイツールがあり、定点観測が可能です。
現状の課題とゴールを可視化すると、対策の優先順位や必要なリソースが見えてきます。
役割分担とルール決定
役割分担とルール決定とは、チーム内での責任範囲と運用ルールを明文化することです。
誰が何を担当するのかが不明確な状態だと、タスク漏れやコミュニケーションの混乱が生じやすくなります。
下記のようにルールを定めるとスムーズです。
- 会議体の開催頻度と担当者
- 報告・連絡・相談の方法
- 成果物のフォーマットと保管場所
明文化しておくと、特定のメンバーに業務が集中することを防ぎやすくなります。
適切なルールの下で働くことは、ストレスの軽減にもつながるため、チームのモチベーション維持にも有効です。
コミュニケーション設計と可視化
最後は、コミュニケーション設計と可視化です。
どのタイミングで、誰と何を共有するかが不明確だと、情報格差や誤解が生じやすくなります。
プロジェクト管理ツールやメンバー同士の定期報告を取り入れると、状況を見える化しながら進められます。
- 報連相ルール:連絡を入れるタイミング、報告スタイルを統一
- ミーティング時の議題設定:事前に資料や質問を共有
- 成果物の進捗共有:エクセルやツールで管理し、全員が閲覧可能にする
見える化を徹底すれば、誰が何を担当しているかが一目で分かるようになります。情報の行き違いによるミスが減り、本来の業務に専念できるため効率が上がります。
チームビルディングを行う際の注意点
下記ではチームビルディングを導入するときに陥りがちな落とし穴について整理します。
準備不十分のまま行うと期待した成果を得にくくなるため、あらかじめ注意しておきたいポイントです。
目的や期待値の共有不足
活動の目的や期待値をメンバー全員で共有していないと、「何のために行っているのか」が曖昧になりがちです。
形だけのチームビルディングになると、本来の成果向上やコミュニケーション促進に結びつかない場合があります。
進行役やリーダーが声掛けをして、全員が同じ視点を持てるように工夫すると良いです。
継続性の欠如(イベント化の落とし穴)
単発のイベントとして終わるチームビルディングは、多くの場合一時的な盛り上がりで終了します。
継続して取り組むためには、日々のミーティングやフィードバック機会の中に組み込むことが不可欠です。
長期的視点で進めることで、小さな変化を積み重ねて大きな組織改革にまでつなげられます。
リーダーシップ不在や責任の曖昧さ
リーダーシップが発揮されない状態では、意思決定の遅れやメンバー同士の対立が長引きやすくなります。
役職や肩書に関係なく、場を仕切るリーダーやファシリテーターの存在を明確にすることが重要です。
誰が調整役を担うのかが決まっていると、メンバーが迷わずに行動しやすくなり、スムーズな進行につながります。
チームビルディングと心理的安全性の関係
心理的安全性が高い組織では、メンバーが失敗を恐れずに発言や挑戦を行いやすいです。
言い換えれば、周囲の反応を気にせず意見を出せる環境があると、組織全体の生産性や創造性が向上すると考えられます。
メンバー間の信頼関係が築かれると、プロジェクトの成功確率も上がるため、チームビルディングは心理的安全性の確保と密接に結びつきます。
成長し合えるコミュニティを作るうえで、率直なフィードバックとポジティブな承認がカギになるのです。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査でも、働きやすい環境がイノベーション創出に寄与する可能性が示唆されています。
チームビルディングに関してよくある質問
チームビルディングに取り組む際に、多くの方が抱える疑問をまとめました。
回答とポイントを簡潔に説明します。
チームビルディングに必要な3要素は?
チームビルディングに必要な3要素は、目的・コミュニケーション・協力です。
明確な目的があれば、チームは迷いにくくなります。
コミュニケーションが活性化すると誤解や衝突を建設的に解決しやすくなり、協力が強まることで全体的な成果の質が上がります。
チームビルディングに必要なスキルは?
チームビルディングに必要なスキルは、リーダーシップ・ファシリテーション・傾聴です。
リーダーシップは方向性を示しながら人を巻き込む能力を指し、ファシリテーションは場をコントロールして多様な意見をまとめる役割を担います。
傾聴はメンバーの声を正しく理解するために欠かせない要素で、意見の相違が生じた際の調整にも役立ちます。
どのような効果があるのか?
どのような効果があるのかは、生産性向上・離職率低下・組織学習の加速です。
チームが一体となって活動すれば、複雑なプロジェクトも分担しやすくなり効率が上がります。
メンバー同士の連携と信頼が深まることで、心理的安全性が高まり、結果として新しいアイデアを生み出す土壌が育つのも特徴です。
職場の雰囲気が良くなると人材定着にも結びつくため、中長期的に見た競争力強化に直結します。
チームビルディングを行うメリットは?
チームビルディングを行うメリットは、風通しの良い職場環境が整い、メンバーが自発的に動くようになることです。
お互いを理解し合うことで意見を遠慮なく出せるようになり、成果創出のスピードやクオリティが上がります。
リーダーの管理負担が軽減される面もあり、組織全体でクリエイティブに動ける可能性が広がります。
チームビルディングのまとめ
チームビルディングは、組織内の人材や関係性を活かして成果を最大化するための取り組みです。
目的を明確にしながら、コミュニケーション活性化や役割分担の最適化を進めるとメンバー間の信頼感が強まり、結果として新しいアイデアの創出や業績向上が期待できます。
プロセスを理解し継続的に活動を行うことで、長期的な組織力の底上げと人材の定着にもつながります。










