人事評価制度サンプル一覧!評価シートの項目例や導入するメリットを紹介
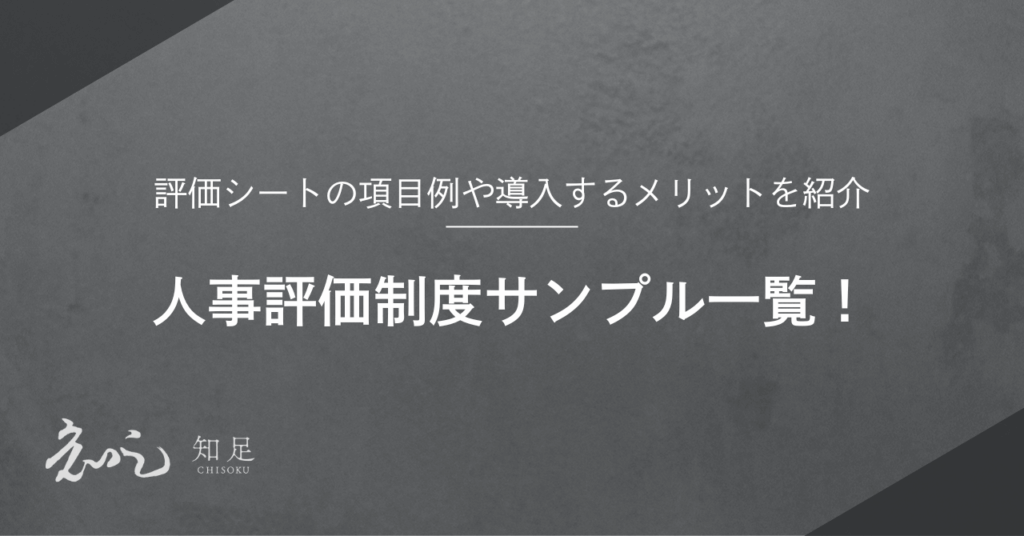
「人事評価制度を見直したいけれど、何から手をつければ良いかわからない」「自社に合った評価シートの作り方が知りたい」と感じていませんか。
曖昧な評価基準は社員の不満を招き、モチベーションの低下や離職につながる可能性があります。
そのまま放置すれば、組織全体の生産性が下がり、優秀な人材が定着しないという事態にもなりかねません。
本記事では、そうした悩みを解決するため、人事評価制度の基本的な考え方から、すぐに使える評価項目のサンプル、職種別のシート例までを網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、自社に最適化された、公平で納得感のある人事評価制度を構築するための具体的なステップが明確になります。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
>>幹部育成の重要性と育成方法!経営幹部を生み出すポイントを解説
目次
人事評価制度とは?
人事評価制度とは、社員の業績や能力、業務への取り組み姿勢などを一定の基準に基づいて評価し、処遇や育成に反映させる仕組みです。
単に給与や賞与を決めるだけでなく、社員の成長を促し、組織全体の目標達成に繋げるという重要な役割を担っています。
この制度の根幹には、企業の経営目標やビジョンが反映されている必要があります。
会社が社員に何を期待しているのかを明確に示し、社員一人ひとりの行動を組織が目指す方向へと導くための指針となるからです。
具体的には、評価の結果を基に昇進・昇格や異動配置を決定したり、個々の強みや課題に応じた研修プランを策定したりします。
適切に設計・運用された人事評価制度は、社員の納得感を高め、組織の活性化を促す強力なツールとなるのです。
人事評価シートと評価項目のサンプル例
具体的な評価シートのイメージを掴むことで、自社に合った制度設計がスムーズに進みます。
職種ごとのサンプルも参考に、評価項目の解像度を高めましょう。
人事評価シートとは?
人事評価シートとは、評価期間内における社員の目標達成度や業務遂行能力、勤務態度などを記録し、評価するための文書です。
評価者と被評価者の間で評価基準を共有し、客観的で公平な評価を行うための重要なツールといえます。
評価シートがあることで、評価のブレをなくし、評価結果の根拠を明確に残すことが可能です。
シートには通常、評価対象となる期間や被評価者の基本情報、評価項目とそのウェイト、具体的な評価基準、自己評価と上司評価の記入欄、そしてフィードバック面談の内容を記録するコメント欄などが設けられます。
このシートをもとに評価面談を実施することで、被評価者は自身の強みや課題を具体的に認識でき、次の成長へと繋げられるのです。
評価項目の例一覧
評価項目は、一般的に「成果評価」「能力評価」「情意評価」の3つの観点から設定されます。
それぞれの観点と具体的な項目例を理解し、自社の状況に合わせて組み合わせることが重要です。
| 評価の観点 | 概要 | 項目例 |
| 成果評価 | 業績や目標の達成度など、具体的な結果を評価する | ・売上目標達成率 ・新規顧客獲得数 ・生産性向上率 ・コスト削減額 |
| 能力評価 | 業務を遂行するために必要な知識やスキル、能力を評価する | ・企画力 ・問題解決能力 ・リーダーシップ ・専門知識 |
| 情意評価 | 業務に対する姿勢や勤務態度などを評価する | ・責任感 ・協調性 ・規律性 ・積極性 |
これらの項目をバランス良く組み合わせることで、多角的な視点から社員を評価できます。
企業の理念や文化、事業フェーズによって重視する項目は異なるため、自社が社員に何を求めているのかを明確にした上で設定しましょう。
職種別の評価項目サンプル
評価項目は、全ての職種で一律にするのではなく、それぞれの職務内容や役割に応じて最適化することが求められます。
職務の特性に合わない項目で評価すると、社員の納得感が得られず、不満の原因になりかねません。
ここでは、代表的な職種における評価項目のサンプルを紹介します。
| 職種 | 成果評価の例 | 能力評価の例 | 情意評価の例 |
| 営業職 | ・新規契約獲得数 ・既存顧客売上伸長率 | ・顧客関係構築力 ・交渉力 | ・目標達成意欲 ・フットワーク |
| 技術職 | ・開発プロジェクトの納期遵守 ・バグ修正件数 | ・技術習熟度 ・設計能力 | ・品質へのこだわり ・探求心 |
| 企画職 | ・企画の採用件数 ・担当サービスのROI | ・情報収集力 ・発想力 | ・創造性 ・粘り強さ |
| 事務職 | ・業務効率化の改善提案数 ・ミス発生率の低減 | ・PCスキル ・正確性 | ・協調性 ・機密保持 |
このように、職種ごとに求められる成果や能力は大きく異なります。
職務分析(ジョブディスクリプション)を丁寧に行い、それぞれの役割に即した評価項目を設定することが、公平で納得感のある評価制度の鍵となります。
評価シートのテンプレート
評価シートをゼロから作成するのは大変な作業です。
そのため、公的機関や民間のサービスが提供するテンプレートを参考にすると効率的です。
厚生労働省は、職業能力評価の基準をまとめた「職業能力評価シート」を公開しています。
事務系職種や営業・販売系職種、IT系職種など、業種や職種別に細かく分類されたモデル評価シートが用意されており、自社の評価項目を作成する上で非常に参考になります。
テンプレートを活用する際は、そのまま使うのではなく、必ず自社の経営方針や理念、行動指針(バリュー)に合わせてカスタマイズすることが重要です。
テンプレートはあくまで雛形と捉え、自社の状況に即した独自の評価シートを作成しましょう。
人事評価制度を導入するメリット4選
人事評価制度の導入は、企業に多くの好影響をもたらします。
社員と組織、双方の成長を促す具体的なメリットを確認していきましょう。
社員のモチベーション向上
人事評価制度は、社員のモチベーションを大きく向上させる効果があります。
会社が何を評価し、どのような行動を求めているのかが明確になるため、社員は日々の業務において努力の方向性を定めやすくなるからです。
目標達成や優れた行動が正当に評価され、昇給や賞与といった処遇に反映されることで、仕事への意欲や満足感が高まります。
さらに、評価を通じて上司から具体的なフィードバックを受ける機会は、自身の成長を実感する絶好の機会です。
承認欲求が満たされるだけでなく、キャリアパスが明確になることで将来への希望も持て、組織へのエンゲージメント強化にも繋がるでしょう。
公正/公平な人事の実現
人事評価制度を導入する大きなメリットは、人事評価の公平性や透明性を確保できる点にあります。
明確で具体的な評価基準が存在しない場合、評価は上司の主観や印象に左右されがちです。
「声の大きい社員が得をする」「上司との相性で評価が決まる」といった状況は、社員の不満や不信感の温床となります。
制度を導入し、全社で統一された基準とプロセスに基づいて評価を行うことで、個人的な感情や偏見が入り込む余地を減らせます。
評価結果の根拠が明確になるため、社員は評価に対する納得感を持ちやすくなり、ひいては会社への信頼感を醸成することに繋がるのです。
人材育成につながる
人事評価制度は、効果的な人材育成の基盤となります。
定期的な評価とフィードバック面談を通じて、社員一人ひとりの強みや弱み、今後の課題が明確になります。
上司は評価結果に基づいた具体的なアドバイスができるため、的を射た指導や育成計画の立案が可能です。
社員自身も、評価を通じて自己の現在地を客観的に把握できます。
これにより、自らのキャリアプランを考え、必要なスキルや知識を習得するための目標を立てやすくなるのです。
評価は単なる査定で終わるのではなく、社員の成長を促すための対話の機会として機能します。
結果として、組織全体のスキルレベルの底上げが期待できるでしょう。
業績向上への効果
最終的に、人事評価制度は企業全体の業績向上に大きく貢献します。
この制度は、企業の経営目標を個人の業務目標にまで落とし込む役割を担っています。
経営ビジョンや事業戦略が、部署の目標、そして各社員の目標へと具体的にブレークダウンされるのです。
これにより、社員一人ひとりの日々の業務が、会社全体の目標達成にどうつながっているのかを意識できるようになります。
全社員が同じ方向を向いて力を合わせることで、組織としての一体感が生まれ、戦略の実行力が高まります。
個々のパフォーマンスの最大化が、組織全体のパフォーマンス向上、ひいては業績向上へと直結する好循環を生み出すのです。
人事評価制度の作り方
効果的な人事評価制度を構築するには、段階を踏んだ丁寧な設計が不可欠です。
本パートを理解することで、自社に合った制度をゼロから構築するための具体的なステップを学び、計画的に導入を進められるようになります。
評価方針/評価項目の決定
まず初めに、評価制度の根幹となる方針を決定します。
企業の経営理念やビジョン、行動指針(バリュー)と連動させ、「どのような人材を評価し、育てていきたいのか」を明確にしましょう。
年功序列を重視するのか、成果主義を徹底するのか、あるいはその両方のバランスを取るのかといった方針が、後の評価項目や基準の土台となります。
方針が固まったら、具体的な評価項目を設定します。
先に述べた「成果評価」「能力評価」「情意評価」の3つの観点を基本に、自社の事業内容や職種ごとの特性を考慮して項目を洗い出しましょう。
経営層だけでなく、現場の管理職や社員の意見もヒアリングすることで、より実態に即した評価項目を作成できます。
評価基準/等級の設定
次に、各評価項目をどのレベルまで達成すれば良いのかを示す評価基準を設定します。
一般的には「S・A・B・C・D」のような5段階評価が用いられますが、各段階の定義を具体的に言語化することが重要です。
例えば、「A:期待を大幅に上回る成果を出した」「C:期待通りの役割を果たした」のように、誰が評価しても解釈がブレないような明確な基準を作成します。
同時に、社員の役割や責任範囲を示す等級制度も設計します。
一般社員、リーダー、管理職といった等級ごとに、求められる能力や成果のレベルを定義するのです。
この等級ごとの要件と評価基準を連動させることで、社員は次のステップに進むために何をすべきかが明確になり、キャリアアップの指針となります。
評価プロセスの設計
評価を「誰が」「いつ」「どのように」行うか、一連の流れ(プロセス)を設計します。
評価期間(半期に一度、年に一度など)を定め、その期間内にどのようなステップを踏むかを決めます。一般的なプロセスは以下の通りです。
- 目標設定:期初に上司と部下が面談し、評価期間の目標を設定する。
- 自己評価:期末に部下自身が目標の達成度や業務への取り組みを振り返り、評価シートに記入する。
- 一次評価:直属の上司が評価を行う。
- 二次評価:一次評価者のさらに上の上司が評価を行い、評価の甘辛調整を行う。
- 評価の確定・フィードバック:最終的な評価が決定され、上司から部下へ面談形式で結果と理由が伝えられる。
このプロセスを明確にルール化し、全社で共有することが、制度の円滑な運用には不可欠です。
評価シート/フォーマット準備
設計した評価項目や基準、プロセスを反映させるための評価シートや各種フォーマットを準備します。
評価シートは、評価内容を記録し、評価者と被評価者の認識を合わせるための重要なツールです。
前述のテンプレート例を参考に、自社の運用に合わせたフォーマットを作成しましょう。
多くの企業ではExcelやスプレッドシートが活用されていますが、近年では人事評価に特化したクラウドシステムを導入するケースも増えています。
システムの導入は、評価プロセスの効率化やデータの一元管理、分析などに大きなメリットがあります。
自社の規模や予算、目指す運用レベルに応じて最適なツールを選定することが重要です。
社員への周知と評価者トレーニング
新しい人事評価制度を導入する際は、全社員への丁寧な説明が不可欠です。
説明会などを開催し、制度の目的、評価の仕組み、処遇への反映方法などを詳しく周知します。
社員の疑問や不安を解消し、制度への理解と納得を得ることが、円滑な導入の鍵となります。
特に重要なのが、評価者となる管理職へのトレーニングです。
評価基準の目線合わせ、部下の目標設定支援の方法、効果的なフィードバック面談の進め方などを研修で徹底します。
評価者によって評価の厳しさや甘さにバラつきが出ないよう、具体的なケーススタディを交えながらトレーニングを行うことで、制度の公平性と信頼性を担保できます。
制度運用開始とフィードバック
準備が整ったら、いよいよ評価制度の運用を開始します。
導入初回は人事部が中心となって各部署の評価プロセスをサポートし、円滑に評価が実施できるようフォローしましょう。
評価期間終了後、各評価者は部下とのフィードバック面談を必ず行います。
評価結果は通知するだけでなく、面談で本人に直接伝えることで初めて価値を持ちます。
面談では「なぜその評価になったのか」を具体的に説明し、良い点はしっかり認め、改善点がある場合は今後どう取り組むかを一緒に考えるのです。
本人が評価に納得できない様子であれば、疑問や不満をできるだけ早く解消するよう努めましょう。
制度運用初期には、評価を伝える過程で制度の不備に気付くこともあります。
その場合は人事部で意見を集約し、評価基準の見直しや運用方法の修正など制度のブラッシュアップを行います。
このようにPDCAを回しながら、自社にフィットした評価制度へと育てていく姿勢が大切です。
フィードバックを通じて社員の成長を促しつつ、制度自体も改善を重ねていきましょう。
人事評価制度導入の注意点
新たに人事評価制度を導入・運用する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
ここでは、公平性の担保や社内の巻き込み、制度の継続的な改善、そして従業員の不満対策について解説します。
事前に注意点を押さえておくことで、制度の効果を最大限に引き出し、運用上のトラブルを防ぐことができるでしょう。
公平性/透明性の確保
人事評価制度では公平性と透明性を何より確保しなければなりません。
評価者の主観や好き嫌いで評価が左右されないよう評価基準を明確に定め、全評価者が共通のルールに従って評価することが重要です。
評価基準や評価プロセスは社内規程として文章化し、全社員に公開して制度をオープンにしましょう。
評価結果については、なぜその評価になったのか根拠を説明し、被評価者にフィードバックすることで納得感を高めます。
例えば、人事評価制度では「公平性・客観性・透明性・納得性」の四つの視点が求められると言われています。
- 公平性:評価者の好き嫌いではなく、定めたルールに従い正しく評価すること
- 客観性:評価エラーや主観に影響されないよう、事実や数値に基づき平等に評価すること
- 透明性:評価基準や評価の根拠、ルールを明確に定めて社内に開示すること
- 納得性:評価理由を適切に説明・フィードバックし、評価される側が理解・納得できるようにすること
評価制度の運用においては、常にこの4点を意識しておく必要があります。
評価者研修で公平・客観な評価の重要性を周知し、評価段階の定義やガイドラインを示すなど組織として評価の質を担保する仕組みを整えましょう。
そうすることで、社員に不信感を抱かせない公正な評価を実現できます。
経営層と現場の巻き込み
評価制度を機能させるには、経営層と現場双方の巻き込みが欠かせません。
制度設計の段階からトップマネジメントの意向を反映させるとともに、現場の管理職や従業員の声も取り入れて制度内容を検討することが大切です。
経営層が評価制度にコミットし、「なぜこの制度を導入するのか」「会社として何を評価したいのか」を明確に示すことで、全社的な理解と協力を得やすくなります。
一方、現場の実情を無視した制度は形骸化する恐れがあります。
現場社員から見て評価しづらい点や懸念事項はないか、事前に意見を集めて調整しましょう。
例えば、テレワーク導入で「在宅勤務者の評価が不利にならないか」といった声があれば、評価基準にプロセス観点を追加する等の対応が考えられます。
経営層と現場の間で十分に擦り合わせを行い、双方が納得した上で制度を導入することが成功の鍵です。
事前に多くの部署を巻き込んで作り上げた制度は、社員にとっても「自分たちの制度だ」という意識が生まれ、運用開始後の定着もスムーズになるでしょう。
定期的な見直し
人事評価制度は一度作って終わりではなく、定期的な見直しが必要です。
ビジネス環境や働き方は常に変化するため、導入当初は適切だった評価基準や運用方法も、数年後には合わなくなる可能性があります。
例えば、近年ではテレワークの普及により「従来の評価項目では在宅勤務者を正当に評価できない」という課題も生まれています。
また、長年同じ制度を運用していると形骸化やマンネリが起こり、社員の不満が蓄積するケースもあるのです。
ある調査では社員の約4割が自社の評価制度に不満を持っているとの結果もあり、不満を抱えたまま働くことは生産性の低下や離職につながると指摘されています。
こうした声に耳を傾け、制度に改善の余地があると分かったら機敏に見直しを行いましょう。
評価制度の見直し時には、現行制度の問題点を洗い出すためのチェックリストを使ったり、他社事例や新しい評価手法の情報を参考にしたりすると効果的です。
トレンドに安易に飛びつく必要はありませんが、自社の状況に合ったアップデートを重ねることで、常に制度を新鮮で有効な状態に保つことができます。
従業員の不満への対処
どれだけ精緻な制度を設計しても、全ての従業員が100%満足する評価制度を築くことは困難です。
評価結果に対する不満や疑問の声が上がることは、ある程度避けられません。
重要なのは、そうした不満に真摯に向き合い、適切に対処する仕組みを整えておくことです。
まずは、評価フィードバック面談を徹底し、評価結果の根拠を丁寧に説明する場を設けることが基本です。
それでも納得できない社員のために、異議申し立てができる窓口やプロセスを準備しておくことも有効です。
社員の声を無視せず、誠実に対応する姿勢を示すことが、最終的に制度への信頼を醸成することに繋がります。
人事評価制度に関してよくある質問
最後に、人事評価制度に関して多くの企業で寄せられる疑問についてQ&A形式で回答します。
無料の評価シート入手方法から評価手法の選択、目標やコメントの書き方のコツ、評価手法の違い、評価規程の作成ポイントまで、気になるポイントを解消し制度運用の参考にしてください。
無料で使える人事評価シートのサンプルはどこにある?
無料で使える人事評価シートのサンプルは、厚生労働省のウェブサイトで入手可能です。
厚生労働省は「職業能力評価シート」として、さまざまな業種・職種に対応したテンプレートを公開しています。
これを基に自社の状況に合わせてカスタマイズするのが効率的です。
また、インターネット上で「人事評価シートテンプレート無料」などと検索すると、コンサルティング会社やIT企業が提供するExcel形式のテンプレートも見つかります。
職種別に評価項目や基準はどう変えるべき?
職種別に評価項目や基準を変えるべきです。
職務内容によって、求められる成果やスキルは大きく異なるからです。
例えば、営業職であれば「売上目標達成率」が重要な成果指標になりますが、事務職であれば「業務の正確性や効率性」が重視されます。
各職種のジョブディスクリプション(職務記述書)を基に、その職務の成功に不可欠な要素は何かを分析し、評価項目に反映させることが重要です。
MBOの目標や自己評価コメントをうまく書くコツは?
MBO(目標管理制度)の目標設定では、「SMART」の原則を意識するのがコツです。
SMARTとは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Related(関連性)、Time-bound(期限)の頭文字を取ったものです。
自己評価コメントでは、設定した目標に対し、どのような行動を取り、どのような結果が出たのかを具体的な事実や数値を交えて記述しましょう。
単なる感想ではなく、客観的な事実を基に貢献度をアピールすることがポイントです。
相対評価と絶対評価はどちらがよい?分布制御は必要?
相対評価と絶対評価に絶対的な優劣はなく、企業の文化や目的によって選択すべきです。
相対評価は、組織内の順位を明確にし、人件費のコントロールがしやすいメリットがありますが、過度な競争を招くデメリットもあります。
絶対評価は、個人の成長を促しやすいですが、評価の甘辛が生じやすいです。
どちらの方式を採用するにせよ、評価者による評価のばらつきを抑えるための「評価者調整会議」の実施など、一定の分布制御の仕組みを設けることが望ましいでしょう。
評価規程には何を盛り込めばよい?
人事評価規程には、制度の透明性と公平性を担保するために、以下の項目を盛り込むことが一般的です。
- 総則:規程の目的、適用範囲、評価の基本原則など
- 評価の構成:評価期間、評価者、被評価者
- 評価項目と基準:成果・能力・情意評価などの具体的な項目と評価段階の定義
- 評価プロセス:目標設定からフィードバック面談までの流れとスケジュール
- 評価結果の活用:昇給、賞与、昇格など処遇への反映方法
- その他:異議申し立ての手続き、秘密保持義務など
これらの項目を網羅し、誰が読んでも理解できる形で明文化しておくことが重要です。
人事評価制度を活用し組織を成長させよう【まとめ】
人事評価制度は、社員の働きぶりを正当に評価して処遇に反映するだけでなく、社員の成長促進や組織の成果向上につなげる重要な経営ツールです。
本記事では、人事評価シートの項目例やテンプレート、制度導入のメリット、具体的な作り方の手順、運用上の注意点、そしてよくある質問への回答を総合的に紹介しました。
ポイントは、目的に沿った評価項目と公正な基準を定め、社員に制度を十分説明して納得感を得ること、そして運用しながら常に改善を重ねる姿勢です。
適切に設計・運用された人事評価制度によって社員のモチベーションと能力を引き出し、結果として組織全体の成長・業績向上へつなげていきましょう。













