PPM分析とは?事業戦略で差をつける4象限活用法を紹介!
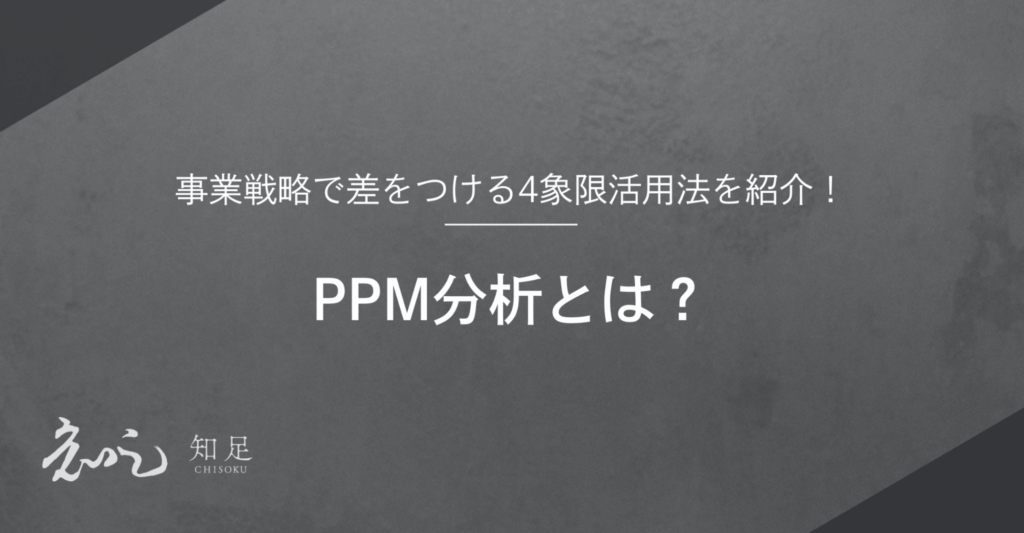
「事業の成長性と収益性をどう判断すればいいのかわからない」「限られた経営資源をどの事業に集中投資すべきか悩んでいる」
こんな課題を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。
複数の事業を手がけている企業では、どの事業にもそれなりの売上があるものの、「本当にこのまま続けていいのか?」という迷いが常につきまといます。
特に、創業時から続けている事業については、感情的な思い入れもあって冷静な判断ができないケースが多く見られます。
そんな時に有効なのがPPM分析です。この手法を活用することで、これまで「なんとなく」で判断していた事業戦略が、驚くほどクリアになります。
本記事では、PPM分析の基本概念から具体的な活用方法まで詳しく解説していきます。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
>>事業戦略ロードマップの作り方!手順をイメージ図の作成例付きで紹介!
目次
PPM分析とは?
PPM分析とは、Product Portfolio Management(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の略称で、企業が保有する複数の事業や製品を「市場成長率」と「相対的市場シェア」の2つの軸で分類・分析する経営戦略フレームワークです。
1970年代にボストン・コンサルティング・グループ(BCG)によって開発されたこの手法は、「BCGマトリックス」とも呼ばれています。
縦軸に「市場成長率」、横軸に「相対的市場シェア」を取り、事業を4つの象限に分類して可視化するのが特徴です。
PPM分析により、各事業の特性を理解し、限られた経営資源をどの事業に優先的に配分すべきかの判断が可能になります。
PPM分析が重要な理由
PPM分析が企業経営において重要な役割を果たす理由を、具体的なメリットとともに解説します。
経営資源の最適配分
限られた経営資源を最も効果的な事業に集中投資できます。
多くの企業では、すべての事業に平等に投資してしまいがちですが、客観的な判断ができていないケースが少なくありません。
PPM分析を導入することで、データに基づいた冷静な判断ができるようになり、全体の収益性が大幅に改善される傾向があります。
戦略的意思決定の支援
客観的なデータに基づいた戦略的意思決定を支援します。
創業の原点となる事業は、市場が縮小していることを薄々感じていても、思いが強くなかなか撤退の判断ができない場合があります。
PPM分析を活用することで、主観的な判断を排除し、市場データに基づいた冷静な判断ができるようになります。
PPM分析をするメリット
PPM分析を実施することで得られる具体的なメリットを、実際の成果とともに紹介します。
事業ポートフォリオの可視化
各事業が「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」のどこに位置するかを視覚的に確認することで、事業ポートフォリオ全体のバランスを客観視できます。
多くの企業では、分析結果を見て初めて「金のなる木」が少なく、「負け犬」が多いという現実に気づくケースがあります。これにより会社全体の収益性が上がらない理由が明確になります。
投資判断の明確化
PPM分析の原則に従って投資配分を見直すことで、全体の営業利益率が大幅に改善される事例が多く報告されています。
特に、「金のなる木」から得られた資金を「問題児」に集中投資することで、その事業を「花形」に押し上げることが可能になります。
戦略的撤退判断の支援
「負け犬」に分類された事業からの撤退は感情的には難しい決断ですが、人材と資金をより有望な事業に集中できるようになります。
PPM分析は撤退判断を含む戦略的意思決定を、データに基づいて客観的に行うための強力なツールです。
PPM分析の実施手順5ステップ
PPM分析を効果的に実施するための具体的な手順を、5つのステップに分けて解説します。
STEP1 市場成長率の算出
各事業が属する市場の成長率を算出します。
市場成長率(%)=[(当年市場規模÷前年市場規模)-1]×100
市場成長率の算出は最も時間のかかる作業の一つです。特に新しい業界では信頼できるデータが少なく、複数の情報源を組み合わせて推定する必要があります。
一般的に、市場成長率10%以上を「高成長」、10%未満を「低成長」として分類します。
STEP2 相対的市場シェアの計算
各事業の相対的市場シェアを算出します。
相対的市場シェア=自社の市場シェア÷最大競合他社の市場シェア
売上金額だけ見ていると気づきにくいですが、競合と比較することで現実的なポジションが見えてきます。
この値が1.0以上であれば市場リーダー、1.0未満であればフォロワーの位置にあることを示します。
STEP3 事業のマッピング
算出したデータを基に、各事業をPPMマトリックス上にプロットします。
このマッピング作業により、客観的な現実と向き合うことができます。
思い入れのある事業が「負け犬」に分類される場合もありますが、これを客観的な現実として受け入れることが重要です。
STEP4 4象限の分析と評価
「問題児」に分類された事業の判断が最も難しいとされています。
高成長市場にいるものの、シェアが低いという状況で、大きく投資してシェアを取りにいくか、早めに撤退するかの判断が求められます。
STEP5 戦略方向性の決定
四半期ごとにPPM分析を見直すことが推奨されます。特にデジタル関連の事業は市場の変化が激しいので、頻繁なチェックが欠かせません。
定期的な見直しにより、市場環境の変化に応じた迅速な戦略修正が可能になります。
PPM分析の4つの象限詳細
PPM分析で使用される4つの象限について、それぞれの特徴と戦略を詳しく解説します。
花形事業(Star)
高成長市場において高い市場シェアを持つ事業です。
Eコマース事業などが典型例として挙げられます。
市場は急拡大していますが、競合も次々と参入してくるため、システム投資やマーケティング投資を怠ることができません。
特徴
- 高い成長性と収益性を両立
- 多額の投資資金が必要
- 将来の「金のなる木」候補
戦略
- 市場シェア維持・拡大のための積極投資
- 研究開発や設備投資の強化
- マーケティング投資の拡大
投資は大変ですが、この事業が後に「金のなる木」となって会社を支える柱になる可能性が高いため、重要な投資判断となります。
金のなる木(Cash Cow)
成熟した市場において高い市場シェアを持つ事業です。
コンサルティング事業などが該当例として挙げられます。
市場自体の成長は鈍化していますが、長年培った顧客基盤とノウハウにより安定した収益を確保できる特徴があります。
特徴
- 安定した収益性
- 少ない投資で高いリターン
- 企業の収益基盤
戦略
- 効率性の向上とコスト削減
- 市場地位の維持
- 他事業への資金供給
この事業からの収益を新規事業投資に回すことで、ポートフォリオ全体のバランスを保つことができます。
問題児(Question Mark)
高成長市場において市場シェアが低い事業です。
AI関連のサービス事業などが該当します。
市場は確実に成長しているものの、競合が強く、なかなかシェアを伸ばせない状況が続くケースが多く見られます。
特徴
- 高い成長ポテンシャル
- 低い市場シェア
- 大きな投資リスク
戦略
- 選択的投資による花形化
- ニッチ戦略の検討
- 撤退判断の検討
特定の業界に特化したニッチ戦略を採用することで、この事業を「花形」に押し上げることが可能な場合があります。
負け犬(Dog)
低成長市場において市場シェアも低い事業です。
研修事業などが該当することがあります。
創業当初から手がけていた事業でも、データは明確にその事業の限界を示すことがあります。
特徴
- 低い成長性と収益性
- 限定的な投資価値
- 経営資源の非効率な使用
戦略
- 事業撤退・売却の検討
- 最小限の維持投資
- 経営資源の他事業への移転
「負け犬」事業からの撤退により、限られた経営資源をより有望な事業に集中することが可能になります。
PPM分析を活用した戦略立案
PPM分析の結果を基に、具体的な戦略立案を行う方法を解説します。
事業別投資戦略の決定
効果的な投資配分の例として、以下のような配分が考えられます:
- 花形事業:売上の15-20%を投資(業界平均範囲内)
- 金のなる木:売上の5-10%を投資(効率化重視)
- 問題児:選択した事業に売上の10-15%を集中投資
- 負け犬:段階的撤退のため投資ゼロまたは最小限
この配分により、全体の収益性が大幅に改善される事例が多く報告されています。
経営資源配分の最適化
人材配置の見直しは想像以上に効果的です。
特に、「負け犬」事業で経験を積んだベテラン社員を「問題児」事業に異動させることで、その事業の業績が劇的に改善されるケースがあります。
人材配置方針
- 優秀な人材:「花形事業」と有望な「問題児」に配置
- 「金のなる木」:効率性重視の運営体制
- 「負け犬」:段階的に人材を他事業に移転
事業撤退判断の指標
「負け犬」に分類された事業について、以下の観点から撤退を検討します:
- 将来的な市場成長の見込み
- シェア向上の実現可能性
- 撤退に伴うコストとリスク
- 他事業への影響
撤退判断は感情的に困難ですが、既存顧客への影響や従業員の処遇を含めて総合的に検討することが重要です。
PPM分析に役立つ補完フレームワーク
PPM分析の精度向上と戦略立案の質の向上を図るため、他の分析手法と組み合わせることが効果的です。
SWOT分析
毎年、PPM分析と同時にSWOT分析も実施することが推奨されます。
「問題児」に分類された事業でも、独自の強みがあれば花形化の可能性を見出すことができるからです。
各事業のStrengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)を分析し、PPM分析の結果と照らし合わせることで、戦略の妥当性を検証できます。
3C分析
顧客ニーズの変化、競合他社の動向、自社の能力を詳細に分析することで、PPM分析の精度向上と戦略立案の質の向上が図れます。
特に市場成長率の算出においては、3C分析で得られた洞察が重要な判断材料になります。
バリューチェーン分析
「問題児」事業でもバリューチェーン分析により、特定の工程で競争優位を持っていることが判明する場合があります。
その強みを活かした戦略転換により、その事業を「花形」に押し上げることが可能になります。
バリューチェーン分析により、各事業の強みや弱みをより具体的に把握し、PPM分析の結果を深く理解できるようになります。
PPM分析の実施体制とプロセス管理
PPM分析を効果的に実施するための組織体制とプロセス管理について解説します。
分析チームの組成
以下のメンバーでチームを組成することが推奨されます:
- 経営企画担当(チームリーダー)
- 各事業部責任者
- 財務・経理担当
- マーケティング・営業担当
- 外部コンサルタント(必要に応じて)
多角的な視点で分析できるよう、異なる専門性を持つメンバーを集めることが重要です。
客観性を保つために外部の経営コンサルタントにも参加してもらうことが効果的です。
データ収集と精度管理
データの精度確保が最も重要な要素の一つです。特に市場規模データは情報源によって大きく異なるため、複数のソースを組み合わせて検証することが不可欠です。
データ収集のポイント
- 業界団体統計の活用
- 調査会社レポートの比較検討
- 競合他社の公開情報分析
- 顧客ヒアリングによる実態把握
各四半期に1度、主要顧客5社程度にヒアリングを実施し、市場の実態を把握することが推奨されます。
PPM分析の効果測定と改善
PPM分析の導入効果を測定し、継続的な改善を図る方法について解説します。
ROIによる効果測定
PPM分析導入前後でROIを比較することで、効果を定量的に測定できます。
多くの企業で平均30%程度の改善が見られ、特に、「花形事業」への集中投資の効果が顕著に現れる傾向があります。
ROI=(投資による収益増加-投資額)÷投資額×100
市場シェア変化の追跡
投資戦略の実行後、各事業の市場シェアがどのように変化したかを定期的に測定し、戦略の有効性を評価します。
「問題児」事業への集中投資により、6ヶ月でシェアが向上し、最終的に「花形」事業へと成長させることが可能になるケースが報告されています。
KPI例:売上成長率・利益率
PPM分析の効果測定には、以下のKPIが有効です。
- 売上成長率:前年同期比での成長率
- 営業利益率:売上に対する営業利益の比率
- 市場シェア:対象市場における自社のシェア
- ROI:投資収益率
- キャッシュフロー:事業が生み出すキャッシュフロー
これらのKPIを月次で追跡し、PPM分析の結果と照らし合わせることで、戦略の修正や改善点を迅速に特定できます。
PPM分析に関してよくある質問
PPM分析にまつわる基本的な疑問について、よくある質問と回答をまとめました。
PPM分析とBCGマトリックスの違いは何ですか?
実質的に同じフレームワークです。
両者とも「市場成長率」と「相対的市場シェア」の2軸で事業を4つの象限に分類する手法であり、分析方法や活用目的に違いはありません。
PPM分析の限界と注意点は?
以下のような限界があることを理解して活用することが重要です。
主な限界点
- 短期的な財務指標に偏りがち
- 事業間のシナジー効果を考慮しにくい
- 定性的要因(ブランド価値など)の評価が困難
- 市場の定義によって結果が大きく変わる
PPM分析だけで全てを判断するのは危険です。特に事業間のシナジーについては別途検討が必要です。
中小企業でも活用できますか?
十分活用可能です。
従業員30名程度の会社でもPPM分析は非常に効果的です。むしろ中小企業の方が意思決定が迅速にできるため、分析結果を戦略に反映させやすいというメリットがあります。
中小企業の場合、製品ラインや事業部門レベルでの分析が効果的です。
どのくらいの頻度で見直すべきですか?
業界の特性と市場環境の変化速度によって決まります。
推奨見直し頻度
- IT・テクノロジー業界:3-6ヶ月
- 製造業:6-12ヶ月
- 伝統的産業:12ヶ月
デジタル関連事業を手がけている場合は、四半期ごとの見直しが推奨されます。
デジタル時代におけるPPM分析の有効性は?
デジタル時代においても、PPM分析の基本的な有効性は変わりません。
むしろ、デジタル技術により以下の点で分析精度が向上しています:
- リアルタイムでのデータ収集・分析が可能
- ビッグデータを活用した市場分析の高度化
- AIによる将来予測の精度向上
- ダッシュボードによる可視化の向上
BIツールを活用してリアルタイムでKPIを監視できるようになっています。
ただし、デジタル市場では市場の変化が極めて速いため、従来以上に頻繁な見直しと迅速な戦略修正が求められます。
BtoBとBtoCでの適用方法の違いは?
BtoBとBtoCでは、市場の定義方法と分析のアプローチに違いがあります。
【BtoB市場での特徴】
- 市場規模の把握が困難な場合が多い
- 顧客数が限定的で関係性が重要
- 長期契約によるスイッチングコストが高い
- 技術的優位性の影響が大きい
【BtoC市場での特徴】
- 市場データが豊富で分析しやすい
- ブランド力とマーケティングの影響が大きい
- 消費者の嗜好変化への対応が重要
- 規模の経済性が効きやすい
BtoB事業では顧客との関係性やサービス品質がシェアに大きく影響するため、定量データだけでなく顧客満足度調査なども併用して分析精度を高めることが重要です。
PPM分析のまとめ
PPM分析は、企業の事業ポートフォリオを客観的に評価し、戦略的な意思決定を支援する強力なフレームワークです。
PPM分析を導入することで、経営判断の質が格段に向上します。感情的な判断から脱却し、データに基づいた冷静な戦略立案ができるようになります。
特に、複数事業を展開する企業にとって、PPM分析は以下の価値を提供します。
- 事業ポートフォリオの客観的な可視化
- 投資優先順位の明確化と資源配分の最適化
- 戦略的撤退判断の支援
- 経営陣・投資家との議論の円滑化
ただし、PPM分析には限界もあるため、SWOT分析や3C分析、バリューチェーン分析などの他手法と組み合わせ、定性的要因も考慮した総合的な判断が重要です。
事業ポートフォリオの見直しを検討している経営者には、PPM分析の導入を強く推奨します。最初は簡易版からでも構いません。きっと新たな発見と改善の機会が見つかるはずです。
デジタル時代の激しい市場変化に対応するため、定期的な見直しと迅速な戦略修正を心がけ、企業の持続的成長を実現していきましょう。










