OKRの具体例と設定方法!成功させる運用ポイントや注意点を解説
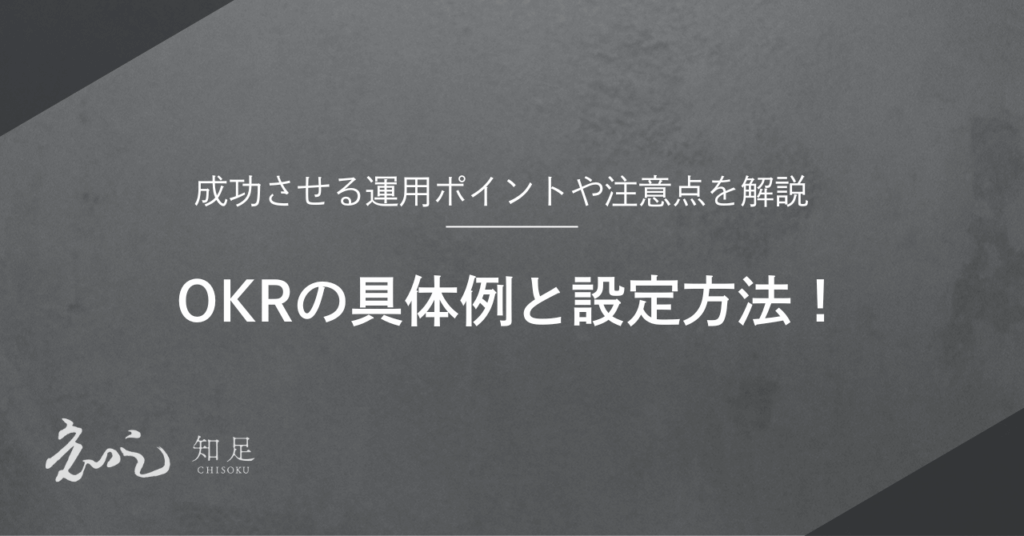
「チームの目標が曖昧で、社員の足並みがそろわない」「高い目標を掲げても、いつの間にか形骸化してしまう」このような悩みを抱えていませんか。
組織の成長が鈍化し、メンバーのモチベーションも低下している状況は、経営者やマネージャーにとって大きな課題です。
OKRは、壮大な目標を掲げ、チーム一丸となって挑戦するための強力なツールです。
本記事では、OKRの基本的な知識から、具体的な設定例、成功に導く運用ポイントまでを網羅的に解説します。
この記事を読めば、あなたの組織に革新的な成長をもたらすOKR導入の第一歩を踏み出せるはずです。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能
>>事業戦略ロードマップの作り方!手順をイメージ図の作成例付きで紹介!
目次
OKRとは?
OKRとは、「Objectives and Key Results(目標と主要な結果)」の略称で、組織や個人の目標を設定し、その進捗を管理するためのフレームワークです。
GoogleやIntelなどの世界的な企業が導入し、大きな成功を収めたことで注目を集めています。
厚生労働省の労働経済白書でも、OKRを用いた報酬制度が市場価値に迅速対応する事例として紹介されました。
OKRは、達成すべき野心的な「目標(Objective)」と、その目標の達成度を測定するための具体的な「主要な結果(Key Results)」の2つの要素で構成されます。
- 目標(Objective): チームや個人が「どこに向かうのか」を示す、定性的で心躍るような目標です。「顧客満足度を劇的に向上させる」や「業界で最も革新的な製品をリリースする」といった、 inspirational(意欲をかき立てる)なものが理想とされます。
- 主要な結果(Key Results): 目標達成への道のりを「どうやって測るのか」を示す、定量的で具体的な指標です。一つのObjectiveに対して、通常2〜5個のKey Resultsを設定します。例えば、「顧客満足度を劇的に向上させる」というObjectiveに対して、「NPS(ネットプロモータースコア)を20ポイント向上させる」「解約率を5%未満に抑える」「製品レビューの平均スコアを4.5以上にする」といった数値で測定できるKRを設定します。
OKRの最大の特徴は、会社全体の大きな目標から、部門、チーム、そして個人の目標へと一貫して連動している点です。
これにより、組織の全員が同じ方向を向いて業務に取り組むことができ、エンゲージメントの向上と、組織全体の大きな成果創出につながります。
OKRの設定方法
OKRを効果的に機能させるためには、その設定方法にいくつかの重要なポイントがあります。
本パートを理解することで、挑戦的でありながらも達成可能な、質の高いOKRを作成できるようになるでしょう。
Objective(目標)設定のポイント
Objectiveは、人を鼓舞するような定性的で挑戦的な目標を設定することが重要です。
ワクワクするような野心的な目標は、チームのモチベーションを高め、既成概念にとらわれない創造性を引き出す原動力となります。
短期的な期間、一般的には四半期(3ヶ月)で達成を目指すような、シンプルで覚えやすい目標が理想です。
「業界の常識を覆すプロダクトを開発する」「顧客から熱狂的に愛されるサービスを創出する」といった、心に響く言葉を選びましょう。
重要なのは、会社全体のObjectiveと部門、個人のObjectiveが連動していることです。
これにより、自分の仕事が会社の成功にどう貢献するのかを全員が理解できます。
Key Results(重要指標)数値化のコツ
Key Resultsは、Objectiveの達成度を測るための定量的な指標であり、具体的かつ測定可能でなければなりません。
数値で示すことにより、進捗状況を誰が見ても客観的に判断でき、目標達成に向けた具体的なアクションを促せます。
「顧客から熱狂的に愛されるサービスを創出する」というObjectiveに対して、例えば
- 「NPS(ネット・プロモーター・スコア)を30ポイント向上させる」
- 「有料会員の解約率を5%から2%に低減させる」
- 「ユーザーからの感謝メッセージをSNSで月間100件以上獲得する」
といった、3〜5個の具体的な数値目標を設定します。
達成度が60〜70%程度になるような、少し挑戦的なストレッチゴールにすることが、チームの成長を促すコツです。
【企業別】OKRの具体例
OKRは業種や組織の規模を問わず活用できるフレームワークです。
ここでは、様々な企業形態におけるOKRの具体例を見ていきましょう。
IT企業の例
IT企業では、変化の速い市場に対応するため、技術革新や顧客体験の向上がOKRのテーマになることが多いです。
スピード感とイノベーションを重視した目標設定が特徴です。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | 革新的なモバイルアプリでユーザーの日常を豊かにする |
| Key Result 1 | アプリのダウンロード数を3ヶ月で50万件達成する |
| Key Result 2 | MAU(月間アクティブユーザー数)を20万人まで増加させる |
| Key Result 3 | アプリストアのレビュー評価で平均4.5以上を維持する |
製造業の例
製造業におけるOKRは、生産性の向上、品質管理の徹底、コスト削減といったテーマが中心となります。
現場の効率化と製品価値の向上を両立させる目標が求められます。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | スマートファクトリー化を実現し、業界最高水準の生産体制を構築する |
| Key Result 1 | 製品1単位あたりの製造コストを15%削減する |
| Key Result 2 | 生産ラインの自動化率を40%から60%に向上させる |
| Key Result 3 | 不良品率を0.5%から0.1%まで低減させる |
| Key Result 4 | 従業員からの業務改善提案を四半期で100件集め、30%を実行に移す |
スタートアップの例
スタートアップでは、事業の急成長と市場でのポジション確立が最優先課題です。
そのため、OKRはプロダクトマーケットフィットの達成や資金調達、ブランド認知度の向上などに焦点を当てた、野心的なものになります。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | 主力プロダクトの市場シェアを確立し、シリーズAの資金調達を成功させる |
| Key Result 1 | MRR(月次経常収益)を500万円から1,500万円に成長させる |
| Key Result 2 | 有料課金ユーザーのチャーンレート(解約率)を3%未満に抑える |
| Key Result 3 | 業界トップティアのVC5社と面談し、1社以上から投資意向表明を得る |
| Key Result 4 | 主要メディアでの掲載記事数を10件獲得する |
非営利組織の例
非営利組織(NPO)のOKRは、そのミッション達成への貢献度を測ることに主眼が置かれます。
受益者への価値提供や、活動資金の確保、社会的な認知度向上が目標の中心となります。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | 地域の子どもたちの教育格差を是正し、未来の可能性を広げる |
| Key Result 1 | 学習支援プログラムの参加児童数を100人から200人に倍増させる |
| Key Result 2 | 参加児童の学力テストの平均点を10%向上させる |
| Key Result 3 | 活動資金として、新たに500万円の寄付を獲得する |
| Key Result 4 | ボランティアスタッフの登録者数を50人から80人に増やす |
【部門別】OKRの具体例
企業全体の目標を達成するためには、各部門がその役割に応じたOKRを設定し、連携して取り組むことが不可欠です。
本パートを理解することで、各部門がどのように会社全体の目標に貢献できるのか、その具体的な道筋を描きやすくなります。
マーケティング部の例
マーケティング部は、リード(見込み客)の獲得やブランド認知度の向上が主なミッションです。
OKRは、これらの成果を最大化するための戦略的な目標設定が求められます。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | デジタルマーケティングを強化し、業界トップのリードジェネレーションエンジンとなる |
| Key Result 1 | Webサイトからのオーガニック検索流入を30%増加させる |
| Key Result 2 | MQL(Marketing Qualified Lead)の獲得単価を20%削減する |
| Key Result 3 | 新規セミナーの参加者数を四半期で合計500名達成する |
| Key Result 4 | オウンドメディアの記事からのコンバージョン数を倍増させる |
営業部の例
営業部のOKRは、売上目標の達成はもちろんのこと、顧客との関係性構築や営業プロセスの効率化にも焦点を当てることが重要です。
単なる数字目標だけでなく、質の高い営業活動を目指します。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | 顧客の成功を第一に考え、信頼されるパートナーとして圧倒的な成果を出す |
| Key Result 1 | 四半期の新規契約受注額を1億円達成する |
| Key Result 2 | 既存顧客からのアップセル・クロスセルによる売上を3,000万円創出する |
| Key Result 3 | 顧客単価(ARPA)を15%向上させる |
| Key Result 4 | 営業プロセスのリードタイムを20%短縮する |
人事部の例
人事部のOKRは、優秀な人材の獲得・育成・定着を通じて、組織全体のパフォーマンスを向上させることが目的です。
エンプロイーエクスペリエンス(従業員体験)の向上が重要なテーマとなります。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| OKRの具体例 | |
| Objective | 最高の才能が集まり、成長し続ける魅力的な組織文化を創造する |
| Key Result 1 | エンジニア職の中途採用目標10名を達成する |
| Key Result 2 | 従業員エンゲージメントスコアを10ポイント向上させる |
| Key Result 3 | 新入社員の入社後1年以内の離職率を5%未満に抑える |
| Key Result 4 | 社内研修プログラムの満足度評価で平均90%以上を獲得する |
カスタマーサクセス部の例
カスタマーサクセス部は、顧客が製品やサービスを最大限に活用し、成功体験を得られるように支援する役割を担います。
顧客満足度の向上と解約率の低減がOKRの中心です。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | プロアクティブな支援で顧客を成功に導き、LTV(顧客生涯価値)を最大化する |
| Key Result 1 | 顧客のチャーンレート(解約率)を月次1%未満に抑制する |
| Key Result 2 | ヘルススコアが良好な顧客の割合を70%から85%に引き上げる |
| Key Result 3 | 顧客満足度(CSAT)調査で「満足」以上の回答率を95%にする |
| Key Result 4 | 導入事例コンテンツを10件作成し、Webサイトで公開する |
【個人】OKRの具体例
OKRは組織だけでなく、個人の成長を促すツールとしても非常に有効です。
本パートを理解することで、自身の役割やキャリアプランに合わせた目標を設定し、日々の業務を通じてスキルアップと組織への貢献を両立させる方法が分かります。
マネージャー職の例
マネージャーのOKRは、自身の目標達成だけでなく、チームメンバーの育成やチーム全体のパフォーマンス向上に焦点を当てることが特徴です。
チームの成果を最大化するための目標を設定します。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | データに基づいた意思決定ができる自律的なチームを作り上げる |
| Key Result 1 | チームメンバー全員が、担当業務のKPIを毎週レポーティングできるようにする |
| Key Result 2 | チームの主要プロジェクトの進捗達成率を平均80%以上にする |
| Key Result 3 | 週次の1on1ミーティング実施率を100%に保ち、議事録を残す |
| Key Result 4 | チームメンバーから360度評価で「育成支援」の項目で平均4.0(5段階評価)以上を得る |
一般社員の例
一般社員のOKRは、所属するチームのOKRと連携し、自身の担当業務においてどのような成果を出すかを具体的に設定します。
専門スキルを磨き、チーム目標に貢献することが中心となります。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | コンテンツマーケティングの専門家として、Webサイトの集客力を飛躍的に向上させる |
| Key Result 1 | 担当するブログ記事から、月間100件のホワイトペーパーダウンロードを達成する |
| Key Result 2 | SEOの知識を深め、担当キーワードのうち3つを検索順位10位以内に入れる |
| Key Result 3 | 新しい分析ツールを導入し、レポート作成時間を30%削減する |
| Key Result 4 | 月に1回、マーケティング関連の勉強会に参加し、学びをチームに共有する |
新入社員の例
新入社員のOKRは、まず業務の基本を習得し、チームの一員として貢献できる状態になることが目標です。
早期のキャッチアップと、主体的な学習姿勢を示すことが重要になります。
| OKRの具体例 | |
|---|---|
| Objective | 3ヶ月で独り立ちし、チームに不可欠な戦力として認められる |
| Key Result 1 | 担当する定型業務を、マニュアルを見ずに一人で完遂できるようになる |
| Key Result 2 | メンターからのレビューでの指摘事項を、次の週には50%以上改善する |
| Key Result 3 | 自社の主要製品・サービスに関するテストで90点以上を獲得する |
| Key Result 4 | チームメンバー全員とランチに行き、顔と名前、担当業務を覚える |
OKRを成功させる運用ポイント3選
OKRは、設定するだけで自動的に機能する魔法の杖ではありません。
その効果を最大限に引き出すためには、継続的な運用が不可欠です。
本パートを理解することで、OKRを形骸化させず、組織の成長エンジンとして機能させるための実践的な運用術を学べます。
可視化とフィードバックの仕組み化
OKRの進捗状況は、経営層から現場の社員まで、誰もがいつでも確認できる状態にしておくことが極めて重要です。
スプレッドシートや専用のOKRツールを活用し、全社のOKRツリーと各チーム・個人の進捗率を可視化しましょう。
透明性を高めることで、部門間の連携がスムーズになり、自分の業務が他の誰の目標に影響を与えているのかを理解できます。
また、週に一度の「チェックイン」と呼ばれる短い進捗確認ミーティングを設けるのが効果的です。
この場で進捗の共有、課題の相談、次のアクションの確認を行います。
定期的なフィードバックのサイクルを仕組み化することが、目標達成への確実な歩みにつながります。
ストレッチ目標60〜70%達成の意義
OKRで設定する目標は、簡単に達成できるものではなく、少し背伸びをした挑戦的な「ストレッチゴール」であることが推奨されます。
100%の達成が前提ではない点が、ノルマ管理型の目標(KPIなど)との大きな違いです。
一般的に、OKRの達成率は60〜70%程度が「成功」と見なされます。
この達成率が意味するのは、チームがコンフォートゾーン(快適な領域)を抜け出し、高い目標に果敢に挑戦した証しだということです。
100%の達成が続くようであれば、それは目標設定が低すぎるサインかもしれません。
失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性を確保し、ストレッチゴールを目指す文化を醸成することが、イノベーションや飛躍的な成長を生み出す土壌となります。
文化として根付かせるコミュニケーション術
OKRを組織文化として根付かせるには、トップの強いコミットメントと継続的なコミュニケーションが欠かせません。
経営層が自らのOKRを全社に公開し、その進捗について定期的に発信することで、OKRの重要性が社員に伝わります。
また、OKRは単なる管理ツールではなく、コミュニケーションツールであると認識することも大切です。
1on1ミーティングで上司と部下がOKRについて対話し、目標達成に向けた課題やキャリアについて話し合う機会は、エンゲージメントを高めます。
成功事例だけでなく、挑戦した結果の失敗談もオープンに共有し、学びを次に活かす文化を作りましょう。
こうした地道なコミュニケーションの積み重ねが、OKRを組織の血肉に変えていきます。
OKRを作る際の注意点
OKRは強力なフレームワークですが、設定や運用方法を誤ると期待した効果が得られません。
本パートを理解することで、OKR導入で陥りがちな落とし穴を避け、より効果的に活用するための具体的な注意点を把握できます。
KRを業務指標に寄せすぎない
Key Resultsを設定する際によくある間違いが、日々の業務タスク(ToDoリスト)をそのままKRにしてしまうことです。
例えば、「A社に提案書を提出する」「会議を5回開催する」といった活動は、それ自体が成果ではありません。
KRは、その活動によってもたらされる「結果」や「変化」を測定する指標であるべきです。
先の例で言えば、「A社から新規契約を獲得する」「会議の結果、プロジェクトの課題を3つ解決する」といった形が理想です。
常に「そのタスクを完了したら、どのような価値が生まれるのか?」と自問自答し、成果に基づいたKRを設定するよう心がけましょう。
数値目標と質的目標のバランス
OKRは、人を鼓舞する定性的なObjective(質的目標)と、その達成度を測る定量的なKey Results(数値目標)の組み合わせで成り立っています。
このバランスが崩れると、OKRはうまく機能しません。
KRが数値で測れることは必須ですが、そればかりを追い求めると、本来の目的を見失い、ただの数字遊びに陥る危険性があります。
一方で、Objectiveが具体的でなく、あまりに漠然としていると、チームは何を目指せば良いのか分からなくなります。
「なぜこの目標を追いかけるのか」というワクワクするような物語(Objective)と、「どうなれば達成と言えるのか」という冷静な指標(Key Results)の両輪を意識して設定しましょう。
四半期ごとの振り返りと見直し
OKRは一度設定したら終わりではありません。
ビジネス環境は常に変化しており、3ヶ月前に立てた目標が、現在も最適であるとは限りません。
そのため、四半期(3ヶ月)を一つのサイクルとして、定期的にOKR全体を振り返り、見直すプロセスが不可欠です。
四半期の終わりには、達成度のレビューだけでなく、「なぜ達成できたのか」「なぜ達成できなかったのか」「プロセスから何を学んだか」といった点をチームで深く議論します。
そして、その学びを次の四半期のOKR設定に活かしていくのです。
この振り返りと再設定のサイクルを回し続けることが、組織の継続的な学習と成長を促します。
ツールとテンプレートの活用
OKRの運用を効率的に進めるためには、ツールやテンプレートの活用が有効です。
特に組織の規模が大きくなるほど、スプレッドシートだけでの管理には限界が生じます。
OKR専用の管理ツールを使えば、全社のOKRツリーの可視化、進捗状況のリアルタイム更新、チェックインミーティングの管理、フィードバックの記録などが容易になります。
ツールの導入は、管理工数を削減するだけでなく、OKRの透明性を担保し、コミュニケーションを活性化させる効果も期待できます。
まずはシンプルなテンプレートから始め、運用の定着度合いに合わせて専用ツールの導入を検討するのが良いでしょう。
OKRに関してよくある質問
以降では、読者の疑問に回答していきます。
OKRとKPIの違いは?
OKRとKPIの最も大きな違いは、その目的にあります。
OKRが「どこを目指すか」という挑戦的な目標と方向性を示す羅針盤であるのに対し、KPI(重要業績評価指標)は「現状が順調か」を測る健康診断のメーターのようなものです。
OKRは野心的なゴールを設定し組織を鼓舞することを目的とし、達成度は60〜70%で成功と見なされます。
一方、KPIは日々の業務プロセスが正常に機能しているかを管理するための指標であり、達成度100%を目指すのが一般的です。
OKRとKPIは併用できますか?
はい、OKRとKPIは併用できます。
むしろ、両者を併用することで、より効果的な目標管理が可能になります。
OKRで「どこを目指すか」という挑戦的な目標を設定し、日々の業務のパフォーマンス管理はKPIで行う、という使い分けが一般的です。
例えば、営業部門がOKRで「新規市場でのシェアNo.1獲得」を目指しつつ、KPIでは「日々の架電数」や「商談化率」といった数値を管理する、といった形です。
OKRを導入するメリットは?
OKRを導入する主なメリットは以下の通りです。
- 優先順位の明確化: 組織全体で最も重要な目標に集中できます。
- 組織の連携強化: 会社の目標と個人の業務が繋がり、部門間の連携が促進されます。
- 従業員エンゲージメントの向上: 自分の仕事の意義を実感でき、モチベーションが高まります。
- 高い目標への挑戦: ストレッチゴールを目指す文化が醸成され、イノベーションが生まれやすくなります。
OKRのサイクル期間は?
OKRのサイクル期間は、一般的に四半期(3ヶ月)が推奨されています。
3ヶ月という期間は、市場の変化に迅速に対応できるだけの機敏さを保ちつつ、意味のある成果を出すのに十分な長さだからです。
会社の大きなビジョンを示すOKRは年単位で設定し、それを達成するための中期的な目標として、部門やチームが四半期ごとのOKRを設定するという階層構造を取ることが多くあります。
これにより、長期的な視点と短期的な集中力を両立させることができます。
OKRの具体例で組織を成長させる【まとめ】
本記事では、IT企業から非営利組織まで、様々な業種や部門、個人の具体的なOKR設定例を紹介しました。
OKRは、単なる目標管理の手法ではなく、組織全体のベクトルを合わせ、従業員一人ひとりの力を最大限に引き出すための強力なフレームワークです。
挑戦的で心躍るObjective(目標)と、その達成度を測る明確なKey Results(主要な結果)を設定することで、組織は迷うことなくゴールに向かって進むことができます。
週次のチェックインや四半期ごとのレビューといった運用を仕組み化し、コミュニケーションを活性化させながら、組織文化として根付かせて事業の目標達成に活かしてください。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能









