N1インタビューとは?成功するやり方とN1分析の進め方を徹底解説
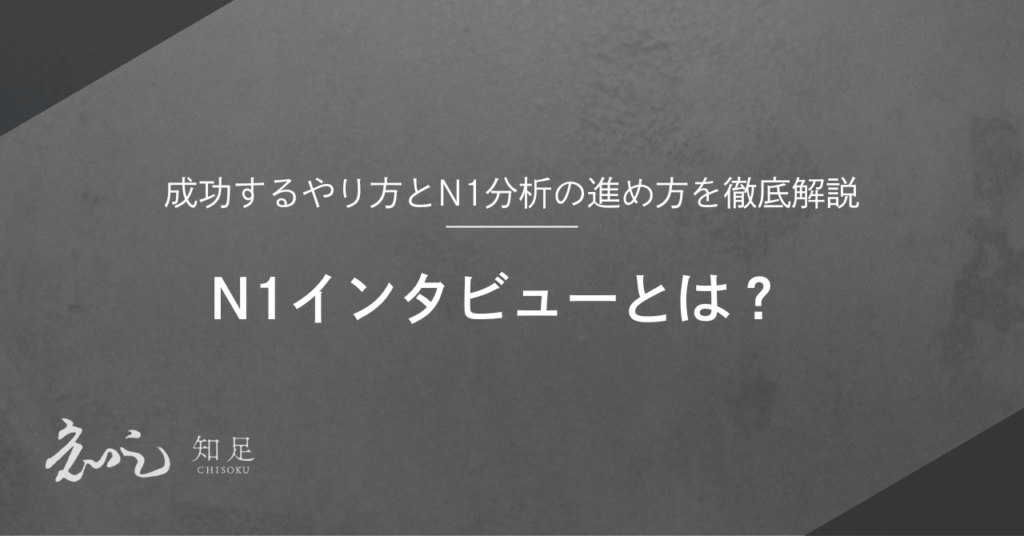
「自社のサービスがなぜか顧客に響かない」「マーケティング施策がいつも空回りしている」と感じていませんか。
多くの企業が直面するこの課題は、顧客の本当の声、つまり「インサイト」を掴めていないことが原因かもしれません。
たった一人の顧客と深く向き合う「N1インタビュー」は、顧客自身も気づいていない本音やニーズを掘り起こし、ビジネスを飛躍させる強力なヒントを発見する手法です。
この記事を読めば、N1インタビューの具体的なやり方から分析方法までを体系的に理解し、顧客に本当に求められるサービス開発やマーケティング施策を実行できるようになります。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能
>>受注分析のやり方!営業データを活かして受注率を上げる具体的手法と成功パターンを紹介
>>失注分析のやり方!営業で負けを勝ちに変える改善手順を紹介
目次
N1インタビューとは?
N1インタビューとは、特定の顧客一人(N=1)を対象に、その人の経験や価値観、行動の背景などを深く掘り下げていくインタビュー手法です。
アンケート調査のように多くの人から広く浅く情報を集める(定量調査)のとは対照的に、N1インタビューは一人の対象者から深く狭く情報を得る(質的調査)ことを目的とします。
なぜ「たった一人」にこだわるのでしょうか。
それは、商品やサービスの利用背景にある個人のライフスタイルや価値観、隠れた欲求といった「深層インサイト」は、平均化されたデータからは見えてこないからです。
一人の顧客を徹底的に理解することで、その背後にある共通の課題や本質的なニーズの仮説を導き出せます。
この仮説が、多くの人の心を動かす画期的な商品開発や、心に響くマーケティング施策を生み出す起点となるのです。
N1インタビューのメリットとデメリット
N1インタビューには、顧客を深く理解できる強力なメリットがある一方、注意すべきデメリットも存在します。
両方を理解することで、調査をより効果的に活用できます。
メリット:顧客の深層インサイトを把握
N1インタビューの最大のメリットは、顧客の深層インサイト、つまり行動の裏にある「なぜ?」を明らかにできる点です。
通常のアンケートでは「この商品に満足していますか?」という問いに「はい」と答えた理由は分かりません。
しかし、N1インタビューであれば「なぜ満足しているのですか?」「どのような点が特に気に入っていますか?」と深く掘り下げられます。
これにより、作り手側が想定もしていなかった商品の価値や、顧客が本当に解決したいと願っている課題を発見できるのです。
実際に、ある製品が「機能性」ではなく「所有する満足感」で選ばれていた、といったインサイトは、このような対話から生まれることが多く、次のプロダクト開発やコミュニケーション戦略に直結する貴重な情報となります。
- 感情の変化を時間軸で追えるため、潜在ニーズの背景まで理解できる
- 施策アイデアが具体的な行動イメージと結び付く
- 小規模ゆえに準備コストが抑えられ、スピード検証が可能
デメリット:サンプル数の限界とバイアス
N1インタビューのデメリットは、対象者が一人(あるいは少数)であるため、得られた結果を市場全体の意見として一般化するのが難しい点です。
その一人の意見が、たまたま特殊なケースである可能性は常にあります。
そのため、N1インタビューの結果だけで重要な経営判断を下すのはリスクが伴います。
また、結果はインタビュアーのスキルや、対象者との相性にも左右されます。
インタビュアーが無意識に特定の回答へ誘導してしまったり、対象者が「よく見せたい」という意識から本音を話してくれなかったりする「バイアス」が発生する危険性も考慮しなければなりません。
これらのデメリットを理解し、他の調査手法と組み合わせることが重要です。
- 個人特有の体験が全体傾向と錯覚されやすい
- 対象者選定が不適切だと示唆の質が大幅に低下
- インタビュアーの先入観が内容に混入しやすい
N1インタビューの流れ4ステップ
成功するN1インタビューは、周到な準備から始まります。
本パートを理解することで、インタビュー当日に質の高い情報を引き出すための土台を固められます。
1.目的設定と仮説立案
N1インタビューを始める前に、まず「何のためにインタビューを行うのか」という目的を明確に設定することが不可欠です。
目的が曖昧なままでは、質問が散漫になり、結局何が分かったのか分からない、という事態に陥りかねません。
例えば、「若年層向けの自社アプリの利用率が低い原因を探る」「新サービスの価格設定の妥当性を検証する」といったように、具体的で明確な目的を立てます。
次に、その目的に対する仮説、つまり「現時点で考えられる答え」を立てます。
「アプリのデザインが古いと感じられているのではないか」「競合サービスと比較して、月額料金が高いと思われているのではないか」といった仮説です。
この仮説があることで、インタビューで検証すべき点が明確になり、より鋭い質問ができるようになります。
2.対象顧客の選定基準
調査目的と相関が高い顧客を選ぶと、少人数でも厚みのある洞察を得られます。
例えば、「離脱直前のユーザー」に絞るなど、極端な事例を優先するのが鉄則です。
リクルート時は登録フォームに「直近の利用頻度」「失望したポイント」などのオープン質問を入れると、候補者の温度感がつかめます。
IPA「2024年度 中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」でも、経営層21者のインタビューで質的情報を収集し、量的アンケートと相互補完しました。
3.質問シナリオ作成のコツ
インタビュー当日の会話をスムーズに進め、聞き漏らしを防ぐために、あらかじめ質問のシナリオ(インタビューガイド)を作成します。
ただし、これは厳格な台本ではなく、あくまで話の流れの骨子です。
質問の順番は、対象者が話しやすいように、過去の経験から現在の状況、そして未来への期待へと時系列で流れるように構成するのが基本です。
特に重要なのは、相手が「はい/いいえ」で答えられない「オープンクエスチョン(開かれた質問)」を中心にするようにします。
「この機能は便利ですか?」ではなく、「この機能を使ってみて、どのように感じましたか?」と尋ねることで、相手は自身の言葉で具体的なエピソードや感情を語り始めます。
冒頭には緊張をほぐすアイスブレイクの時間を設けることも忘れないようにしましょう。
4.リクルーティングと日程調整
設定した基準に合う対象者を探し、インタビューを依頼するプロセスがリクルーティングです。
リクルーティングには、自社の顧客リストから探す、SNSで公募する、リサーチ会社に依頼するなど、様々な方法があります。
自社で実施する場合は、候補者にインタビューの目的、所要時間、謝礼の有無などを明確に伝えて協力を依頼します。
謝礼は、1時間あたり5,000円〜20,000円程度が相場ですが、対象者の専門性や希少性によって変動するのです。
日程調整は、候補日を複数提示するなど、相手の負担を軽減する配慮が大切です。
近年では、日程調整ツールを活用することで、スムーズにアポイントメントを確定できます。
N1インタビュー実施のポイント4選
インタビュー当日の進行が、引き出せる情報の質を大きく左右します。
本パートを理解することで、対象者から本音を引き出すための具体的な技術を学べます。
オンラインでの実施ポイント
現在、N1インタビューはZoomやGoogle Meetといったツールを用いたオンラインでの実施が主流です。
オンラインでは、対面に比べて相手の表情や場の空気が読み取りにくいため、いくつか工夫が必要です。
まず、通信環境が安定しているかをお互いに事前に確認しておくことが大前提となります。
インタビュー中は、意識的に対面よりも少し大きな相槌を打ったり、表情を豊かにしたりすることで、共感や関心を示し、相手が話しやすい雰囲気を作りましょう。
また、画面共有機能を活用して、プロトタイプやウェブサイトを一緒に見ながら話を進めると、具体的なフィードバックを得やすくなります。
移動の手間がない分、リラックスして参加してもらえるというメリットもあります。
対面での実施ポイント
対面でのインタビューは、オンラインでは捉えきれない細かなニュアンスや非言語的な情報を得られるという大きな利点があります。
相手の些細な表情の変化、身振り手振り、声のトーンなどから、言葉の裏にある本音や感情を読み取れる可能性があります。
実施場所は、相手がリラックスして話せるように、静かでプライバシーが保たれる会議室やカフェの個室などを選びましょう。
資料を見せる際は、プリントアウトしたものを用意すると、相手が手元でじっくり確認でき、会話に集中しやすくなります。
対面ならではの「場の空気」を大切にし、信頼関係を築くことで、より深いレベルでの対話が期待できます。
録画・録音・メモ取りのベストプラクティス
インタビューで得られる情報は非常に高密度なため、記憶だけに頼るのは危険です。
後から正確に振り返り、分析するために、対象者の許可を必ず得た上で録画・録音を行いましょう。
「分析のために録画させていただきますが、この内容が外部に公開されることは一切ありません」と丁寧に説明し、同意を得ることが必須です。
録画・録音があれば、分析時に会話の文脈や感情の機微まで再確認できます。
ただし、インタビュー中にメモを取ることも重要です。
これは全てを書き留めるためではなく、話の流れを整理したり、深掘りしたいキーワードを忘れないようにしたりするためです。
もし可能であれば、インタビュアーとメモ係の2人体制で臨むと、それぞれが役割に集中でき、より質の高い情報を収集できます。
本音を引き出すインタビューテクニック
対象者から本音を引き出すには、テクニック以前に「傾聴」、つまり相手の話に真摯に耳を傾ける姿勢が最も重要です。
尋問のようにならないよう、あくまで「あなたの話を聞きたい」というスタンスを保ちます。
具体的なテクニックとしては、相手の言葉をそのまま繰り返す「ミラーリング」(例:「〇〇と感じたんですね」)や、適度な相槌が有効です。
相手が言葉に詰まった時、焦って次の質問をするのではなく、あえて「沈黙」を待つことで、相手が考えを整理し、より深い内省から言葉を発してくれることもあります。
そして、話の重要なポイントでは「それは、なぜそのように思われたのですか?」「もう少し詳しく教えていただけますか?」といった深掘りの質問を投げかけ、インサイトに迫っていきます。
N1インタビュー結果をN1分析へ落とし込む方法
インタビューで得た貴重な情報を、具体的なアクションに繋げるための分析は不可欠です。
本パートを理解することで、膨大な発言から本質的なインサイトを見つけ出す手法を習得できます。
発言のコーディングとテーマ整理
インタビューの録画・録音データは、まず文字起こしを行い、テキストデータに変換します。
次に、その膨大なテキストの中から、顧客のニーズ、課題、感情、重要なキーワードなどが表れている発言を抜き出していく「コーディング」という作業を行います。
例えば、「設定が面倒だった」という発言には「#操作性の課題」、「これがあると友達に自慢できる」という発言には「#承認欲求」といったラベル(コード)を付けていきましょう。
この作業を繰り返した後、似たような意味を持つコードをグループ化し、「初期設定のハードル」「自己表現ツールとしての価値」といった、より抽象度の高い「テーマ」に整理していきます。
この地道な作業が、本質的なインサイトを発見するための土台となります。
インサイト可視化シート活用
コーディングとテーマ整理で構造化された情報を、さらに深く理解し、チームで共有しやすくするために、インサイトを可視化するフレームワークを活用します。
代表的なものに「カスタマージャーニーマップ」があります。
これは、顧客が製品やサービスを認知し、利用し、その後の体験に至るまでの一連の行動、思考、感情を時系列で可視化したものです。
各段階で顧客がどのような発言をし(Say)、何を考え(Think)、何を行い(Do)、どう感じたか(Feel)をマッピングしていくことで、顧客体験のどこに喜びの瞬間があり、どこに不満や課題(ペインポイント)が潜んでいるのかを一目で把握できます。
この可視化によって、チーム全体の顧客理解が深まり、具体的な改善策の議論へと繋がりやすくなります。
施策への転換と社内共有
分析から導き出されたインサイトは、具体的なアクションに繋げなければ意味がありません。
「初期設定のハードルが高い」というインサイトが得られたなら、「チュートリアル動画を導入する」「UIを改善する」といった施策のアイデアを立案します。
重要なのは、インサイトと施策案をセットで考えることです。
そして、分析結果と施策案をレポートにまとめ、開発チームやマーケティングチームなど、関係部署に共有します。
その際、専門用語を避け、誰にでも分かる言葉で、顧客の生の声を引用しながらストーリーとして伝えることが共感を得るコツです。
「〇〇さんは、この点について『まるで迷路のようだ』と話していました。
この課題を解決するために、〜という改善を提案します」といったように、具体的に伝えることで、組織全体を動かす力になります。
N1インタビューと併用したい調査手法
N1インタビューは万能ではありません。
他の調査手法と組み合わせることで、より精度の高い意思決定が可能になります。
定量調査とのハイブリッドアプローチ
N1インタビューで得られた「〇〇という課題があるのではないか」というインサイトは、あくまで一人の声から生まれた仮説です。
その仮説が、市場全体においてどの程度の人が感じている普遍的な課題なのかを検証するために、アンケートなどの定量調査が非常に有効です。
例えば、N1インタビューで「アプリの通知が多すぎて不快だ」という意見が得られた場合、その仮説を基に「アプリの通知頻度についてどう感じますか?」という設問をアンケートに組み込み、数千人規模で調査します。
このハイブリッドアプローチにより、「質」で発見したインサイトの「量」的な裏付けが取れ、施策の優先順位を客観的なデータに基づいて判断できるようになります。
ユーザビリティテストとの比較
N1インタビューと混同されやすい調査手法に「ユーザビリティテスト」があります。
両者は目的が異なります。
N1インタビューは、顧客のライフスタイルや価値観、ニーズといった「Why(なぜそう思うのか)」を探るのが主な目的です。
一方で、ユーザビリティテストは、ユーザーが製品やサービスを実際に使っている様子を観察し、「How(どのように使うのか)」「Where(どこでつまずくのか)」といった行動上の課題を発見することを目的とします。
例えば、「このボタンはなぜ押されないのか」という行動の背景にある心理を探るのがN1インタビュー、「そもそもユーザーはこのボタンに気づいているのか」を行動観察で確かめるのがユーザビリティテストです。
目的に応じて使い分ける、あるいは両方を組み合わせることで、顧客理解はさらに深まります。
N1インタビューに関してよくある質問
N1インタビュー実務では、細かな疑問が尽きません。
疑問を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出しましょう。
N1インタビューは何人に実施するべき?
目的によりますが、一般的には同じ顧客セグメントに対して5〜10人程度が目安です。
理由として、質的調査では5人を超えたあたりから、新しい発見やインサイトが出現する確率が徐々に低くなる「飽和」という現象が起こり始めると言われているためです。
ただし、調査したいターゲット層が複数(例:20代女性と40代男性)に分かれている場合は、それぞれのセグメントで3〜5人ずつ実施することが望ましいです。
N1分析とデプスインタビューの違いは?
N1分析は分析手法、デプスインタビューは調査手法です。
デプスインタビューは、特定のテーマについて対象者と1対1で深く掘り下げていくインタビュー手法全般を指す言葉です。
N1インタビューは、このデプスインタビューの一種と位置づけられます。
一方、N1分析は、そのインタビューで得られた情報(特に一人の顧客=N1の情報)を基に、本質的なインサイトを導き出し、事業のアイデアや施策に繋げるための一連の思考プロセスや分析手法を指します。
N1分析の提唱者は誰ですか?
P&G やロート製薬のマーケティング責任者、スマートニュース取締役CMOなどを歴任したマーケター西口一希氏が提唱者です。
西口氏は、実在する「たった一人(N=1)の顧客」を徹底的に観察・インタビューし、そこで得た深い洞察を普遍化して多くの人に届く価値を生み出すフレームワークを体系化しました。
このアプローチは、著書『ビジネスの結果が変わる N1分析 ― 実在する1人の顧客の徹底理解から新しい価値を創造する』(日本実業出版社、2024年)などで詳述され、現在の N1分析の代表的手法として浸透しています。
N1インタビューにかかる費用は?
費用はリクルーティング方法や謝礼によって大きく変動します。
自社の顧客リストなどを活用して自身で対象者を探す場合、かかる費用は対象者への謝礼が中心となり、1時間のインタビューで5,000円〜20,000円程度が一般的な相場です。
一方で、特定の条件に合う対象者を外部のリサーチ会社に依頼してリクルーティングする場合は、その手数料が加わり、1人あたり数万円から、場合によっては十数万円の費用がかかることもあります。
N1インタビューまとめ|インサイトをビジネス成果に繋げる3つのアクション
N1インタビューは、アンケートなどの定量調査では決して見えてこない、顧客のリアルな本音や隠れたニーズ、つまり「深層インサイト」を発見するための極めて強力な手法です。
一人の顧客と深く向き合うことで、製品開発やマーケティング戦略の方向性を照らす、質の高い仮説を導き出せます。
この手法を成功させるためには、①明確な目的と仮説に基づく周到な準備、②相手の本音を引き出す傾聴の技術、そして③得られた情報を具体的な施策に繋げる的確な分析、という3つの要素が不可欠です。
N1インタビューで得たインサイトは、単なる「良い話」で終わらせてはいけません。
それを具体的なサービス改善や新しいコミュニケーション戦略といった「アクション」に転換し、ビジネスの成果に繋げることこそが最終的なゴールです。
この記事を参考に、ぜひN1インタビューに挑戦し、顧客の心を掴むビジネスを実現してください。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能









