論理的思考を鍛える方法!論理的思考力を最速で伸ばす7つのステップ
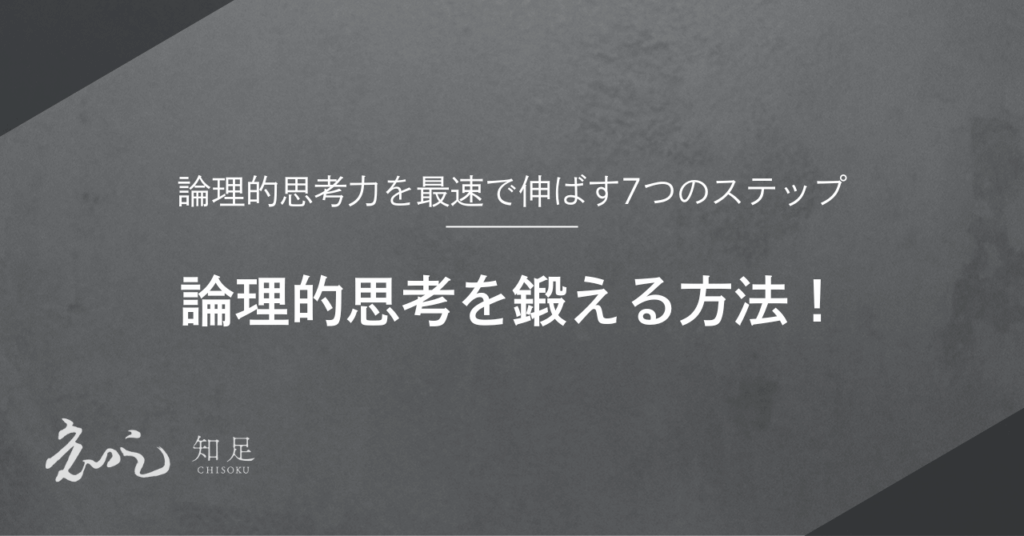
「なぜ、自分の話はうまく伝わらないのだろう」「複雑な問題を前にすると、どこから手をつけていいか分からない」。
このような悩みを抱えていませんか。
その状態が続くと、ビジネスシーンでの評価が下がり、大きなチャンスを逃してしまうかもしれません。
実は、その根本的な原因は「論理的思考力」の不足にある可能性があります。
しかし、論理的思考は才能ではなく、正しい方法でトレーニングすれば誰でも身につけられるスキルです。
本記事では、数あるトレーニングの中から即効性が高く、今日から実践できる7つのステップを厳選して解説します。
最後まで読めば、あなたの思考はクリアになり、仕事も人間関係も、よりスムーズに進められるようになるでしょう。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能
>>「as is」「to be」での分析とは?フレームワークや使い方を図解でわかりやすく説明!
目次
論理的思考とは?
論理的思考(ロジカルシンキング)とは、一言で言えば「物事を体系的に整理し、筋道を立てて矛盾なく考える思考法」のことです。
複雑に絡み合った情報や事象を、要素ごとに分解・整理し、それらの関係性を明らかにすることで、問題の本質を捉え、最適な結論を導き出します。
感覚や経験だけに頼るのではなく、「なぜそう言えるのか?」という根拠を常に明確にしながら思考を進めるのが特徴です。
これにより、自分自身の考えが整理されるだけでなく、他者に対しても説得力のある説明ができるようになります。
ビジネスシーンはもちろん、日常生活における様々な意思決定の場面で役立つ、現代社会を生き抜くための必須スキルと言えるでしょう。
論理的思考を鍛えるメリット
論理的思考を身につけることで、具体的にどのような良い変化があるのでしょうか。
ここでは、ビジネスシーンで特に重要となる2つのメリットを解説します。
意思決定の質が向上する
論理的思考を鍛えることで、意思決定の質が格段に向上します。
物事を客観的な事実やデータに基づいて判断できるようになるためです。
私たちは日々の生活や仕事の中で、大小さまざまな決断を迫られます。
その際に、感情や直感、あるいはその場の雰囲気に流されて判断を下してしまうと、後々後悔する結果になりかねません。
論理的思考が身についていると、複数の選択肢のメリット・デメリットを冷静に比較検討できます。
それぞれの選択肢がもたらす結果を予測し、最も合理的で成功確率の高いものを選び取ることが可能になるのです。
具体的には、新しい企画を立案する際に、市場データや過去の事例といった客観的な根拠を基に提案を組み立てることで、説得力が増し、承認される可能性も高まります。
問題解決スピードが上がる
問題解決のスピードが飛躍的に向上することも、論理的思考を鍛える大きなメリットです。
問題が発生した際に、その事象の表面だけを見て場当たり的な対応をするのではなく、根本的な原因は何かを突き止められるようになります。
原因と結果の因果関係を正確に捉えることで、的確な打ち手を見つけ出せるのです。
例えば、売上が低下しているという問題に対し、「とにかく広告を増やそう」と考えるのではなく、「なぜ売上が落ちているのか?」という問いから始めます。
すると、「新規顧客が減っているのか」「リピート率が下がっているのか」「客単価が落ちているのか」といったように、問題を分解して考えることができます。
原因を特定できれば、あとはその原因を解消するための具体的なアクションプランに集中できるため、無駄な時間やコストをかけずに問題を解決に導けるのです。
論理的思考を鍛える7つの実践ステップ
論理的思考は、特別な才能ではなく、トレーニングによって誰でも後天的に身につけられるスキルです。
本パートを理解することで、日常生活や仕事の中で意識的に取り組める、思考力を高めるための具体的な訓練方法が分かります。
①抽象語→具体語変換トレーニング
最初に実践すべきは、抽象的な言葉を具体的な言葉に置き換えるトレーニングです。
私たちは日常会話やビジネスシーンで、「あれ、やっといて」「なるべく早くお願いします」「いい感じにしておいて」といった曖昧な表現を使いがちです。
しかし、このような抽象的な言葉は、人によって解釈が異なり、誤解や手戻りの原因となります。
論理的思考の基本は、物事を明確に定義し、誰が聞いても同じ意味に捉えられるように表現することです。
例えば、「資料を分かりやすくまとめて」という指示を、「A4用紙1枚に、グラフを用いて主要な3つのポイントを箇条書きでまとめて」と言い換える練習をします。
このトレーニングを繰り返すことで、物事の解像度を高め、思考をクリアにする癖がつきます。
②Why を5回繰り返す深掘り
「なぜ?」を5回繰り返すことで、物事の本質的な原因を探るトレーニングも非常に効果的です。
表面的な事象に捉われず、その背後にある根本原因を突き詰める思考の癖をつけることができます。
トヨタ自動車の生産方式で用いられる「なぜなぜ分析」としても知られるこの手法は、因果関係を深く、正確に捉える力を養います。
例えば、「資料の作成が遅れた」という事象に対し、
- なぜ? → 必要なデータの収集に時間がかかった
- なぜ? → 〇〇部へのデータ依頼が遅れた
- なぜ? → 依頼内容の整理に手間取った
- なぜ? → どのデータが必要か明確に理解していなかった
- なぜ? → そもそも資料作成の目的を十分に把握していなかった
というように深掘りすることで、「目的の理解不足」という本質的な課題にたどり着けます。
この思考法を実践することで、対症療法ではなく、根本的な問題解決ができるようになります。
③5W1Hメモ術で情報整理
情報を整理する際に5W1H(When, Where, Who, What, Why, How)を意識したメモを取る方法は、情報を構造的に捉える訓練になります。
話を聞いたり文章を読んだりする際に、ただ漫然と情報を受け取るのではなく、これらの要素を意識的に整理するのです。
会議の内容をメモする際にも、「いつ(When)までに」「誰が(Who)」「何を(What)するのか」を明確にするだけで、情報の抜け漏れがなくなり、やるべきことが明確になります。
特に「なぜ(Why)」その行動が必要なのか、目的を常に意識することが重要です。
このメモ術を習慣化することで、複雑な情報も頭の中で自動的に整理され、論理的な思考の土台が強化されます。
④仮説→検証サイクルを回す
日常生活や仕事の中で常に「仮説→検証」のサイクルを回す意識を持つことは、実践的な論理的思考力を養います。
これは、単に物事を分析するだけでなく、未来を予測し、行動によってその予測が正しかったかを確認するプロセスです。
例えば、「この新しい広告デザインならクリック率が上がるのではないか(仮説)」と考え、実際に広告を出稿して結果をデータで確認する(検証)といった行動です。
もし仮説が間違っていたら、「なぜ間違っていたのか」を分析し、次の仮説を立てます。
このサイクルを繰り返すことで、経験とデータに基づいた精度の高い思考ができるようになります。
ビジネスでよく言われるPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを、個人の思考レベルで実践するトレーニングと言えるでしょう。
⑤ストラクチャリングで図解する
複雑な物事を文章だけで理解しようとすると、全体像や要素間の関係性が掴みにくいことがあります。
ストラクチャリング、つまり情報を構造化して図で表現する習慣は、論理的思考を可視化し、強化するのに役立ちます。
例えば、問題の原因と結果を線で結んだり、ロジックツリーやマインドマップを使って情報を整理したりする方法があるでしょう。
頭の中にあるモヤモヤとした思考を紙に書き出して図にすることで、要素の抜け漏れや論理の飛躍に自分で気づくことができます。
また、他者に説明する際にも、図を用いることで直感的な理解を促し、説得力を高める効果があります。
まずは簡単な線や丸で関係性を描くことから始めてみましょう。
⑥Teach-Back:人に説明する
学んだことや考えたことを自分の言葉で誰かに説明する「ティーチバック」は、知識の定着と論理の検証に絶大な効果があります。
人に分かりやすく説明するためには、まず自分自身が内容を完全に理解し、情報を体系的に整理し直す必要があるからです。
説明の途中で相手から「それはどうして?」「具体的にはどういうこと?」といった質問を受けることで、自分の思考の曖昧な部分や論理の穴が浮き彫りになります。
うまく説明できなかった箇所こそ、あなたの理解が不十分な点です。
同僚や友人に協力してもらうのも良いですし、誰もいない場所で声に出して説明してみるだけでも効果があります。
この方法は、自分の思考を客観的に見つめ直す最高の機会となります。
⑦ロジックゲームや問題集で実戦練習
論理パズルや推理ゲーム、市販されている論理的思考の問題集に取り組むことは、楽しみながら思考力を鍛える良い方法です。
これらのゲームや問題は、与えられた情報(ルールや条件)の中から、論理的な推論を積み重ねて唯一の正解を導き出すように設計されています。
数独やイラストロジックのようなパズル、あるいは推理小説を読んで犯人を特定する思考プロセスも、立派な論理トレーニングです。
重要なのは、答えを当てることだけでなく、「なぜその答えになるのか」という根拠やプロセスを自分の中で明確に説明できることです。
ゲーム感覚で取り組めるため、継続しやすく、日常生活や仕事とは異なる角度から脳を刺激し、地頭の良さを鍛えることができます。
論理的思考を鍛える考え方
本パートを理解することで、論理的思考を支える代表的な3つの推論方法を知ることができます。
これらの「考え方の型」を学ぶことで、自分の思考プロセスを客観的に分析し、より意識的に論理を組み立てられるようになります。
演繹法
演繹法(えんえきほう)は、一般的なルールや法則(大前提)に、個別の事象(小前提)を当てはめて、結論を導き出す思考法です。
有名な三段論法がその代表例です。
演繹法の例
- 大前提:すべての人間はいつか死ぬ。
- 小前提:ソクラテスは人間である。
- 結論:ゆえに、ソクラテスはいつか死ぬ。
ビジネスシーンでは、確立されたルールや自社の規則から、個別の事象に対する判断を下す際などに使われます。
前提が正しければ、結論も必ず正しくなるのが特徴ですが、前提そのものが間違っていると、結論も誤ってしまう点に注意が必要です。
帰納法
帰納法(きのうほう)は、複数の個別の事象や事実から、それらに共通する傾向やルールを見つけ出し、結論を導き出す思考法です。
演繹法とは逆向きのアプローチと言えます。
帰納法の例
- 事実A:商談A社は、事前に担当者のSNSをチェックしたら話が弾んだ。
- 事実B:商談B社も、事前に担当者のインタビュー記事を読んだら良好な関係が築けた。
- 事実C:商談C社も、事前に企業理念を深く理解していったら共感を得られた。
- 結論:商談の成功には、事前の情報収集が重要である。
市場調査の結果から顧客ニーズを推測したり、成功事例から法則性を見つけ出したりする際に有効です。
ただし、集める事実の数が少なかったり、偏りがあったりすると、誤った結論に至る可能性があります。
アブダクション
アブダクションは、ある事実(結果)を最も上手く説明できる仮説を導き出す推論方法です。
「結果→仮説」の流れで考えます。
- 事実(結果): 道が濡れている。
- 仮説(推論): (おそらく)雨が降ったのだろう。
演繹法や帰納法と異なり、必ずしも論理的に正しいとは限りません。
「水をまいた」「スプリンクラーが作動した」など、他の可能性も考えられるからです。
しかし、アブダクションは、情報が限られている中で、最もありえそうな原因を探り、次の一手を考えるための「仮説構築力」の源泉となります。
医者が患者の症状から病名を推測する、探偵が現場の状況から犯人像を推理するといった場面で使われる思考法です。
論理的思考を鍛えるために知っておくべきフレームワーク
論理的思考をより効率的かつ体系的に行うためには、先人たちが生み出した「フレームワーク」という思考の道具を知っておくと非常に便利です。
ここでは、特によく使われる3つのフレームワークを紹介します。
MECE
MECE(ミーシー)とは、「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の頭文字を取った言葉で、「モレなく、ダブりなく」という意味の分析思考の基本概念です。
物事を分析したり、問題を要素分解したりする際に、全体を網羅しつつ、各要素が重複しないように分類するための考え方です。
例えば、顧客層を分析する際に「20代」「30代」「40代」「50代以上」と分ければ、モレもダブりもありません。
しかし、「若者」「社会人」と分けると、「社会人の若者」がダブってしまい、MECEにはなりません。
MECEを意識することで、思考の抜け漏れを防ぎ、問題の全体像を正確に把握することができます。
あらゆる論理的思考の土台となる、非常に重要なフレームワークです。
ピラミッド構造
ピラミッド構造は、伝えたい主要なメッセージ(結論)を頂点に置き、その根拠となる複数の理由や事実を階層的に下に配置していく情報整理の手法です。
特に、説得力のある文章を作成したり、分かりやすいプレゼンテーションを行ったりする際に強力なツールとなります。
頂点に「何を言いたいのか」という結論を置き、そのすぐ下の階層に「なぜそう言えるのか」という主要な根拠を3つ程度並べます。
さらに、それぞれの根拠を裏付けるための具体的なデータや事例を下の階層に配置するのです。
この構造により、話の全体像と詳細な根拠の関係が一目で分かり、聞き手や読み手は論理の筋道を追いやすくなります。
自分の考えを整理し、他者に納得してもらうための基本構造です。
ロジックツリー
ロジックツリーは、あるテーマや問題を木の幹に見立て、その原因や解決策を枝葉のように分解・整理していくための思考ツールです。
問題を網羅的に洗い出し、その構造を可視化するのに役立ちます。
主に3つの種類があります。原因を掘り下げる「Whyツリー」、課題の構成要素を分解する「Whatツリー(イシューツリー)」、そして解決策を具体化していく「Howツリー」です。
例えば、「売上が低い」という問題をWhyツリーで分解すると、「客数が少ないから?」「客単価が低いから?」と枝分かれさせ、さらにその原因を掘り下げていきます。
これにより、問題の根本原因を特定したり、具体的なアクションプランを立てたりする際に、思考が整理されやすくなります。
論理的思考に関してよくある質問
ここでは、論理的思考に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
論理的な思考ができる人の特徴は?
論理的な思考ができる人の特徴は、物事を客観的に捉え、感情に流されずに行動できる点です。
常に「なぜ?」と問い、物事の根本原因や本質を探求する姿勢を持っています。
話が明快で分かりやすく、結論から話す傾向があるため、コミュニケーションがスムーズです。
また、複雑な問題を要素に分解して整理する能力に長けており、問題解決の場面で的確な判断を下すことができます。
前提を疑い、多角的な視点から物事を検証できるため、思い込みや偏見に基づいた誤った判断を避けることができます。
論理的思考ができないのはなぜですか?
論理的思考ができない主な理由は、思考の「癖」にあります。
多くの人は、客観的な事実よりも自分の感情や直感を優先して判断しがちです。
また、物事を深く考えずに表面的な情報だけで結論を出してしまったり、そもそも前提が正しいかを疑わなかったりすることも原因です。
知識や経験が不足しているために、適切な判断軸を持てない場合もあります。
これらは生まれつきの能力ではなく、後天的な習慣によるものが大きいため、意識的なトレーニングによって十分に改善することが可能です。
論理的思考がビジネスで必要な理由は?
論理的思考がビジネスで必要な理由は、再現性が高く、説得力のある成果を出すために不可欠だからです。
ビジネスの世界では、顧客、上司、同僚など、多様な関係者を納得させながら仕事を進める必要があります。
論理に基づいた説明は、個人の感覚や経験談よりも客観的で、誰にとっても理解しやすいため、合意形成をスムーズにします。
また、問題解決や意思決定の場面で、根拠に基づいた的確な判断を下すことは、事業の成功確率を高め、リスクを低減させることにつながります。
クリティカルシンキングとの違いは?
論理的思考(ロジカルシンキング)とクリティカルシンキングは密接に関連していますが、その焦点に違いがあります。
- 論理的思考: 物事を筋道立てて整理し、矛盾なく結論を導くこと。「AだからB、BだからC」と論理をつなげるスキル。
- クリティカルシンキング: 物事を無批判に受け入れるのではなく、「本当にそれは正しいのか?」「前提は間違っていないか?」と前提を疑い、多角的に吟味する思考法。
論理的思考が「論理を組み立てる」スキルだとすれば、クリティカルシンキングは「その論理の質を検証する」スキルと言えるでしょう。
両者は車輪の両輪のような関係にあります。
論理的思考を鍛える|まとめ
本記事では、論理的思考の基本的な概念から、それを鍛えるメリット、そして今日から実践できる7つの具体的なトレーニングステップまでを網羅的に解説しました。
論理的思考は、物事を体系的に整理し、矛盾なく筋道を立てることで、意思決定の質を高め、問題解決のスピードを向上させる強力なスキルです。
それは一部の特別な才能ではなく、「抽象語を具体語に変換する」「Whyを繰り返す」「人に説明する」といった日々の意識とトレーニングによって、誰もが着実に向上させることができます。
まずは、今回紹介した7つのステップの中から、最も取り入れやすいと感じたものを一つ選んでみてください。
例えば、明日の会議では「5W1Hを意識してメモを取る」ことから始めてみてはいかがでしょうか。
その小さな一歩が、あなたの思考を明晰にし、仕事や人生における様々な課題を乗り越えるための大きな力となるはずです。
論理という武器を手に、より良い未来を切り拓いていきましょう。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能












