属人化の解消方法とは?原因と5つの方法やメリットをわかりやすく解説
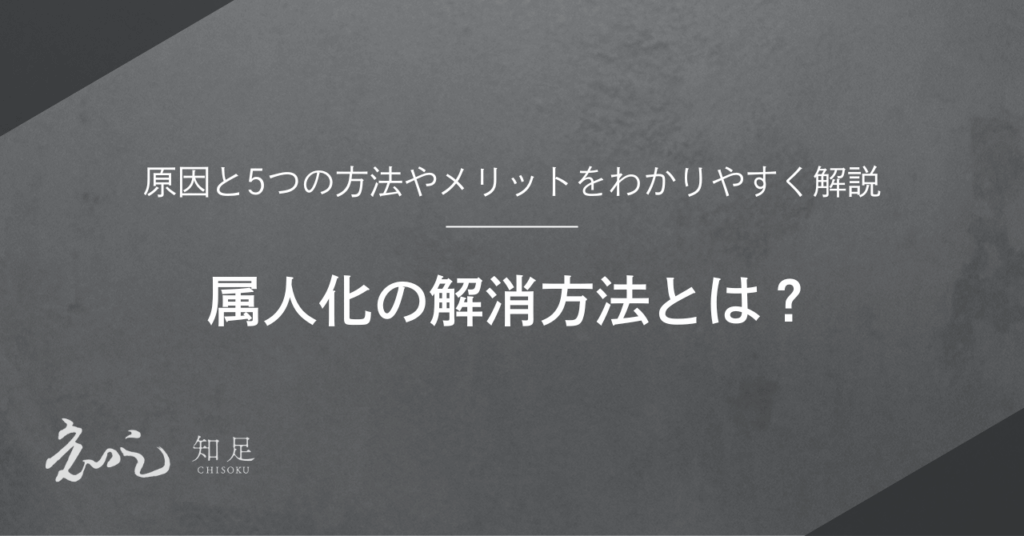
「この仕事はあの人にしかわからない…」そんな状況に心当たりはないでしょうか?
業務が特定の社員に依存する「属人化」は、放置すると業務停滞や品質低下など深刻な問題を招きかねません。
そこで本記事では、属人化とは何かを説明し、その原因とリスクを整理します。
その上で、属人化を解消する具体的な5つの方法と、解消によって得られるメリットをわかりやすく解説します。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
>>組織戦略の立て方とは?フレームワークと成功ポイント完全ガイド
属人化とは?
属人化とは、特定の業務を特定の従業員しか担当できず、その人以外には業務の進め方や詳細なノウハウがわからない状態を指します。
言い換えれば、業務が「人」に紐付いてしまっている状態です。
担当者のスキルや経験に業務の成果が大きく依存するため、一見するとその人の専門性が高いように見えるかもしれません。
しかし、組織全体で見た場合、その担当者が不在になると業務が完全に停止してしまうリスクを抱えています。
業務プロセスや知識が共有されていないため、他の従業員が代わりを務めることが極めて困難になるのです。
このような状況は、業務のブラックボックス化を招き、組織の柔軟性や対応力を著しく低下させる要因となります。
属人化によって生じるリスク
属人化を放置すると、組織に様々な悪影響が及びます。
ここでは、具体的にどのようなリスクが発生するのかを詳しく見ていきましょう。
業務効率の低下/停滞
業務効率の低下・停滞とは、属人化によって仕事の進行が遅くなったり、止まってしまったりする問題です。
特定の社員しか対応できない業務があると、その社員が不在になった際に業務全体が滞ります。
実際に担当者以外に代行者がいなければ作業が進まず、関連する業務まで玉突き的に遅延し、生産性が著しく低下してしまいます。
例えば、顧客対応を属人化させている場合、その担当者の休暇中に対応が遅れると顧客満足度の低下にもつながりかねません。
このように属人化は業務全体のスピードを鈍らせ、結果として企業の生産性を下げてしまうのです。
品質の不安定化
成果物の品質が、担当者のスキルや経験、さらにはその日のコンディションに左右されるようになります。
ベテラン担当者が作れば高品質なものができあがる一方で、他の人が見よう見まねで対応すると品質が大きく低下する、といった事態が頻発します。
これでは、組織として顧客に安定した品質のサービスや製品を提供することができません。
品質のばらつきは、顧客からの信頼を損ない、長期的な関係構築の妨げとなるでしょう。
クレーム対応に追われるなど、余計なコストが発生する原因にもなります。
人材流出時の損失
人材流出時の損失とは、担当者の急な離脱によって業務ノウハウが失われるリスクです。
突然キーパーソンが休職・退職・異動した場合、属人化していた業務では蓄積されたノウハウが一緒に失われてしまう可能性が高くなります。
例えば、担当者が急病で長期離脱したケースを考えてみましょう。
属人化により属人的なノウハウが共有されていない業務では、代替要員が手順を再現できず、元の品質を維持できなくなるでしょう。
このように属人化はノウハウの組織内蓄積を阻害し、退職者とともに知見が流出してしまう危険性があります。
結果として、新任者が一からやり直す非効率が発生し、企業にとって大きな損失となります。
従業員の負担増
業務を一手に引き受ける担当者は、常に過大な業務量と責任を抱えることになります。
自分がいなければ仕事が回らないというプレッシャーから休みを取りにくくなり、心身ともに疲弊してしまうケースも少なくありません。
このような状態は、エンゲージメントの低下や離職につながるリスクを高めます。
また、周りの従業員も「あの人に聞かないと分からない」という状況にストレスを感じ、チーム全体の協力体制や士気の低下を招く原因となります。
属人化が発生する主な原因
属人化の背景には、組織や業務のさまざまな問題が潜んでいます。
ここでは、業務が属人化してしまう主な原因を4つ取り上げます。
原因を把握することで、自社のどこに改善の余地があるかを見極め、効果的な対策につなげやすくなるでしょう。
情報共有の不足
情報共有の不足は、属人化を引き起こす大きな要因です。
社内でナレッジ(有益な情報や経験)が適切に整備・共有されていないと、特定の人だけが知識を抱え込みがちです。
例えば、営業現場で、ベテラン社員が商談ノウハウや顧客情報を自分のメモだけに記録し共有しなければ、その人以外は状況を把握できません。
その結果、「その件は○○さんしかわからない」という属人化が起こってしまいます。
さらに、ナレッジ共有が評価されない職場風土だと社員は自分だけの知識で優位性を保とうとしてしまい、なおさら情報共有が進まない悪循環に陥ります。
逆に言えば、知識や情報をみんなで共有する仕組みや文化を構築しない限り、属人化はどんどん進行してしまうのです。
業務の繁忙/人手不足
日々の業務に追われ、マニュアルの作成や後進の育成といった緊急性の低い業務に時間を割けないことも大きな原因です。
特に、人手不足の職場では、一人ひとりが目の前のタスクをこなすことで手一杯になりがちです。
新しいメンバーに丁寧に教える余裕がなく、「自分でやった方が早い」という判断が繰り返されることで、結果的に業務が特定の人に集中し、属人化が進行してしまいます。
中小企業庁の調査でも、多くの中小企業が人手不足を経営上の課題として挙げており、これが業務の標準化を妨げる一因となっています。
マニュアル未整備
業務手順を記録したマニュアルが存在しない、あるいは存在していても情報が古く、実際の業務内容と乖離しているケースも原因の一つです。
マニュアルが整備されていなければ、新任者や他の従業員が業務を学ぼうとしても、担当者に直接やり方を聞くしかありません。
これでは、いつまで経っても担当者への依存から抜け出せません。
マニュアルを作成し、定期的に更新する運用ルールが確立されていない組織では、知識が個人に蓄積されやすく、属人化が起こりやすい環境といえるでしょう。
経営層の認識不足
経営層や管理職の問題意識の欠如も、属人化を長引かせる原因になります。
企業文化として「属人化は仕方がない」「あの人に任せておけば大丈夫」という空気があると、トップが積極的に是正しないまま現場任せになってしまいます。
属人化を解消するには、まず経営層がその問題点を正しく理解し、解消の必要性を認識することが大切です。
トップがリーダーシップを発揮して社内に意識改革を促さなければ、現場だけで属人化を脱却するのは困難でしょう。
事実、従来の日本企業では属人化が発生しやすい文化が見られ、問題を認識しつつ放置されているケースも少なくありません。
経営陣が属人化によるリスクと、解消によるメリットを明確に示し全社に共有することが、脱属人化の第一歩となります。
属人化を解消する方法5選
属人化のリスクと原因を理解した上で、具体的な解消方法を見ていきましょう。
ここでは、どのような組織でも実践可能な5つのステップを紹介します。
業務の可視化と棚卸しを行う
属人化解消の第一歩は、現状を正確に把握することです。
「誰が」「何を」「どのように」行っているのか、全ての業務を洗い出します。
各業務の担当者、作業内容、所要時間、発生頻度などをリストアップし、一覧化しましょう。
次に、業務フロー図などを用いて、プロセス全体を視覚的に整理します。
この作業を通じて、業務が特定の個人に集中している箇所や、手順がブラックボックス化している部分が明確になり、どこから手をつけるべきかの優先順位を判断できるようになります。
業務手順の標準化・マニュアル化
業務の可視化によって属人化している業務が特定できたら、次にその手順を標準化します。
担当者の経験や勘に頼っていた部分を言語化し、誰が担当しても同じ成果を出せるような、明確で具体的なルールを定めます。
そして、その標準化された手順をマニュアルとして文書化しましょう。
作業の目的、具体的な操作手順、判断基準、注意点、トラブル発生時の対処法などを詳細に記載することが重要です。
作成したマニュアルは、定期的に見直しと更新を行う仕組みを整えることで、形骸化を防ぎます。
ナレッジ共有ツールの導入/活用
作成したマニュアルや業務に関するノウハウ、よくある質問などを、組織全体で簡単に閲覧・検索できる仕組みを整えることが有効です。
具体的には、社内wiki、情報共有ツール、ビジネスチャットツールなどを活用します。
これらのツールを導入することで、知識が個人のパソコンの中だけでなく、組織の共有財産として蓄積されていきます。
ツール導入と同時に、情報を積極的に共有する文化を醸成することも大切です。
わからないことがあれば、まずツールで検索する習慣を根付かせましょう。
業務担当の分業/ローテーション
特定の担当者に業務が集中しないよう、複数の従業員で業務を分担できる体制を構築します。
一つの業務を複数人で担当するペアプログラミングや、主担当と副担当を置く制度が有効です。
さらに、定期的に担当業務を入れ替える「ジョブローテーション」を導入することも効果的です。
これにより、一人の従業員が様々な業務を経験でき、幅広いスキルを習得できます。
結果として、誰かが急に休んでも他の人がカバーできる「多能工化」が進み、変化に強い柔軟な組織体制が実現します。
外部リソース/自動化の活用
全ての業務を内製化することに固執する必要はありません。
高度な専門性が求められる業務や、季節的に発生する繁忙期の業務などは、外部の専門業者へ委託(アウトソーシング)することも一つの選択肢です。
また、請求書発行やデータ入力といった定型的な繰り返し作業は、RPA(Robotic Process Automation)などのツールを導入して自動化することも検討しましょう。
これにより、従業員はより創造性や判断力が求められる付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性の向上にもつながります。
属人化を解消するメリット
属人化の解消は、リスク回避だけでなく、組織に多くのポジティブな効果をもたらします。
ここでは、企業成長につながる4つの主要なメリットを解説します。
業務効率/生産性の向上
属人化を解消すると業務の効率化と生産性アップが期待できます。
業務内容やノウハウを複数人で共有することで、一人では見落としがちな課題にも気付きやすくなり、プロセスの改善につながるためです。
また、複数人で分担できるようになれば業務量の偏りが解消され、進捗の遅延や停滞を防ぐことにもつながります。
実際に属人化を解消した企業では、「これまでは担当者不在で止まっていた作業が他のメンバーでフォローできるようになり、全体の仕事の流れがスムーズになった」という声も聞かれます。
属人化が解消されることで、無駄な待ち時間や手戻りが減り、結果として組織全体の生産性向上に寄与するのです。
サービス品質の安定
属人化が解消されると、担当者のスキルや経験に依存することなく、常に一定水準の品質を保ったサービスや製品を提供できるようになります。
マニュアルに基づいた標準的な手順で業務が行われるため、成果物の品質が安定し、顧客からの信頼性が向上します。
品質のばらつきが原因で発生していたクレームや問い合わせも減少し、対応にかかっていたコストや時間を削減できるでしょう。
安定した品質は、企業のブランドイメージ向上にも大きく貢献します。
従業員の負荷軽減と育成
特定の従業員に業務が集中する状況が改善され、業務負荷がチーム全体で平準化されます。
これにより、過度な残業が減少し、従業員は心理的なプレッシャーからも解放されるでしょう。
有給休暇を取得しやすくなるなど、ワークライフバランスの改善にもつながります。
また、業務の標準化やジョブローテーションを通じて、従業員は新しいスキルを習得する機会を得られます。
組織全体で人材を育成する土壌が育まれ、個々のキャリア形成にも良い影響を与えるのです。
組織の継続性向上
業務のノウハウや知識が、個人ではなく組織に蓄積されるようになります。
そのため、急な退職者や休職者が出た場合でも、事業への影響を最小限に食い止めることが可能です。
ナレッジが共有されているため、後任者への引き継ぎもスムーズに進みます。
このように、人材の流動性に左右されない強固な組織基盤を構築できることは、企業の持続的な成長にとって非常に重要です。
変化の激しい時代においても、安定して事業を継続していくためのレジリエンス(回復力)が高まります。
属人化の解消に関してよくある質問
属人化の解消に取り組む上で、多くの方が抱く疑問にお答えします。
具体的なアクションを起こす前の不安や悩みをここで解消しておきましょう。
「属人化の解消」の言い換えは?
「属人化の解消」と同じ意味を持つ表現は、「業務標準化」や「脱属人化」などです。
いずれも特定の人に依存せず誰でも業務を行える状態にすることを指します。
実際、属人化の対義語として「標準化」が挙げられ、「脱属人化」という言い方も広く使われます。
いずれの表現も属人化による弊害を取り除き、仕事の進め方を組織全体で共有・統一するというニュアンスを持っているのです。
属人化と標準化の違いは?
属人化と標準化は対極にある概念です。
属人化が「業務知識や手順が特定の個人にしかわからない状態」であるのに対し、標準化は「誰もが同じルール・手順で業務を行える状態」を意味します。
言い換えると、属人化はブラックボックス化を招くのに対し、標準化は見える化・マニュアル化されたオープンな業務運営です。
例えば、属人化では担当者が変わると仕事の進め方が変わってしまいますが、標準化された業務はマニュアルに沿って誰が担当しても一定の品質で遂行できます。
このように属人化と標準化は正反対であり、標準化を推進することが属人化解消の根本対策となります。
どのくらいの期間で属人化を解消できる?
解消にかかる期間は、組織の規模、業務の複雑さ、属人化の度合いによって大きく異なります。
小規模なチームの特定の業務であれば数ヶ月で改善が見られることもありますが、全社的な取り組みとなる場合は数年単位の長期的なプロジェクトになることも珍しくありません。
大切なのは、期間の長短よりも、一度始めた改善活動を継続的に行い、少しずつでも着実に前進させていくことです。
小規模チームでも効果はある?
小規模チームでも効果は絶大です。
むしろ、メンバーが少ない小規模チームこそ、一人の不在が業務全体に与える影響が大きいため、属人化を解消するメリットは計り知れません。
人数が少ない分、情報共有やコミュニケーションが密に行いやすく、改善活動もスピーディーに進めやすいという利点もあります。
事業を安定させ、少数精鋭で高いパフォーマンスを発揮するためにも、早期の取り組みが推奨されます。
まず何から着手すべき?可視化と文書化の優先度は?
まず着手すべきは「業務の可視化」です。
現状を正しく把握しなければ、どこに問題があるのか、何を優先的に改善すべきか判断できません。
業務の全体像を可視化し、特にリスクが高い、あるいは影響範囲が広い属人化業務を特定した上で、その業務から優先的に文書化(マニュアル化)を進めるのが最も効率的で効果的な手順です。
闇雲に文書化を始めても、労力がかかる割に効果が薄い可能性があります。
ツール導入のベストタイミングは?
ツール導入のベストタイミングは、業務の可視化を終え、ある程度の標準化やマニュアル化の目処が立った段階です。
ツールはあくまで情報共有を促進するための「手段」であり、導入自体が目的ではありません。
共有すべき情報の内容や、運用ルールが固まっていない段階でツールを導入しても、結局使われずに形骸化してしまうリスクが高いです。
まずは土台となる業務プロセスを整えることが先決です。
属人化解消の重要性まとめ
属人化の解消は、現代の組織運営において避けて通れない重要課題です。
属人化を放置すれば、業務停滞・品質低下・ノウハウ消失・人材流出など多方面にリスクが及びます。
一方で、属人化にメスを入れて業務を標準化・共有化すれば、生産性向上や品質安定、従業員育成、組織の継続性強化といった大きなメリットが得られます。
解消に向けた取り組みは一朝一夕にはいきませんが、業務の棚卸しから始めて着実に標準化と共有を進めていけば、必ず組織体質は改善するでしょう。
属人化を解消し「誰もが安心して引き継げる仕事環境」を整えることは、これからの時代を生き抜く企業にとって欠かせない土台と言えます。
属人化から脱却した強い組織を目指し、今日からできる一歩を踏み出してみてください。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能












