意思決定プロセスとは?7つのステップと改善方法をわかりやすく解説
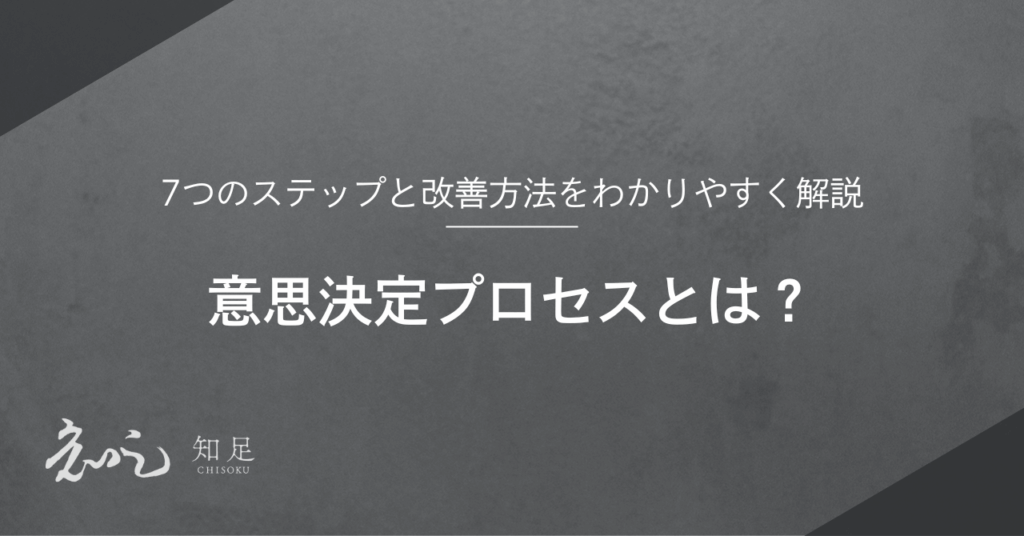
日々の業務で「どの選択肢が最善か分からない」「決断に時間がかかりすぎる」と悩んでいませんか。
重要な決断を迫られる場面で、自信を持って最適な選択ができないと、ビジネスチャンスを逃したり、チームの士気を下げたりする原因になりかねません。
もし、誰でも質の高い意思決定を迅速に行える体系的な方法があるとしたら、知りたくはありませんか。
本記事では、ビジネスの成果を最大化するための「意思決定プロセス」について、具体的な7つのステップや様々なモデル、改善のポイントを分かりやすく解説します。
最後まで読めば、あなたの意思決定の質とスピードは飛躍的に向上するでしょう。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能
>>組織体制とは?種類やメリット・デメリット・作り方などをわかりやすく解説
目次
意思決定プロセスとは?
意思決定プロセスとは、目標達成や課題解決のために、複数の選択肢から最善のものを選び、実行に移すまでの一連の手順のことです。
私たちは日常生活からビジネスまで、常に何らかの意思決定を行っています。
特にビジネスにおいては、企業の将来を左右する重要な意思決定が求められる場面が少なくありません。
勘や経験だけに頼った意思決定は、誤った判断を下すリスクを伴います。
そこで、論理的かつ体系的なプロセスを用いることで、より客観的で納得感のある、質の高い意思決定が可能になります。
このプロセスを理解し実践することは、個人の成長だけでなく、組織全体のパフォーマンス向上にも直結する重要なスキルです。
意思決定プロセスのステップ
質の高い意思決定を安定して行うためには、確立された手順を踏むことが重要です。
本パートを理解することで、意思決定を分解し、各段階で何をすべきかが明確になります。
目標/課題の明確化
意思決定プロセスの最初のステップは、達成すべき目標や解決すべき課題を具体的に定義することです。
何を目指しているのかが曖昧なままでは、その後のプロセス全体がぶれてしまいます。
目的が明確でなければ、どのような情報を集め、どのような基準で選択肢を評価すれば良いのか判断できません。
具体的には、「新製品の売上を前年比150%にする」「顧客満足度を10%向上させる」のように、SMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)を意識して設定することが有効です。
この段階で目的を明確に言語化し、関係者間で共有することで、意思決定の方向性が定まり、一貫性のある行動につながります。
情報収集と分析
次に、目標達成や課題解決に関連する情報を多角的に収集し、分析します。
正確な情報がなければ、適切な選択肢を立てたり、客観的な評価を行ったりすることが困難になるためです。
市場データ、競合の動向、自社のリソース、過去の事例など、信頼できる情報源から幅広く情報を集める必要があります。
集めた情報は、ただ眺めるだけでなく、整理・分析して意味のある洞察を引き出すことが重要です。
SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)やPEST分析(政治、経済、社会、技術)といったフレームワークを活用すると、情報を体系的に整理し、現状を客観的に把握するのに役立ちます。
この分析を通じて、意思決定の土台となる事実を固めます。
選択肢(代替案)の立案
情報分析を通じて現状を把握できたら、目標達成や課題解決のための具体的な選択肢(代替案)を複数立案します。
選択肢が一つしかない場合、それは最適な選択とは言えません。
ブレインストーミングなどを活用し、固定観念にとらわれず、できるだけ多くの可能性を洗い出すことが大切です。
例えば、売上向上という目標に対し、「新規広告の出稿」「既存顧客へのアップセル強化」「新商品の開発」など、さまざまな角度からアイデアを出します。
この段階では、実現可能性やリスクを過度に気にせず、自由な発想で選択肢を広げることが求められます。
多様な選択肢の中から比較検討することで、より創造的で効果的な解決策を見つけられる可能性が高まるでしょう。
各選択肢の評価/比較
立案した複数の選択肢を、あらかじめ設定した評価軸に基づいて客観的に評価し、比較検討します。
それぞれの選択肢が持つメリット・デメリットや、リスク、コスト、実現可能性などを多角的に評価することで、最も合理的な案を絞り込んでいきます。
評価軸を明確にすることが、このステップの質を左右するのです。
具体的には、「コスト」「期間」「期待される効果」「実行難易度」などの評価項目を設定し、それぞれに重み付けを行うと、より客観的な比較が可能になります。
例えば、各選択肢を5段階でスコアリングし、合計点で比較する方法があります。
感情や主観に流されず、論理的な基準で比較することが、後悔のない意思決定につながるのです。
意思決定の実行
評価と比較を経て、最終的にどの選択肢を実行するのかを決定します。
これが意思決定プロセスの核心部分です。これまでのステップで十分に検討を重ねていれば、自信を持って最善の選択ができるはずです。
ただし、ここで注意すべきは、決定を下すだけでなく、その決定に責任を持つ覚悟を決めることです。
決定した内容が組織全体にスムーズに受け入れられるよう、なぜその選択をしたのか、その背景や理由を関係者に丁寧に説明し、納得を得るプロセスも重要になります。
関係者の理解と協力を得ることで、次の実行フェーズが円滑に進みます。最終決定は、プロセス全体の責任者が明確に行い、曖昧さを残さないようにしましょう。
実行とフォローアップ
意思決定が完了したら、決定した内容を計画に落とし込み、実行に移します。
どんなに優れた意思決定も、実行されなければ意味がありません。
誰が、いつまでに、何を行うのかを具体的に定めた実行計画(アクションプラン)を作成し、関係者全員で共有します。
計画を実行するだけでなく、定期的に進捗を確認し、計画通りに進んでいるかを監視するフォローアップも不可欠です。
予期せぬ問題が発生した場合には、迅速に対応策を講じる必要があります。
進捗状況を可視化するためのツール(例:ガントチャート)を活用したり、定期的なミーティングを設定したりすることで、計画倒れを防ぎ、着実な実行を担保します。
振り返りと改善
最後のステップは、意思決定の結果を振り返り、評価することです。
実行した結果が当初の目標を達成できたか、期待通りの効果が得られたかを検証します。
この振り返りを通じて得られた学びや教訓は、次の意思決定プロセスに活かすための貴重な財産となります。
上手くいった点だけでなく、なぜ上手くいかなかったのか、プロセスのどの段階に問題があったのかを分析することが重要です。
具体的には、情報収集は十分だったか、選択肢の評価は適切だったか、実行計画に無理はなかったか、などを検証します。
このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回し続けることで、組織全体の意思決定能力が継続的に向上していくのです。
意思決定モデルと種類
意思決定には様々なアプローチがあり、状況に応じて適切なモデルを使い分けることが求められます。
本パートを理解することで、あなたが直面している課題に最適な意思決定の型を知ることができます。
合理的モデル
合理的モデルは、意思決定において最も古典的で理想とされるアプローチです。
問題に関する全ての情報を収集・分析し、論理的な思考に基づいて、効用が最大化される選択肢を合理的に選ぶことを目指します。
このモデルは、客観性と論理性を重視するため、特に重要かつ複雑な意思決定に適しています。
具体的には、企業のM&Aや大規模な設備投資など、失敗が許されない場面で用いられることが多いです。
ただし、全ての情報を完璧に収集することは現実的に不可能であり、時間やコストもかかるという側面もあります。
そのため、限られた情報の中で最善を目指す「限定合理性モデル」という考え方も存在します。
直感的モデル
直感的モデルは、過去の経験や知識、無意識のパターン認識に基づいて、直感的に判断を下すアプローチです。
論理的な分析を経ずに、「これだ」という感覚でスピーディーに結論を導き出します。
このモデルは、時間的な制約がある場合や、過去に類似の経験が豊富な専門家が判断を下す場合に特に有効です。
例えば、経験豊富な医師が患者の症状を見て瞬時に診断を下したり、熟練のトレーダーが市場の雰囲気から売買を判断したりするケースがこれにあたります。
ただし、個人の経験に大きく依存するため、客観的な説明が難しく、未知の状況や経験の浅い人には適していません。
また、後述する認知バイアスの影響を受けやすいというリスクもはらんでいます。
創造的モデル
創造的モデルとは、既存の枠組みにとらわれず、全く新しい視点から斬新な選択肢を生み出し、意思決定を行うアプローチです。
従来のやり方では解決できないような困難な課題や、イノベーションが求められる場面で活用されます。
このモデルでは、まず課題を深く理解し、情報をインプットする「準備期間」があります。
その後、一旦課題から離れて無意識下でアイデアが熟成される「孵化期間」を経て、突然ひらめきが訪れる「ひらめき(インスピレーション)」の段階へと進むのです。
最後に、そのアイデアが本当に有効かを検証します。
このプロセスは、デザイン思考やアート思考とも親和性が高く、新しい製品やサービスの開発、組織の変革といった場面で大きな力を発揮します。
その他のモデル
合理的、直感的、創造的モデルの他にも、状況に応じてさまざまな意思決定モデルが提唱されています。
| モデル名 | 概要 |
|---|---|
| 満足化モデル | 「最適」な解ではなく、ある程度「満足」できる水準の解が見つかった時点で決定するモデル。時間や情報が限られている場合に現実的なアプローチです。 |
| 政治的モデル | 組織内の複数の利害関係者(ステークホルダー)との交渉や調整を通じて、合意形成を図りながら意思決定を行うモデル。 |
| ごみ箱モデル | 組織内の「問題」「解決策」「選択機会」「参加者」が偶然結びつくことで意思決定がなされると考えるモデル。混沌とした状況での意思決定を説明します。 |
これらのモデルは単独で使われるだけでなく、状況に応じて組み合わせて活用されることもあります。
どのモデルが最適かを理解し、柔軟に使い分けることが、質の高い意思決定につながります。
個人と組織の意思決定プロセスの違い
意思決定は、個人が行う場合と組織として行う場合で、そのプロセスや特性が大きく異なります。
一人の判断で完結する個人の意思決定は迅速ですが、多くの人が関わる組織の意思決定は複雑なプロセスをたどります。
両者の違いを理解することは、それぞれの状況で適切な判断を下すために重要です。
以下に、個人と組織の意思決定プロセスの主な違いを表でまとめます。
| 比較項目 | 個人の意思決定 | 組織の意思決定 |
|---|---|---|
| スピード | 速い | 遅い傾向がある |
| 関与者 | 自分自身 | 複数の利害関係者(ステークホルダー) |
| 基準 | 個人の価値観や目標 | 組織の目標、方針、文化 |
| 情報源 | 個人の知識や経験に限定されがち | 多様な部署や専門家からの情報を活用可能 |
| 責任の所在 | 明確(自分自身) | 分散・曖昧になりがち |
| 複雑性 | 比較的シンプル | 関係者の調整など複雑性が高い |
個人の意思決定は、自分の価値観に基づいて素早く行える利点があります。
しかし、その反面、自分の知識や経験の範囲に限定され、認知バイアスの影響を受けやすいという欠点も持ち合わせています。
一方で、組織の意思決定は、多くのメンバーが関わるため時間がかかり、意見の対立も起こりがちです。
しかし、多様な視点や専門知識を結集させることで、一人では考えつかないような質の高い決定を下せる可能性があります。
また、複数の目でチェックすることで、個人的な思い込みや偏りを是正する効果も期待できます。
意思決定プロセスを改善するポイント
より良い意思決定を継続的に行うためには、プロセスそのものを改善していく意識が不可欠です。
ここでは、意思決定の質を高めるための具体的なポイントをいくつか紹介します。
- 目的と判断基準を事前に共有する
関係者全員が「何のために決めるのか」「何を基準に選ぶのか」という共通認識を持つことが、議論のブレを防ぎ、スムーズな合意形成につながります。 - データに基づいた議論を徹底する
「なんとなく」や「経験上」といった主観的な意見だけでなく、客観的なデータや事実を根拠に議論を進める文化を醸成することが重要です。これにより、感情的な対立を避け、より合理的な結論にたどり着きやすくなります。 - 多様な意見を意図的に取り入れる
同質性の高いグループでは、反対意見が出にくくなる「グループシンク」に陥りがちです。あえて異なる背景を持つメンバーを加えたり、「悪魔の代弁者」として意図的に批判的な視点を提示する役割を設けたりすることで、議論の多角性を担保します。 - 意思決定のフレームワークを活用する
問題の種類に応じて、SWOT分析、プロコンリスト(賛否両論)、ディシジョンツリーといった思考を整理するためのフレームワークを活用することで、思考の漏れや偏りを防ぎ、効率的に検討を進められます。 - 時間を意識した進行を心がける
情報収集や議論に時間をかけすぎると、かえって判断が鈍り、機会を逃してしまうことがあります。「分析麻痺」に陥らないよう、各ステップに適切な期限を設け、スピーディな進行を意識することが大切です。
意思決定のプロセスでよくある失敗
意思決定には落とし穴も多く存在します。
ここでは代表的な失敗とその対策をまとめます。
- 情報不足や情報過多:必要なデータを集めきれず判断が主観に偏る一方、情報を集めすぎても分析できず時間だけが過ぎます。目的に沿って情報源を選び、期限を設けて収集を打ち切ることが対策になります。
- 先入観や固定観念:過去の成功体験や組織文化が強すぎると、新しいアイデアを否定しがちです。反対意見を歓迎し、多様な視点を取り入れる風土づくりが重要です。
- グループ思考:仲間内で批判を避ける傾向が強まると、誤った方向に進みやすくなります。『Making Decisions』では、グループ思考を防ぐために悪魔の代弁者を配置し、外部の専門家を招くことなどが推奨されています。
- 責任の所在が曖昧:組織では決定に関わる人が多いため、誰が責任を負うのか不明確になりがちです。プロセスの最初に役割を決め、実行後も記録を残すことが欠かせません。
- 感情に流される:怒りや興奮、焦りの中で決めると判断が歪みやすいです。一晩置いて考える、第三者の意見を聞くなど、冷静になる時間を確保しましょう。
意思決定プロセスに関してよくある質問
意思決定プロセスについて、多くの方が抱く疑問にお答えします。
意思決定プロセスは何ステップが正解?5と7の違いは?
意思決定プロセスのステップ数に唯一の正解はありません。
一般的に5ステップまたは7ステップで解説されることが多いですが、本質的な内容は同じです。
7ステップモデルは、5ステップモデルをより細分化したものと捉えることができます。
具体的には、「実行」を「意思決定の実行」と「実行とフォローアップ」に分け、「振り返り」を独立したステップとして強調している点が特徴です。
重要なのはステップの数ではなく、各段階で何をすべきかを理解し、実践することです。
評価軸と重み付けはどう決める?
評価軸は、意思決定の「目標/課題の明確化」のステップで定義した内容に基づいて設定します。
具体的には、「コスト」「スケジュール」「品質」「リスク」などが一般的な評価軸です。
重み付けは、それらの評価軸の中で何を最も重視するかによって決定します。
例えば、スピードを最優先するプロジェクトであれば「スケジュール」の重みを高く設定します。
この評価軸と重み付けは、関係者全員で合意形成を図りながら決定することが、後のプロセスを円滑に進める上で重要です。
チームで合意形成を早く進めるコツは?
合意形成を円滑に進めるには、事前に目的や評価基準を共有し、各メンバーが意見を出しやすい環境を整えることが重要です。
よくある認知バイアスと対策は?
意思決定にはさまざまなバイアスが影響します。
代表的なものに、情報の一部だけを重視してしまう「アンカリング」、自分に有利な情報ばかり集める「確証バイアス」、既に費やしたコストに引きずられる「サンクコスト効果」などがあります。
対策としては、複数の情報源を参照すること、反対意見やデータを積極的に探すこと、感情に左右されないよう時間を置いてから決めることなどが有効です。
また、悪魔の代弁者を任命して意図的に反論させる方法もグループ思考を防ぐのに役立ちます。
意思決定プロセスのまとめ
意思決定プロセスとは、目標達成や課題解決のために、複数の選択肢から最善のものを選び実行するまでの一連の手順です。
このプロセスは主に「目標の明確化」「情報収集と分析」「選択肢の立案」「選択肢の評価と比較」「意思決定の実行」「実行とフォローアップ」「振り返りと改善」という7つのステップで構成されます。
意思決定には、論理を重視する「合理的モデル」や経験に基づく「直感的モデル」、新しい発想を生む「創造的モデル」など、様々なアプローチが存在します。
状況に応じて適切なモデルを使い分けることが重要です。
プロセスを改善するためには、判断基準の明確化、多様な視点の導入、データと直感のバランス、責任者の明確化、そして失敗から学ぶ文化の醸成が鍵となります。
また、情報収集の過不足や認知バイアス、同調圧力といったよくある失敗を理解し、対策を講じることで、意思決定の質はさらに向上します。
本記事で解説した内容を実践し、ビジネスにおける成果を最大化させましょう。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能












