CEO・COO・CFOの組織図と役割を徹底解説!図解でわかる企業構造
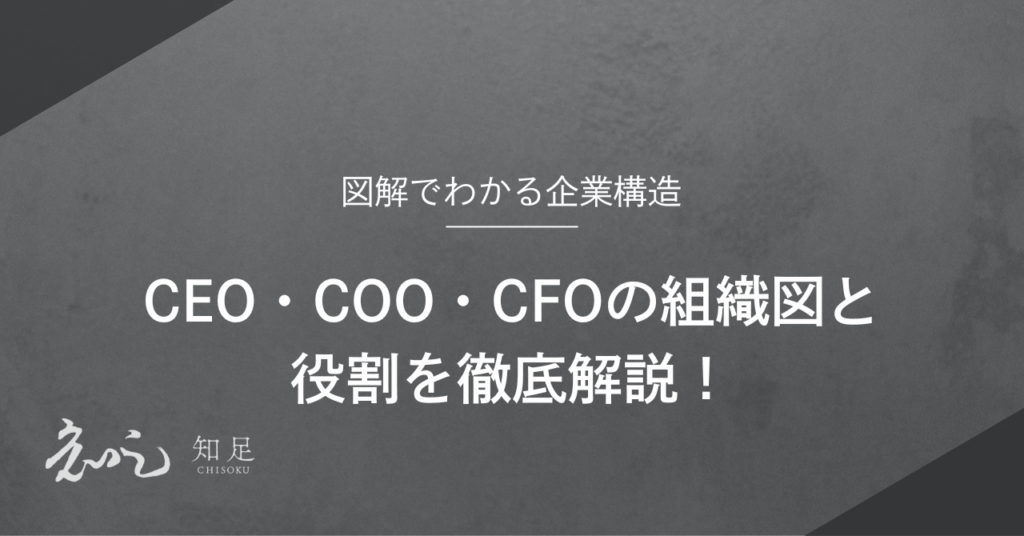
CEOやCOO、CFOといった名前はどこかで聞いたことはあっても「具体的にどんな業務を担っているのか」「自社の規模に合わせるにはどうすればいいのか」と迷う人も多いでしょう。
経営トップのポジションを正しく理解しないと、役割分担のバランスが崩れて事業運営に影響が及ぶことがあります。
本記事では組織図のイメージを示しながら、CEO・COO・CFOの特性や必要性をわかりやすく解説します。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能
>>CXOとは?意味や役職一覧、役割を徹底解説【メリット・違いも網羅】
目次
CEO・COO・CFOの組織図とは
CEO・COO・CFOの三役は、会社の方向性を示す経営戦略や組織管理、財務の舵取りを担うトップ層です。
大企業やスタートアップなど組織の規模はさまざまだが、企業が成長し続けるためには、経営を指揮する役職を明確にして役割を分担する必要があります。
組織図を示すとき、CEOを中心にCOOやCFO、その他の執行役員・取締役がそれぞれ専門性を発揮しながら連携する構造をイメージすると理解しやすいです。
- 社内外の情報を取りまとめ、経営の全体像をリードするCEO
- 現場を統括し、戦略を実務に落とし込むCOO
- 財務計画や資金繰りを管理し、投資家への説明責任を果たすCFO
このように、機能ごとにトップポジションを配置することで、意思決定のスピードが速まり、業務のクオリティ向上が見込まれます。
事業が大きくなるほど部門間の調整が複雑化するため、それぞれの立場で経営を支える三役は欠かせない存在といえるでしょう。
三役の役割を正しく理解し、自社の組織にどう落とし込むかは企業ごとに最適解が異なります。
もし自社の体制づくりや経営レベルの相談が必要なら、知足の個別相談で専門家に壁打ちしてみると、次の一手が見えてきます。
\事業戦略設計に役立つフレームワーク多数!/
>>知足の詳細を見てみる
CEOとは?
CEOに焦点を当てると、最高経営責任者が何を決定し、どのようなリーダーシップを発揮するのかが見えてきます。
次の見出しでは、CEOの本来の役割と組織内での立ち位置を具体的に探っていきましょう。
CEOの役割
CEOとは最高経営責任者で、会社全体の舵取りを行います。
事業の戦略から企業のビジョンやミッションを決定し、組織全体に浸透させる仕事が中心です。
一般的に意思決定の最終権限を持っており、企業の方向性を示すだけでなく、その実行性を高めるためのリソース配分も管理します。
社内外に対して「この企業はどこに向かおうとしているのか」を明確に示すのが役割です。
具体例として、M&Aや海外進出など、重大な意思決定の際はCEOが最終判断を下すケースが多いです。
意思決定のスピードや判断の基準が経営の成否を左右すると考えられるため、CEOが日頃から市場情報や社内データをチェックし、信頼できる経営陣とコミュニケーションを取りながら考察を重ねる姿勢が重要になります。
多忙なスケジュールの合間を縫い、現場感覚をつかむ行動を重視するCEOは、組織の成長や従業員のモチベーション向上に寄与しやすいです。
全社的な視点を保ちながら、必要に応じて実務レベルの判断にも関与することで、ブレのないリーダーシップを発揮します。
企業組織内でのCEOのポジション
企業組織のトップに位置づけられ、ほかの役員や取締役を統括します。
株主や取締役会から信任を受け、組織全体の運営をコントロールする立場にあるため責任も大きいです。
事業方針に加え、人事や財務戦略などにも最終的にコミットするケースが多く、現代ではグローバル展開を念頭に置いたブランドイメージの確立もCEOの大切な役割となっています。
一方で、CEO一人で全業務を取り仕切るのは非現実的です。
共同創業者や他の執行役員がいる場合、トップチームで手分けしながら企業経営を進める方法が一般的になります。
CEOが大局観を示しつつ、専門的な領域はCOOやCFO、CTOなど各分野の責任者に委ねることで、組織として素早い意思決定と実行がしやすい体制が整います。
COOとは?
会社運営の要となるCOOは、現場に密着した視点で事業を動かす存在です。
次の見出しでは、COOが実際に担当する業務内容やCEOとの関係性を深堀りします。
COOの役割
COOとは最高執行責任者で、CEOが定めた方針を具体的な行動計画に落とし込む役割を担います。
経営戦略を現場レベルで実行するリーダーであり、オペレーション面の最終責任者です。
社員や部門をまとめ、スケジュール調整やリソースの割り振りなど管理業務を行います。
経営における長期ビジョンを実現するには細かいタスクの組み立てが欠かせないため、COOは組織内で特に実務に近いポジションとして重視されます。
新規事業の立ち上げや組織改編などは時間と人材のコントロールを要求するでしょう。
ここで手腕を発揮するのがCOOです。
リーダーシップを発揮して現場との信頼関係を築き、売上目標の達成や品質管理などを軌道に乗せるために調整役となります。
CEOが大枠の方向性を描くなら、COOは具体的な道筋を引く存在に近いです。
事業の規模が大きくなるほど、COOの重要性が増していきます。
CEOとの違いと協業のバランス
CEOは経営全体の舵取り役、COOはその方針を事業運営に落とし込む実行役という構図が典型的です。
CEOが財務面やブランド戦略、対外的なプレゼンスを高めるための活動に時間を割くことが多い一方、COOは社内オペレーションを安定させ、生産性向上を目指します。
同じトップ層でもカバーすべき領域が異なるので、明確な役割分担が定まっていると組織運営がスムーズになりやすいです。
CEOとCOOがうまく連携していると、経営戦略と現場の動きが乖離しにくいです。
例えば、新製品を発売する際、CEOが打ち出したビジョンをCOOが具体的なプロジェクト計画に組み立てて、社内リソースを集めます。
社内の混乱を抑えながらスピーディーに実行するには、両者の強固なコミュニケーションが欠かせません。
経営トップ二人三脚の体制を築くことで、CEOが見据える未来に向けた戦略を確実に成果へと導きやすくなります。
CFOとは?
CFOは資金調達や財務戦略に深く関わる立場であり、企業の成長スピードに影響を与えます。
次の見出しでは具体的な任務と、投資家やステークホルダーに対する情報発信について解説します。
CFOの役割
CFOとは最高財務責任者であり、資金管理・資金調達・リスクマネジメントなどを統括します。
事業規模や業種によって着目ポイントは異なるが、共通するのは「会社のお金の流れをどう設計するか」を考えることです。
研究開発やマーケティングなど成長のために必要な投資を見極める一方で、収益性やキャッシュフローを維持できるかを見通します。
数字を扱うだけではなく、経営目標や戦略を踏まえたうえで資金配分を最適化する仕事が中心。
企業によっては管理部門全体の責任者をCFOが兼任するケースもあり、その場合は経理、人事、総務部門などの統括も担当することがあります。
財務の視点からリスクを評価し、銀行や投資家との交渉、必要に応じて新株発行や社債発行なども検討します。
組織が安定して回るためには、実務面だけではなく経営陣の一員として根幹にかかわる判断を行う立場でもあるのです。
資金調達やIRとの関係
CFOは資金調達やIR(Investor Relations)を通じて、社外ステークホルダーに対し企業の経営状況を説明します。
株主や投資家に正しい情報を提供することで信頼を得ると同時に、市場から必要な資金を集めやすくするのが主な役割です。
特に、上場企業では四半期ごとの決算説明会やプレスリリースなどを通じて、CFOの発言が株価や市場のイメージに大きく影響します。
経済産業省の「コーポレートガバナンス・コード」にも、投資家への説明責任を果たすことが企業価値向上に資すると明記されている。
このように、CFOは「数字の管理」だけでなく、企業の顔として対外的なコミュニケーションを担う可能性が高いです。
財務情報を軸に経営判断を促すため、CEOやCOOと協議して長期的な視点で企業価値を高める施策を考えるのが求められます。
CEO・COO・CFOの違いを比較
三役の役割は企業の成長ステージや組織体制によって微妙に変わります。
次の見出しで縦型・マトリクス型組織やスタートアップなどの形態にあわせ、彼らの職務分担を具体的に整理していきましょう。
縦型とマトリクス型の組織図
企業の組織図には大きく分けて縦型とマトリクス型があります。
縦型は事業部や部署ごとに階層が明確に分かれ、指揮系統がはっきりしているのが特徴です。
CEOがトップに位置し、その下にCOO、CFOなどが縦割りで配置される形が典型的。
意思決定プロセスがシンプルになる反面、部門横断のプロジェクトを進めるには連携が遅れがちになる可能性があります。
マトリクス型は特定のプロジェクトチームに複数の上司やステークホルダーが関わる構造になり、横断的な意思決定を素早く行いやすいのが利点です。
その一方で、CEOをはじめ各役職の責任範囲が曖昧になりやすい欠点があります。
COOが複数の事業を統括しながら人員調整を行い、CFOが横断的に資金配分を管理するなど、密なコミュニケーションが求められます。
どちらの組織形態においてもCEO・COO・CFOの位置づけは明確にしておき、全体のバランスが崩れないようにするのが重要です。
スタートアップ・中小企業での役割の分かれ方
スタートアップや中小企業では、CEOがCOOやCFOの業務を兼任するケースが少なくないです。
人的リソースや資金が限られるため、経営トップが複数の分野を同時に見ることになるからです。
その場合、優秀なマネージャーやアドバイザーを採用して部分的に業務を委託することが現実的な方法になります。
スタートアップはスピードが勝負なので、CEO自らが事業推進も担うことが珍しくない。
CFO不在のまま、CEOやCOOが資金調達に走る姿も見られます。
この段階では、役割を兼務しながらも専門家の外部協力を得てバランスを保つのがポイントです。
ある程度規模が拡大してきた段階で、それぞれの専門役職を設けると効率的でしょう。
日系企業と外資系企業の組織設計の違い
日系企業では社長・専務・常務といった呼称が使われる伝統が根強いです。
最近は、グローバル化に合わせてCEOやCOO、CFOの肩書きを採用する企業が増えているが、日本独自の取締役会制度や意思決定プロセスが並行して存在するケースもあります。
取締役会が経営の最終判断をする一方、CEOとしての役割を担う人物が株主総会や社外ステークホルダーと対話を主導する場合があります。
外資系企業はCEOの権限が明確で、COOやCFOも独立したポジションとして大きな裁量を与えられている傾向が強いです。
各役職の役割と責任がドキュメント化され、役職に就く本人も専門性を最大限に発揮しやすい環境が整えられています。
日系と外資系を単純比較できないものの、CEO・COO・CFOの三役を明確に使い分ける仕組みは外資系のほうが一般的に進んでいるといえるでしょう。
フェーズ別(創業期~成熟期)での配置の変化
創業期はCEOが事業のアイデアや顧客開拓を推進しつつ、資金調達も担う場合が多いです。
企業が成長して従業員が増えると、COOを置いて日常業務の最適化や新規事業の立ち上げを任せる段階に移行します。
財務面も複雑化してくるため、CFOを迎えてキャッシュフローやリスクマネジメントを強化するのが一般的です。
成熟期になると、さらにCTOやCMOなどの役職を加え、専門分野別にトップ人材を配置する企業が増えます。
CEOが大局を見渡し、COOが組織全体を動かし、CFOが財務戦略を策定しながら他の役員と協力する図式です。
会社のフェーズに合わせて役職を追加・見直しすることで、経営リソースを効率的に配分しやすくなります。
CEO・COO・CFOの組織図に関してよくある質問
トップポジションに関する疑問は多く、経営者やビジネスパーソンからよく質問が寄せられます。
ここではCEO・COO・CFOの違いから役割分担、呼称に関するポイントをまとめて解説します。
CEOとCOOの違いは?
CEOは企業全体のビジョンと方向性を示す最高経営責任者で、COOはビジョンを実際の運営に変える最高執行責任者という違いがあります。
CEOが中長期的な戦略や重要案件の最終決断をする一方で、COOは日々の業務計画や部門間調整などを監督します。
両者は経営方針を共有しながらも、それぞれの担当分野で力を発揮することでスピード感のある企業運営が可能になります。
経営陣の役割はどう分担されている?
CEO、COO、CFOの三役が中心ですが、企業によってはCTO(最高技術責任者)、CMO(最高マーケティング責任者)、CHRO(最高人事責任者)などを置く場合もあります。
CEOが全体を見渡す総責任者、COOが現場執行、CFOが財務管理の中核を担います。
ほかの役職も同様に専門領域を担当し、経営戦略の実現に向けて連携するイメージです。
明確な分業と連携体制が構築されると、経営の効率が上がります。
CEOと代表取締役の違いは?
日本の会社法に基づく役職が「代表取締役」で、グローバルで通用する名称が「CEO」ととらえられます。
代表取締役は会社の法人としての対外的な署名や契約などを行う法的権限を持ちます。
一方で、CEOは経営の最高責任者としての肩書きだが、必ずしも代表取締役と同一人物が担うとは限りません。
ただし、日本企業では実質的に同じ人物が兼任するケースが大半です。
COOとCFOはどっちが偉い?
立場の上下を一概に比較するのは難しく、それぞれが担う役割の性質が異なります。
COOはオペレーション全体を管轄し、CFOは企業の財政面を統括するポジションです。
企業の規模や文化によってはCOOがCEOに次ぐ序列とされることもあれば、CFOが資金戦略の要として大きな裁量を与えられる場合もあります。
役割の重要度が違うだけで、どちらが偉いとは断定できません。
CEO・COO・CFOの組織図まとめ
CEO・COO・CFOは企業経営を円滑に進めるための重要な三役で、CEOが大局観を示し、COOが現場運営を監督し、CFOが財務戦略を管理します。
それぞれ異なる専門性を発揮しながら組織を強化し、市場での競争力を高めます。
縦型・マトリクス型など組織構造の違いやスタートアップ~成熟期といったフェーズ変化に応じ、役職の配置を柔軟に検討することが大切です。
会社の規模が拡大するほど、三役の連携が経営成果を左右するカギになるでしょう。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能












