キャッシュフローの考え方は?見方や財務改善方法を初心者向けにわかりやすく解説
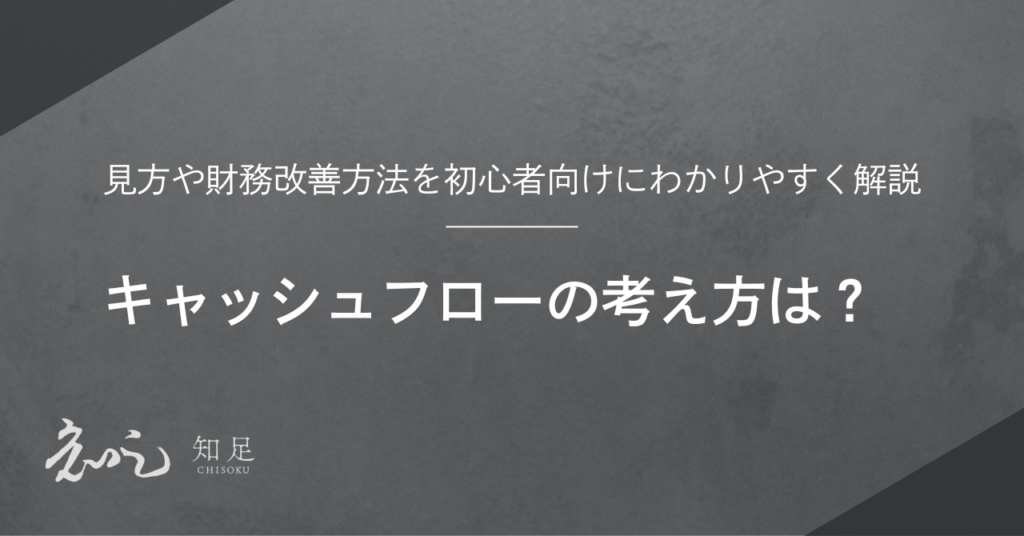
突然ですが、利益が出ているのに手元の資金が足りないという経験はありませんか?
その原因は「キャッシュフロー」に秘密があります。
売上や利益だけを追いかけていても、肝心の現金が不足すれば事業は回りません。
キャッシュフローを正しく理解し、改善する方法を身につけることで、資金繰りの不安を大きく減らすことが可能になります。
この記事では、キャッシュフローの基本や計算書の見方、さらには資金繰り改善の具体策までわかりやすく解説しています。
初心者の方でも無理なく読み進められるように、できる限り専門用語をかみ砕いて説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
>>財務戦略の立て方は?ポイントや資金調達、ROE改善まで徹底解説
目次
キャッシュフローとは?
キャッシュフローを正しく理解すれば、黒字倒産のリスクを大幅に減らせます。
ここではまずキャッシュフローの定義と、「利益」とは何が違うのかを明確に把握することが重要です。
次いで、キャッシュフロー計算書を読み解くうえで欠かせない3区分の概要を押さえていきましょう。
キャッシュフローの定義と「利益」との違い
キャッシュフローとは、一定期間における現金や預金などの「お金の流れ」を示す概念です。
「利益」は売上と費用の差額ですが、必ずしも現金の増減を反映しているわけではありません。
例えば、売掛金をたくさん抱えている状態では、帳簿上の利益はある程度出ていても、実際の現金は手元になく資金ショートする可能性があります。
そのため、企業活動を継続するには「利益が出ているか」だけでなく「現金がきちんと回っているか」を合わせて把握することが不可欠です。
利益はあくまで会計上の概念であり、キャッシュフローこそが事業を続けられるかどうかを左右する現実的な指標になります。
キャッシュフロー計算書の3区分
キャッシュフロー計算書は、以下の3つの区分から構成されます。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフロー
この3区分を正しく理解することで、自社が「事業活動でどれだけお金を稼ぎ、どこに投資をして、どのように資金を調達しているか」がひと目でわかります。
実際の経営判断の場面では、どの区分でプラスやマイナスが生じているかを確認することで、資金繰りの現状と改善すべきポイントが明確になるでしょう。
キャッシュフローの考え方で押さえる3つの視点
ここではキャッシュフロー計算書の3区分を踏まえつつ、それぞれの視点で何に注目すれば改善につながるのかを解説します。
どの区分も大切ですが、それぞれを俯瞰することで初めて事業全体の資金の流れを読み解けるようになります。
営業キャッシュフローのチェックポイント
営業キャッシュフローは「本業によって得られるお金の流れ」を示し、最も重要とされる部分です。
売掛金や買掛金の支払いタイミング、在庫の増減など、日々の事業活動で発生する現金の動きを正確に把握することがポイントです。
例えば、売上が好調でも、売掛金の回収が大幅に遅れていれば、営業キャッシュフローはマイナスとなり資金不足を引き起こしかねません。
まずは月次でキャッシュの出入りを細かく追いかけ、入金サイクルや支払い期日を管理することが重要です。
そうすることで、安定したキャッシュを保ちながら、追加の投資や事業拡大を検討できるようになります。
投資キャッシュフローの読み解き方
投資キャッシュフローは、設備投資や研究開発などに充てられる資金の流れを示します。
マイナスとなるのが一般的ですが、これは将来の事業拡大や効率化のための支出なので、一概に悪いとはいえません。
しかし、設備投資を大きくしすぎると、短期的なキャッシュ不足を招くリスクがあります。
例えば、生産ラインの大幅な拡張を急ぎすぎて、資金繰りが苦しくなるケースも少なくありません。
そのため、営業キャッシュフローの余力や、外部からの資金調達の計画と整合性が取れているかを常にチェックすることが大切です。
投資キャッシュフローをコントロールすることで、長期的な成長と短期的な安定を両立させることが可能になります。
財務キャッシュフローが示す資金調達の実態
財務キャッシュフローは、借入金や増資などにより調達した資金、およびその返済や配当などにより支出された資金の動きを示します。
ここがプラスであれば「金融機関からの借入れが増えた」「増資によって資金を調達した」などが推測されます。
一方で、返済が増えれば財務キャッシュフローはマイナスとなり、将来的に営業キャッシュフローで返済をカバーできるかどうかが課題になります。
財務キャッシュフローが極端にマイナスのままだと、手元資金を大きく減らしてしまい、事業継続が脅かされる可能性もあります。
したがって、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローのバランスを踏まえつつ、財務キャッシュフローをコントロールする視点が欠かせません。
キャッシュフローの考え方を活かした資金繰りのやり方
キャッシュフローに注目して資金繰りを行うことで、黒字倒産を避けられるだけでなく、必要なタイミングでの投資チャンスを逃さずに済むようになります。
ここでは具体的な予測方法や計算方法、さらに月次での資金管理ポイントを紹介し、キャッシュフローを活用した実践的な資金繰り手法を解説します。
キャッシュフロー予測を作る5ステップ
先々のキャッシュフローを予測することで、資金繰りの危機を未然に防ぐことができます。
以下の5ステップでシンプルに組み立ててみましょう。
- 売上予測を立てる
- 売掛金の回収時期を見積もる
- 仕入や人件費など支出項目を洗い出す
- 借入金の返済スケジュールを組み込む
- 投資に回す金額をシミュレーションする
この流れに沿って月ごとの予測を立てると、どのタイミングでキャッシュが不足しそうかが明確になります。
早めに不足の兆しが見えれば、金融機関との交渉やコスト削減など具体策を講じることができ、資金ショートを未然に防ぎやすくなるでしょう。
フリーキャッシュフローの計算方法
フリーキャッシュフロー(FCF)とは、企業が自由に使える現金のことで、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを差し引いて算出します。
数式で表すと以下のとおりです。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー – 投資キャッシュフロー
例えば、営業キャッシュフローが1,000万円、投資キャッシュフローが500万円のマイナスであれば、フリーキャッシュフローは500万円となります。
フリーキャッシュフローがプラスであれば、その資金を借入金返済や新規投資、配当に回すなど自由な選択が可能です。
一方、マイナスの場合は借入や増資などでカバーする必要がありますが、その状態が長引くほど会社の体力は低下していくため、早めの対策が必要です。
キャッシュバーンレートの求め方と目安
キャッシュバーンレートとは、一定期間内にどれくらいの現金が減っているかを示す指標です。
主にスタートアップ企業などが、資金が「いつ尽きるか」を把握するために用います。
計算式としては、直近数か月の平均キャッシュ減少額を算出し、それを基に「あと何か月で資金が底をつくか」を見積もります。
目安としては、少なくとも半年から1年程度は事業を継続できるキャッシュを確保しておきたいところです。
キャッシュバーンレートが高すぎると、黒字転換前に資金が枯渇するリスクが高まるため、支出項目を精査して適切にコントロールする必要があります。
月次資金繰り表を作成するポイント
月次資金繰り表は、キャッシュフロー管理の要ともいえるツールです。
毎月の現金収支を見える化し、来月以降の資金不足リスクにいち早く気づくために役立ちます。
作成時のポイントは以下のとおりです。
- 売上・入金予定を保守的に見積もる
- 給与や仕入など、固定的に発生する支出項目を明確にする
- 借入金返済と利息支払いのタイミングを把握する
- 設備投資や大口支出の予定は別枠で管理する
こうしたポイントを押さえ、実際のキャッシュの動きと月次資金繰り表を定期的に突き合わせることが重要です。
差異が大きい場合は、その原因を分析し迅速に修正を加えることで、将来的なリスクを回避しやすくなります。
キャッシュフローの誤った考え方で失敗しないコツ
キャッシュフローを理解していても、実際には思わぬ落とし穴にはまることがあります。
ここでは具体的な失敗を防ぐために、売上入金や支払いサイト、在庫、固定費などの重要な視点を押さえ、事業が滞らないための実践的な工夫を紹介します。
売上入金を早める具体策
売上入金を早めることは、営業キャッシュフローを改善する最も効果的な方法の一つです。
具体策としては、請求書の早期発行や支払いサイトの短縮交渉、クレジットカード決済やオンライン決済の導入が挙げられます。
請求書をデジタル化し、相手先に届くタイミングを早めるだけでも入金サイクルが改善するケースは多々あります。
また、取引先との関係性が良好であれば、支払いサイトの短縮を打診してみるのも一手です。
売上の現金化を迅速に行うことで、手元資金に余裕が生まれ、緊急時にも柔軟に対応しやすくなります。
支払サイトを見直すコツ
キャッシュフローを改善するには、売上の入金だけでなく自社の支払サイトも見直すことが肝心です。
仕入先との契約条件を整理し、必要に応じて「支払を月末締め翌月末払い」から「翌々月払い」へと変える交渉を行うなど、資金の流出タイミングをできる限り遅らせる工夫を検討しましょう。
ただし、支払サイトの延長によって取引先との関係が悪化する可能性もあるため、交渉の際は状況を丁寧に説明して理解を得ることが大切です。
無理に支払サイトを延ばすのではなく、双方にメリットがある条件を探ることで、長期的な信頼関係を維持しつつキャッシュフローを安定させることが可能です。
在庫回転率とキャッシュコンバージョンサイクル
在庫を抱えすぎると、キャッシュがモノの形で滞留し、資金繰りを圧迫します。
そこで注目されるのが、在庫回転率とキャッシュコンバージョンサイクル(CCC)です。
在庫回転率:一定期間内に在庫がどれほど回転したかを示す指標
キャッシュコンバージョンサイクル(CCC):原材料の仕入から売上入金までに要する期間
在庫回転率が低いほど、売れ残りや不良在庫のリスクが高まり、キャッシュが回収されるまでの期間が長くなります。
CCCを短縮するためには、発注量の最適化や需要予測の精度向上などが必要です。
例えば、販売実績データを基にした在庫管理システムを導入し、過剰在庫を回避するなどの工夫が効果的です。
こうした取り組みにより、現金化までの時間を短縮でき、安定した資金繰りを実現しやすくなります。
固定費の見直しと変動費管理
キャッシュフローを圧迫する大きな原因のひとつは固定費です。
家賃や人件費、リース料金などは売上が変動しても必ず支払わなければならず、資金繰りに大きく影響します。
定期的に契約内容を見直し、不要な固定費やより安いサービスへの切り替えを検討することが重要です。
また、変動費についても、原材料費や外注費などは需要に合わせて柔軟にコントロールできるよう、複数の仕入先を確保するなどリスク分散を図りましょう。
こうした経費管理の徹底により、キャッシュフローを安定させ、突発的な売上減少にも対応しやすくなります。
キャッシュフローに関してよくある質問
キャッシュフローの概念や計算方法を理解しても、具体的なケースで疑問が生じることは多々あります。
ここでは、代表的によく寄せられる疑問とその答えをまとめました。
自身の状況に照らし合わせながら、キャッシュフロー管理の精度を高めるきっかけにしてください。
キャッシュフローがマイナスでも黒字って本当?
結論、あり得ます。
帳簿上の利益では黒字でも、売掛金の回収が遅れたり在庫が増えたりして、実際に入ってくる現金が不足している場合、営業キャッシュフローがマイナスになってしまいます。
これがいわゆる「黒字倒産」の可能性を高める要因です。
したがって、PL(損益計算書)の数値だけを見て安心するのではなく、キャッシュフローを並行して確認し、入出金のタイミングを管理する必要があります。
フリーキャッシュフローと利益剰余金の違い
フリーキャッシュフロー(FCF)は、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを差し引いた「手元に自由に使えるお金」です。
一方、利益剰余金はあくまで会計上の利益累計であり、必ずしも現金が存在するわけではありません。
例えば、大きな借入を行って投資をした場合、利益としては将来に反映されるかもしれませんが、手元資金は出ていってしまっています。
こうした違いを理解することで、利益剰余金が大きくても実際の資金繰りが苦しいケースがある点に気づけるでしょう。
キャッシュフロー計算書の見方が難しい時は?
キャッシュフロー計算書はPLやBS(貸借対照表)と比べると、確かに取っつきにくい印象を受けるかもしれません。
難しく感じる場合は、まず「営業」「投資」「財務」の3つの区分に注目し、それぞれのプラス・マイナスが何を意味するのかを簡単な言葉で整理してみると理解しやすくなります。
さらに、経済産業省や中小企業庁などが公開している解説資料を活用するのもおすすめです。
公的機関の資料は図表も多く、要点がコンパクトにまとめられているため、独学で勉強する際には心強い味方となるでしょう。
個人事業主でもキャッシュフローを管理すべき?
結論から言えば、個人事業主であってもキャッシュフロー管理は非常に重要です。
事業規模が小さいほど、思わぬ支出が発生した場合に資金がショートしやすく、経営継続が難しくなるリスクがあります。
毎月の売上と支出を整理し、どれくらいキャッシュが残っているのかを常に把握しておくことは、安定的に事業を続けるうえで不可欠です。
銀行融資を受ける際にも、「いざというときに資金を返済できるか」という点を客観的に示すためにキャッシュフローの実態を提示することが求められます。
キャッシュフローの考え方を身につけ財務管理を徹底しよう
キャッシュフローは、企業や個人事業の経営において「今、手元にいくら現金があるのか」を明確に把握するための基礎となる指標です。
利益が出ていてもキャッシュが不足していれば黒字倒産のリスクは高まります。
キャッシュフロー計算書をはじめとする基本的な見方を理解し、予測や在庫管理、支払サイトの見直しなど実践的な施策を組み合わせることで、安定した資金繰りを維持しながら事業を成長させることが可能です。
まずは小さなステップから始めて、キャッシュフローを軸とした財務管理を徹底していきましょう。













