コンピテンシーモデルとは?意味/メリット/作り方/具体例を徹底解説
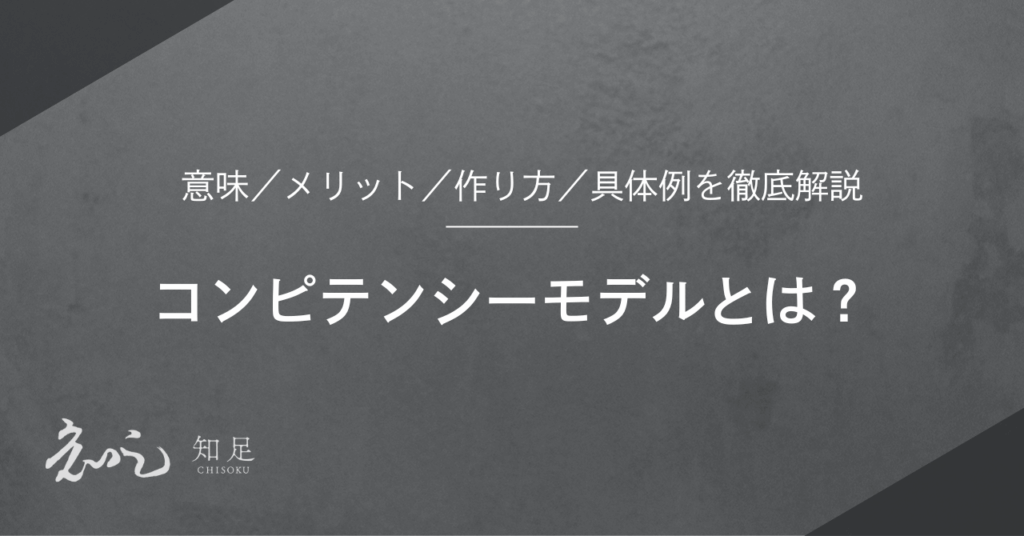
「人事評価の基準が曖昧で、社員の納得感が低い」「採用した人材が期待通りの活躍をしてくれない」こうした悩みを抱えていませんか。
多くの企業が、感覚的な評価や採用のミスマッチによって、優秀な人材の獲得や育成の機会を逃しています。
その問題を解決する具体的な手法が「コンピテンシーモデル」の導入です。
コンピテンシーモデルは、高い成果を出す社員の行動特性を基準にするため、客観的で公平な人事評価や戦略的な人材育成を実現します。
本記事を参考に、自社の人材マネジメントを一段階進化させましょう。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
>>社員がなぜ育たないのか?原因や対策、リスクを徹底解説
>>事業戦略のおすすめ本10選!初心者でも分かりやすいものから名著まで紹介
目次
コンピテンシーモデルとは何か
コンピテンシーモデルとは、社内で高い成果を上げる人材(ハイパフォーマー)に共通する行動特性を、評価基準として具体的にモデル化したものです。
個人の能力や知識そのものではなく、「成果に結びつく具体的な行動」に着目する点が大きな特徴です。
例えば、「コミュニケーション能力が高い」という曖昧な評価項目ではなく、「相手の意見を要約し、認識のズレがないか確認する」といった、誰が見ても判断できる行動レベルまで落とし込みます。
このように行動を基準にすることで、人事評価や採用、育成の客観性や納得感を高めることができます。
企業理念や事業戦略と連動させた独自のモデルを構築することで、組織全体のパフォーマンス向上を目指すための重要な土台となるのです。
コンピテンシーモデルの目的と重要性
コンピテンシーモデルの主な目的は、企業のビジョンや経営戦略を実現するために必要な人材像を具体化し、全社員と共有することです。
評価基準が明確になることで、社員は自身の目指すべき姿を具体的に理解し、日々の業務で何を意識すればよいかが分かります。
このモデルの重要性は、客観的で公平な人事制度の基盤となる点にあります。
評価者の主観に頼った評価は、社員の不満やモチベーション低下の原因になりかねません。
コンピテンシーモデルを導入すれば、誰もが納得できる明確な基準で評価を行えるため、社員のエンゲージメントを高める効果が期待できます。
企業の競争力を高める上で、不可欠な仕組みです。
コンピテンシーモデルの構成要素
コンピテンシーの概念は「氷山モデル」で例えられます。
目に見えるスキルや知識といった表面的な能力は氷山の一角に過ぎず、水面下には「動機」「価値観」「性格」などの見えない要素が存在し、これらが行動に大きく影響するとされています。
このように、成果に直結する行動を支える潜在的な要因まで含めてモデル化する点がコンピテンシーモデルの特徴です。
コンピテンシーモデルの主な構成要素には以下のようなものがあります。それぞれが相互に関連し、高い成果を生む人材像を形作ります。
- スキル(Skills)
職務遂行に必要な専門的・技術的な技能のことです。業務に直結する具体的な能力で、例えばプログラミング能力や高度な問題解決スキルなどが該当します。 - 知識(Knowledge)
業務や分野に関連する体系的な知識です。法務知識や業界特有の専門知識など、仕事を効果的に行うために必要な情報・理論を含みます。 - 行動(Behaviors)
職場で発揮される具体的な行動や態度のことです。リーダーシップやチームワーク、責任感など、組織の文化や職務基準に照らして求められる行動様式を指します。 - 能力(Abilities)
スキルや知識を統合し複雑な業務を遂行する総合力です。学習能力や論理的思考力、創造的な問題解決力などが含まれ、変化に適応して持続的に高成果を出すために重要な要素です。 - 動機・価値観(Motivation & Values)
内面的な動機付けや仕事に対する価値観です。自己成長意欲や職務への情熱、高い倫理観などが該当し、個人の行動を突き動かす原動力となります。 - 個人特性(Personal Attributes)
個人の性格や資質に関わる特性です。リーダーシップの素質、柔軟性、ストレス耐性など、仕事の進め方やパフォーマンスに影響を与える生来的・人格的要因を指します。
以上の要素を統合して、求められる人材像を具体化するのがコンピテンシーモデルです。
目に見えるスキルから内面的な動機づけまでを網羅することで、採用・評価・育成といった人事プロセスにおいて精度と効果を高める枠組みとなっています。
コンピテンシーモデルの作り方
コンピテンシーモデルを自社に導入するには、計画的にいくつかの段階を踏む必要があります。
ここではコンピテンシーモデルを構築する手順をステップごとに解説します。
自社の状況に合わせて進めることで、効果的で実践的なモデルを作成できるでしょう。
事前準備(目的設定・対象者選定)
まずは事前準備として、モデル構築の目的を明確化し、対象とする職種や職位を決定します。
コンピテンシーモデルを作る目的が曖昧だと、項目の選定や方向性がぶれてしまうため、ここをしっかり定めることが重要です。
例えば「評価の透明性向上」や「将来のリーダー育成」といった目的を設定し、経営方針・事業戦略に沿った人材要件を洗い出しましょう。
加えて、モデルを作成する範囲(どの部署・職種を対象にするか)も決めます。
まずは影響範囲の大きい管理職や主要部門から着手するなど、優先順位をつけると良いでしょう。
組織の目標とリンクしたニーズ分析を綿密に行い、「何のために・誰に対して」モデルを作るのかを明確にすることがこの段階のポイントです。
ハイパフォーマーの特定とインタビュー
次に、設定した対象者の中から、継続的に高い成果を上げているハイパフォーマーを複数名選定します。
売上などの定量的な成果だけでなく、周囲への貢献といった定性的な側面も考慮して選びましょう。
選定した社員にはインタビューを実施し、具体的な成功体験について深掘りします。
どのような状況で、何を考え、どう行動したのかを詳細にヒアリングすることが重要です。
行動特性の抽出と分類
インタビューで得られた情報を基に、ハイパフォーマーに共通する具体的な行動や思考のパターン(行動特性)を洗い出します。
例えば、「毎朝、業界ニュースをチェックしてチームに共有している」「クレーム対応の際は、まず顧客の感情に寄り添う言葉をかける」といった具体的なレベルで、できるだけ多く書き出していきましょう。
次に、抽出した行動特性を類似の内容でグループ分けし、分類(クラスタリング)していきます。
この作業を通じて、「顧客志向」「計画性」「問題解決能力」といったコンピテンシー項目が見えてきます。
既存のコンピテンシー・ディクショナリーを参考にしつつも、自社独自の言葉で定義していくことが、社員の理解を促進する上で重要です。
モデル化と評価項目設定
分類した行動特性を基に、コンピテンシーモデルとして体系化します。
各コンピテンシー項目について、具体的な定義を明文化し、行動レベルを段階的に設定します(例:レベル1〜5)。
| レベル | 行動の例(課題解決力) |
|---|---|
| レベル5 | 誰も予見しなかった課題を発見し、斬新な解決策で業界に影響を与える。 |
| レベル4 | 部署全体に関わる複雑な課題に対し、関係者を巻き込みながら解決に導く。 |
| レベル3 | 指示された範囲を超え、自発的に問題点を見つけ、改善策を提案し実行する。 |
| レベル2 | 指示された課題に対して、定められた手順通りに解決できる。 |
| レベル1 | 課題が発生すると、上司や先輩に報告し指示を待つ。 |
このようにレベル分けすることで、評価の客観性が増し、社員自身も次のステップを意識しやすくなります。
検証とフィードバック
作成したコンピテンシーモデルの草案が、現場の実態と乖離していないか、評価基準として機能するかを検証します。
対象部署の管理職や一般社員にモデル案を提示し、フィードバックを求めましょう。
「評価基準が分かりにくい」「この行動は現実的ではない」といった現場の意見を吸い上げることで、より実用性の高いモデルにブラッシュアップできます。
この検証プロセスを通じて、モデルの納得感を高めることができます。
また、関係者を巻き込むことで、本格導入に向けた協力体制を築くことにも繋がるのです。
導入後の運用と改善
完成したコンピテンシーモデルを、いよいよ人事評価や採用、研修などの制度に組み込み、運用を開始します。
導入前には、評価者となる管理職や全社員に対して、モデルの目的や内容、評価方法に関する説明会を実施し、十分な理解を得ることが不可欠です。
そして最も重要なのが、導入後の継続的な改善です。
事業環境の変化や企業の成長ステージに応じて、求められる人材像は変化します。
定期的にモデルの見直しを行い、現状にそぐわない項目があれば修正するなど、常に最適な状態を維持するためのPDCAサイクルを回していくことが、コンピテンシーモデルを形骸化させないためのポイントです。
コンピテンシーモデルを導入するメリット
コンピテンシーモデルを導入すると、企業・従業員双方に多くの利点がもたらされます。
ここではコンピテンシーモデル導入の主なメリットを紹介します。
評価や採用の質向上から人材育成の効率化まで、組織にもたらすポジティブな効果を確認しましょう。
人事評価の納得感向上
コンピテンシーモデルを評価基準として設定することで、人事評価の透明性と公平性が飛躍的に高まります。
評価項目が具体的な行動基準となるため、上司の主観によるばらつきが減り、被評価者も何を評価されているかを理解しやすくなります。
例えば従来は「あの上司は主観的だ」と不満が出ていたケースでも、コンピテンシーに基づく評価なら明確な物差しがあるので納得感が得られやすいでしょう。
評価基準が曖昧だと社員は不満を感じ離職につながる恐れもありますが、モデルを用いた公平な評価はモチベーション維持・離職防止にも寄与します。
このように、コンピテンシーモデルの導入は人事評価における信頼性を高め、従業員の納得感向上につながります。
採用や配置の精度向上
採用活動においてコンピテンシーモデルを活用することで、自社で活躍できる可能性の高い人材を見極めやすくなり、採用のミスマッチを大幅に減らすことができます。
面接では、モデルで定義された行動特性に基づいた質問をすることで、候補者の過去の経験から潜在的な能力や価値観を深く探ることが可能です。
また、人材配置においても、各ポジションで求められるコンピテンシーが明確になっていれば、社員一人ひとりの特性や強みを最大限に活かせる配置が実現します。
これにより、適材適所が促進され、組織全体の生産性向上に繋がります。
人材育成の効率化
社員一人ひとりが、自分に期待される役割や目指すべき姿を具体的に把握できるようになります。
自身の強みや弱みをコンピテンシーモデルと照らし合わせることで、取り組むべき能力開発の課題が明確になります。
企業側も、全社的に不足しているコンピテンシーを特定し、的を絞った研修プログラムを企画できるため、人材育成への投資対効果を高めることが可能です。
コンピテンシーモデル導入のデメリット
本パートを理解することで、モデル導入に伴う潜在的な課題を事前に認識できます。
時間的コストや運用面の難しさなど、成功のために乗り越えるべきハードルを確認しましょう。
作成/運用に時間とコストが掛かる
オリジナルのコンピテンシーモデルを作成するには、相応の時間と労力が必要です。
ハイパフォーマーへのインタビュー、行動特性の分析、モデル化、検証といった一連のプロセスには、数ヶ月単位の期間を要することも少なくありません。
また、これらの作業を担う人事部門の負担は大きく、外部コンサルタントに依頼する場合はコストが発生します。
導入後も、評価者研修や定期的なモデルの見直しなど、継続的な運用コストがかかることを念頭に置く必要があります。
評価者への教育が必要
精度の高いコンピテンシーモデルを作成しても、評価者である管理職がそれを正しく理解し、使いこなせなければ意味がありません。
モデルの各項目や行動レベルの定義を深く理解し、部下の行動を客観的に観察・評価するスキルが求められます。
そのため、モデル導入前には、評価者向けの十分なトレーニングが不可欠です。
この教育を怠ると、結局は評価者の主観による運用に戻ってしまい、制度が形骸化するリスクがあるため注意が必要です。
環境変化への対応
市場の動向や技術革新など、ビジネスを取り巻く環境は常に変化しています。
かつて成果につながった行動が、将来も同じように有効であるとは限りません。
そのため、コンピテンシーモデルは一度作成したら終わりではなく、事業戦略や組織の変化に合わせて定期的に見直し、アップデートしていく必要があります。
メンテナンスを怠ると、モデルが時代遅れになり、かえって組織の成長を妨げる要因になりかねません。
コンピテンシーモデルの具体例
コンピテンシーモデルは、企業の理念や職種、階層によって様々です。
ここでは、職種別にどのようなコンピテンシーがモデルとして設定されることが多いか、具体例を紹介します。
【営業職のコンピテンシーモデル例】
| コンピテンシー項目 | 行動レベルの例 |
|---|---|
| 目標達成志向 | 常に目標数字を意識し、達成に向けた具体的な行動計画を立て、粘り強く実行する。 |
| 顧客関係構築力 | 顧客の潜在的なニーズを引き出し、単なる御用聞きではなく、信頼されるパートナーとしての関係を築く。 |
| 情報収集・活用力 | 業界動向や競合情報を常に収集し、顧客への提案や自身の営業戦略に活かしている。 |
| 交渉力 | 自社の利益と顧客の満足のバランスを取りながら、WIN-WINとなる着地点を見出すことができる。 |
【管理職(マネージャー)のコンピテンシーモデル例】
| コンピテンシー項目 | 行動レベルの例 |
|---|---|
| ビジョン浸透力 | 会社のビジョンや目標を自身の言葉で部下に伝え、チーム全体のモチベーションを高めることができる。 |
| 部下育成力 | 部下一人ひとりの強みや課題を把握し、適切なフィードバックと権限移譲を通じて成長を支援する。 |
| 問題解決力 | チームで発生した問題に対し、原因を分析し、関係者を巻き込みながら解決策を導き出し実行する。 |
| 意思決定力 | 不確実な状況でも、情報を収集・分析し、チームや組織にとって最善の判断を迅速に行うことができる。 |
これらの例はあくまで一例です。重要なのは、自社のハイパフォーマーの行動特性を基に、独自のモデルを構築することです。
コンピテンシーモデルに関してよくある質問
コンピテンシーモデルについて、多くの方が抱く疑問にお答えします。
コンピテンシーとコンピテンシーモデルの違いは?
コンピテンシーは個々の行動特性で、コンピテンシーモデルはそれらを体系的にまとめたものです。
コンピテンシーが「成果を出す人の行動」という単体の要素を指すのに対し、コンピテンシーモデルは、複数のコンピテンシーを組み合わせて定義し、評価や育成に活用するための仕組み全体を指します。
いわば、コンピテンシーが「部品」で、モデルが「設計図」のような関係です。
ディクショナリーは必要?既存を流用してもいい?
独自作成が理想ですが、既存のディクショナリーの活用も有効です。
コンピテンシーディクショナリーとは、汎用的なコンピテンシー項目を一覧にした辞書のようなものです。
ゼロから作成する時間がない場合、これを参考にすると効率的です。ただし、最も重要なのは自社の理念や戦略との整合性です。
既存のものをそのまま使うのではなく、自社の状況に合わせてカスタマイズすることが成功の鍵となります。
評価や面接ではどう活用する?項目は何個が適切?
評価では行動のレベルを測り、面接では過去の行動を深掘りします。
項目数は5〜10個が一般的です。
人事評価では、モデルの行動指標を基準に、社員の日々の行動がどのレベルにあるかを判断します。
採用面接では、「困難な課題を解決した経験はありますか?」のように、コンピテンシーに関連する過去の行動を問う質問をします。
項目が多すぎると運用が複雑になるため、注意が必要です。
モデル作成にかかる期間は?
企業の規模や対象範囲によりますが、一般的に3ヶ月から1年程度です。
特定の部門のみを対象とする小規模なモデルであれば、比較的短期間で作成可能です。
一方で、全社的なモデルをゼロから構築する場合には、綿密な調査や多くの関係者との調整が必要になるため、1年以上の期間を要することもあります。
プロジェクトの目的と体制をしっかり固めてから着手することが重要です。
コンピテンシーモデルで人材マネジメントを進化させよう【まとめ】
コンピテンシーモデルは、高業績者の行動特性を基に理想の人材像を体系化したフレームワークです。
本記事ではその意味や重要性から作り方、メリット・デメリット、具体例まで総合的に解説しました。
コンピテンシーモデルを導入すれば、採用や評価の基準が明確になり、人材育成も戦略的に進められるようになります。
もちろん構築には時間と労力が必要ですが、モデルを軸に人材マネジメントを行うことで組織の生産性向上や公正な評価につながるでしょう。
自社に適したコンピテンシーモデルを作成し、運用・改善を重ねることで、人と組織の成長を加速させる人材マネジメントの進化をぜひ実現してください。













