中小企業のキャッシュフローとは?計算書の見方、作り方を解説
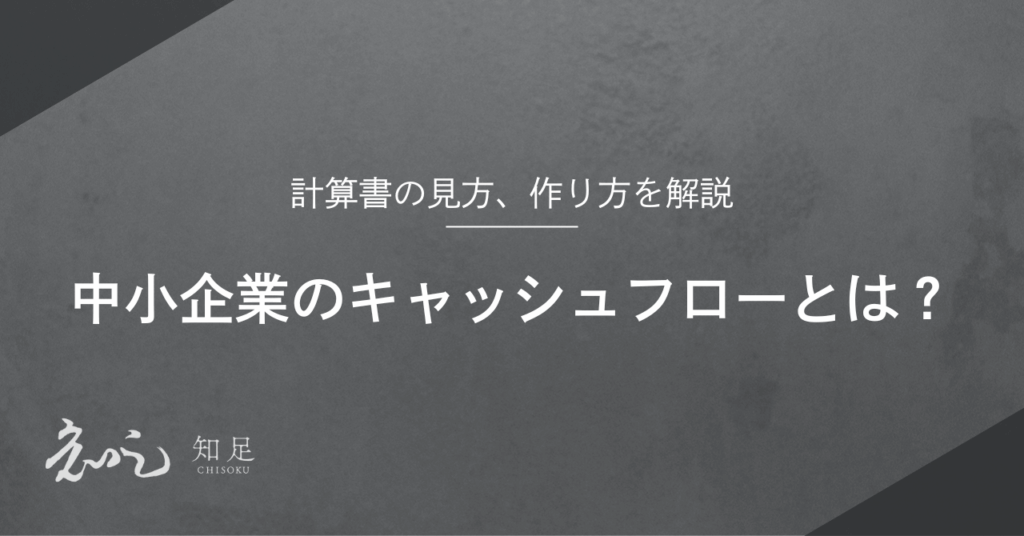
会社の利益は順調に伸びているはずなのに、なぜか手元の現金がいつもギリギリで、支払いに追われる日々が続いていませんか?
その原因は、利益と現金の動きのズレ、つまり「キャッシュフロー」の把握ができていないことにあるかもしれません。
このまま放置すれば、黒字なのに倒産という最悪の事態を招く可能性もあります。
本記事では、キャッシュフローの基本から、具体的な改善策、日々の運用体制までを網羅的に解説。
この記事を読めば、会社のお金の流れを正確に把握し、安定した経営基盤の実現に向けた具体的な一歩を踏み出せるようになります。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能
>>財務戦略の立て方は?ポイントや資金調達、ROE改善まで徹底解説
目次
中小企業のキャッシュフロー基礎
キャッシュフローとは、一言で言えば「会社のお金の流れ」そのものです。
具体的には、一定期間内にどれだけの現金が会社に入ってきて(キャッシュイン)、どれだけ出ていったか(キャッシュアウト)を示します。
たとえ損益計算書(PL)上で利益が出ていても、売掛金の回収が遅れたり、多額の設備投資をしたりすると、手元の現金は不足してしまいます。
この「利益」と「現金」の動きの差を明確に可視化するのがキャッシュフローの役割です。
中小企業にとってキャッシュフローの管理は、資金ショートを防ぎ、安定した経営を続けるための生命線と言えるでしょう。
日々の経営判断を正確に行うためにも、まずはこの基本をしっかりと押さえることが重要です。
中小企業のキャッシュフロー計算書の見方、作り方
キャッシュフロー計算書を理解し活用することで、自社の本当のお金の状態を把握し、将来の資金繰り予測に役立てることができます。
ここでは、計算書の具体的な作成手順と、3つの区分の読み解き方を解説します。
間接法の具体ステップ
中小企業では、損益計算書の情報を基に作成できる「間接法」が一般的です。
まず、損益計算書の税引前当期純利益からスタートします。
次に、実際のお金の動きとは異なる項目(減価償却費など)を足し戻したり、売上債権や棚卸資産、仕入債務の増減額を加減したりして調整します。
このステップを踏むことで、利益と現金のズレを明らかにしながら、営業活動によるキャッシュフローを算出できます。
このプロセスを理解することが、自社の資金繰りの実態を掴む第一歩となります。
間接法によるキャッシュフロー計算書の作成手順
| ステップ | 内容 | 摘要 |
|---|---|---|
| 1. スタート | 税引前当期純利益 | 損益計算書(PL)から転記します。 |
| 2. 加算項目 | 減価償却費、引当金の増加額など | 現金の支出を伴わない費用を加算します。 |
| 3. 減算項目 | 引当金の減少額など | 現金の収入を伴わない収益を減算します。 |
| 4. 資産・負債の増減調整 | 売上債権の増加(減算)、棚卸資産の増加(減算)、仕入債務の増加(加算)など | 営業活動に関わる資産・負債の増減を調整します。 |
| 5. 小計 | 営業活動によるキャッシュフロー | 上記を合計し、法人税等の支払額を差し引いて算出します。 |
営業CF・投資CF・財務CFの読み方
キャッシュフロー計算書は「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つの区分で構成されています。
これらのバランスを見ることで、会社の健全性を多角的に分析できます。
- 営業キャッシュフロー(営業CF): 本業の営業活動でどれだけ現金を稼いだかを示します。ここがプラスであることが健全な経営の絶対条件です。マイナスの場合は、売上不振や回収期間の長期化など、本業に問題がある可能性を示唆します。
- 投資キャッシュフロー(投資CF): 設備投資や有価証券の売買など、将来の成長に向けた投資活動による現金の動きです。通常、事業拡大期には設備投資でマイナスになります。プラスの場合は、資産を売却して現金を得ていることを意味します。
- 財務キャッシュフロー(財務CF): 借入や返済、増資など、資金調達と返済に関する現金の動きです。借入を行えばプラスに、返済を進めればマイナスになります。
これらの3つのキャッシュフローの組み合わせから、企業の現在のステージや財務状況を読み解くことが可能です。
例えば、営業CFがプラスで投資CFがマイナス、財務CFもマイナスという形は、本業で稼いだお金で投資を行い、借入金も返済している健全な状態と言えます。
中小企業のキャッシュフローセルフ診断チェックリスト
自社のキャッシュフロー管理に問題がないか、簡単なチェックリストで確認してみましょう。
当てはまる項目が多いほど、早急な対策が必要です。
- 損益計算書は毎月見ているが、キャッシュフロー計算書は作成していない
- 利益は出ているはずなのに、なぜかいつも資金繰りが厳しい
- 売掛金の回収期間を正確に把握していない
- 在庫がどれくらいあるか、すぐに答えられない
- どんぶり勘定で仕入れや経費の支払いをしている
- 複数の銀行口座にお金が散らばっており、会社の現預金残高を即答できない
- 資金調達を検討しているが、いくら必要で、いつまでに必要か明確でない
- 設備投資の判断を、投資回収期間を考慮せずに行っている
これらの項目は、キャッシュフロー悪化の兆候です。
まずは自社の状況を客観的に把握することから始めましょう。
中小企業のキャッシュフロー改善方法
キャッシュフローを改善するには、入ってくる現金を増やし(Cash-in)、出ていく現金を減らす(Cash-out)ことが基本です。
ここでは、具体的な改善策を多角的に解説します。
Cash-in:回収前倒し・前受金・価格改定
キャッシュインを増やすためには、売上を増やすだけでなく、現金を早く回収する工夫が必要です。
例えば、取引先に交渉し、売掛金の回収期間を短縮してもらう、契約時に一部を前受金として受け取る、といった方法が有効です。
また、提供する商品やサービスの価値を見直し、思い切って価格改定を行うことも、キャッシュフローに直接的なインパクトを与える強力な手段となります。
これらの施策は、手元資金を厚くし、資金繰りを安定させる効果があります。
Cash-out:支払期間交渉・在庫圧縮・固定費見直し
キャッシュアウトを減らすには、支出のタイミングを遅らせ、不要な支出をなくす視点が重要です。
仕入先との信頼関係を基に、買掛金の支払期間を延長してもらう交渉は有効な手段の一つです。
また、過剰な在庫は現金を寝かせているのと同じであり、販売予測の精度を上げて在庫を圧縮することが求められます。
さらに、家賃や人件費、通信費といった固定費を定期的に見直し、削減できる部分がないか精査することも、継続的なキャッシュフロー改善に繋がります。
運転資金とCCCを縮める打ち手
運転資金とは、事業を回していくために必要な手元資金のことです。
この運転資金を適切に管理する指標としてCCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)があります。
CCCは、商品を仕入れてから販売し、その代金を回収するまでにかかる日数のことです。
この日数が短いほど、資金効率が良い経営と言えます。
CCCを短縮するには「売掛金の回収を早める」「在庫の保有期間を短くする」「買掛金の支払いを遅らせる」という3つの要素を同時に改善していく必要があります。
資金調達の選択肢と留意点
キャッシュフロー改善の努力をしてもなお資金が不足する場合は、外部からの資金調達を検討します。
選択肢としては、日本政策金融公庫や制度融資などの公的融資、民間の金融機関からのプロパー融資、ビジネスローン、さらにはファクタリング(売掛債権の売却)など多岐にわたります。
それぞれの調達方法には、金利、審査期間、必要な担保などの条件が異なります。
自社の状況や緊急度に合わせて最適な手段を選ぶことが重要ですが、安易な借入は将来の財務CFを圧迫するため、返済計画を綿密に立てるべきです。
中小企業のキャッシュフロー改善の具体的ロードマップ
キャッシュフローの改善は、一朝一夕には実現しません。
企業の状況に応じて、段階的に取り組むことが成功の鍵です。
ここでは、緊急時から成長期までを見据えたロードマップを提示します。
緊急対応:回収前倒し・支払期間調整・在庫と費用棚卸
まず資金繰りが逼迫している緊急時には、即効性のある対策が必要です。
具体的には、滞留している売掛金の回収を最優先で行い、同時に主要な仕入先に対して支払期間の延長を交渉します。
さらに、すぐに現金化できる不要な在庫がないか洗い出し、削減できる経費がないか全ての費用項目を徹底的に見直すことが求められます。
この段階では、1日でも早く手元現金を確保することが最重要課題です。
定着:請求サイクル短縮・在庫最適化・与信ルール整備
緊急時を乗り越えたら、次に改善を定着させるフェーズに入ります。
毎月の請求書発行から入金確認までのサイクルを仕組み化し、短縮を図ります。
また、販売データに基づいた需要予測を導入し、在庫の最適化を進めることで、不要なキャッシュアウトを防ぎます。
さらに、新規取引先の与信管理ルールを明確に定め、回収不能リスクを未然に防ぐ体制を構築することが、安定したキャッシュフローの基盤となります。
成長:ペイバック管理・資金調達の最適化・再投資判断
経営が安定し、成長を目指す段階では、より戦略的なキャッシュフロー管理が求められます。
設備投資などを行う際には、その投資が何年で回収できるか(ペイバック期間)を必ず算出し、投資判断の精度を高めます。
また、複数の借入金をより有利な条件のものに借り換えるなど、財務構成の最適化も検討します。
そして、生み出されたキャッシュをどこに再投資すれば企業価値が最大化するのか、長期的な視点での意思決定が重要になります。
中小企業のキャッシュフロー運用体制
キャッシュフローを継続的に管理し、経営に活かすためには、社内の運用体制を構築することが不可欠です。
ここでは、その具体的な方法について解説します。
週次、月次のモニタリング設計
キャッシュフローは、年に一度の決算時に確認するだけでは不十分です。
理想的には、月次でキャッシュフロー計算書と資金繰り表を作成し、経営状況をタイムリーに把握することが望ましいでしょう。
特に資金繰りが厳しい状況では、週次で入出金予定を確認し、短期的な資金ショートのリスクを常に監視する体制が必要です。
定期的なモニタリングを習慣化することで、問題の早期発見と迅速な対策が可能になります。
会計ソフトやBI、銀行APIの活用
手作業でのキャッシュフロー管理には限界があります。
近年では、多くの会計ソフトにキャッシュフロー計算書の自動作成機能が搭載されています。
また、複数の銀行口座の入出金データを自動で取得・集計できる銀行API連携サービスや、データを可視化するBIツールを活用することで、モニタリング業務を大幅に効率化できます。
こうしたITツールを積極的に活用し、リアルタイムに近い形で自社のキャッシュフローを把握できる環境を整えることが重要です。
中小企業のキャッシュフロー に関してよくある質問
ここでは、中小企業の経営者からよく寄せられるキャッシュフローに関する質問とその回答をまとめました。
利益は出ているのに現金が足りないのはなぜ?
これは「勘定合って銭足らず」と呼ばれる典型的な状態で、黒字倒産の原因ともなります。
主な理由として、①売掛金の回収が支払よりも遅い、②棚卸資産(在庫)が過剰になっている、③借入金の返済額が大きい、④多額の設備投資を行った、などが挙げられます。
損益計算書上の利益は、あくまで会計上の数字であり、実際の現金の動きとはタイムラグがあることを理解する必要があります。
計算書は年次だけで十分?月次で見るべき?
年次での確認だけでは、経営判断のスピードに対応できません。
中小企業こそ、月次でキャッシュフロー計算書を作成し、資金繰りの状況を把握することが強く推奨されます。
月次でPDCAサイクルを回すことで、キャッシュフロー悪化の兆候を早期に掴み、手遅れになる前に対策を打つことができます。
間接法だけで運用して問題ない?
実務上、多くの中小企業では間接法で十分対応可能です。
間接法は、損益計算書と貸借対照表があれば作成でき、利益とキャッシュフローの差異の要因を分析しやすいというメリットがあります。
直接法(主要な取引ごとに現金の収入・支出を総額で表示する方法)は、より詳細な分析が可能ですが、作成に手間がかかるため、まずは間接法での運用を定着させることが現実的です。
資金繰り表とキャッシュフロー計算書の使い分けは?
キャッシュフロー計算書が「過去」の一定期間における現金の増減の要因を分析するための財務諸表であるのに対し、資金繰り表は「未来」の現金の入出金予定を管理し、資金ショートを防ぐための管理資料です。
キャッシュフロー計算書で過去の実績を分析し、その結果を未来の資金繰り表の予測精度向上に活かす、という形で両者を使い分けることが重要です。
中小企業でもキャッシュフローを明確化して利益を伸ばそう!【まとめ】
本記事では、中小企業におけるキャッシュフローの重要性から、計算書の見方・作り方、具体的な改善策、そして日々の運用体制までを網羅的に解説しました。
キャッシュフローとは単なるお金の流れではなく、企業の血液とも言える重要な経営指標です。
損益計算書上の利益だけを見ていては、資金ショートという思わぬ落とし穴にはまる危険性があります。
まずは自社のキャッシュフローを正確に把握することから始め、今回紹介したチェックリストや改善のロードマップを参考に、できるところから着手してみてください。
会計ソフトなどのツールも活用しながら、月次でのモニタリングを習慣化することで、お金の不安から解放され、攻めの経営判断が可能になります。
安定したキャッシュフローは、企業の持続的な成長を支える強固な土台となるでしょう。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能












