組織体制とは?種類やメリット・デメリット・作り方などをわかりやすく解説
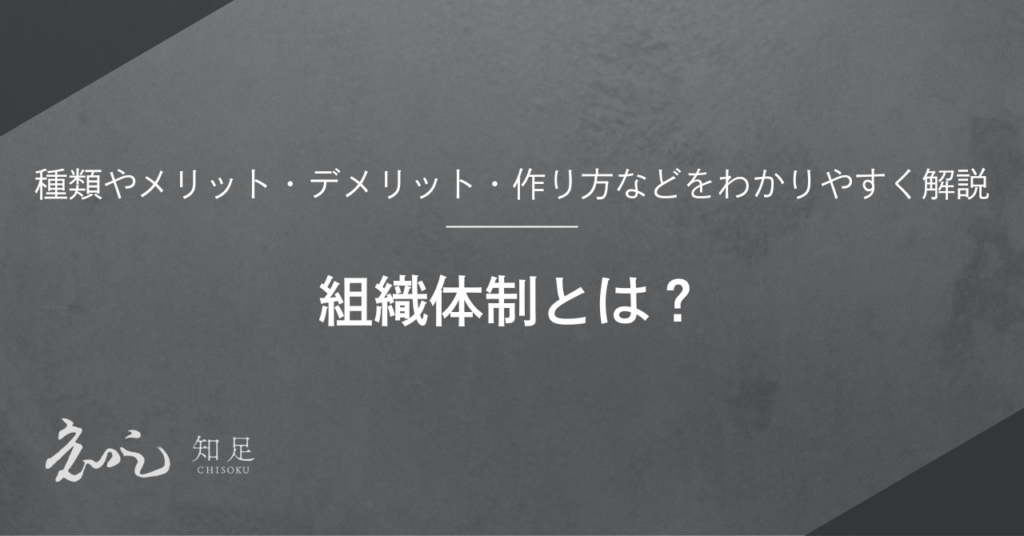
「社員は増えているのに、なぜか業務効率が上がらない」「部門間の連携がうまくいかず、プロジェクトが前に進まない」こうした悩みを抱えていませんか。
組織の成長に伴い、これまでのやり方が通用しなくなるのは自然なことです。
しかし、この問題を放置すれば、企業の成長は鈍化し、従業員のモチベーション低下や人材流出につながりかねません。
その根本的な解決策が、自社の戦略や規模に合った組織体制の構築です。
この記事では、組織体制の基本的な種類から、具体的な作り方のステップ、メリット・デメリットまでを網羅的に解説します。
自社に最適な組織の形を見つけ、持続的な成長を実現するための第一歩を踏み出しましょう。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
組織体制とは?
組織体制とは、企業が目標を達成するために必要な役割分担や指揮命令系統を定めた、公式な仕組みのことです。
誰が何を担当し、誰に報告・相談するのかという、組織の骨格やルール全体を指します。
優れた組織体制は、業務の効率化や迅速な意思決定を促し、企業の成長を力強く後押しします。
逆に、企業規模や事業内容に合わない体制では、情報伝達の遅れや部門間の対立といった問題が生じ、経営の足かせになりかねません。
そのため、事業戦略や企業文化に合わせて最適な形を設計し、必要に応じて見直していくことが極めて重要です。
組織体制の種類
ここでは、企業で採用されることの多い、代表的な5つの組織体制を解説します。
それぞれの特徴を理解し、自社に最適な形を見つけるための参考にしてください。
職能別組織体制
職能別組織体制は、開発、製造、営業、人事、経理といった専門的な機能(職能)ごとに部門を編成する形態です。
各部門に特定の分野の専門家が集まるため、専門知識やスキルの蓄積が進み、業務の効率性が高まる点が大きな特徴です。
これにより、各部門はそれぞれの業務に集中でき、高品質なアウトプットを生み出しやすくなります。
多くの企業で採用されている伝統的な形といえるでしょう。
一方で、各部門が自部門の利益を優先しがちになる「セクショナリズム」に陥る危険性もはらんでいます。
部門間の連携が希薄になり、組織全体としての意思決定が遅れることがある点には注意が必要です。
事業部制組織体制
事業部制組織体制とは、製品やサービス、あるいはエリア(地域)といった事業単位で部門を構成する組織形態です。
各事業部が独立した組織のように、開発から営業、マーケティングまでの機能を持ち、事業に関する意思決定権限と責任を担います。
この体制の最大のメリットは、事業ごとの意思決定が迅速に行える点です。
市場の変化に素早く対応できるため、事業の成長を加速させやすくなります。
また、事業部長には経営者としての視点が求められるため、次世代の経営幹部候補を育成する場としても機能します。
しかし、各事業部が独立採算のようになるため、事業部間で人材やノウハウの交流が少なくなり、全社的なシナジーが生まれにくいという側面があるのです。
また、各事業部に同様の機能(人事、経理など)が設置されることで、経営資源の重複が生じ、コストが増大する可能性も考慮しなければなりません。
マトリックス型組織体制
マトリックス型組織体制とは、職能別と事業部制を組み合わせたクロスした体制です。
従業員は機能部門と事業・プロジェクトの両方に所属し、二方向の指揮系統を持ちます。
例えば、開発部の社員が新製品プロジェクトチームにも参加するような形です。
マトリックス型のメリットは、柔軟な人材活用とシナジー創出にあります。
機能別組織の専門性追求と事業部制の機動力を両立でき、組織全体でリソースを有効活用できます。
重複業務も抑えられ、必要に応じ人材をプロジェクト横断で投入できるため、複雑な課題にも対応しやすいでしょう。
ただし二重の指揮系統ゆえにメンバーが混乱しやすい点には注意が必要です。
上司同士で方針が異なる場合、現場が板挟みになる恐れもあります。
そのため組織全体でビジョンを共有し、上長同士が連携して部下をフォローするなど、運用面での工夫が不可欠です。
カンパニー制組織体制
カンパニー制組織体制とは、事業部を社内カンパニー(社内会社)のように独立経営させる体制です。
基本的な構造は事業部制と似ていますが、各カンパニーに対して裁量権と責任をより大きく委ねる点が異なります。
要するに、社内に複数の“小会社”が存在するイメージです。
カンパニー制の利点は、極めて迅速な意思決定と起業家的な組織運営が可能になることです。
カンパニーには利益責任だけでなく経営判断の自由度も与えられるため、市場変化に柔軟に対応できます。
またリーダーやメンバーが経営者視点を磨く場にもなり、人材育成の面でもプラスに働きます。
一方でカンパニー間の交流が減り、他事業とのシナジーが生まれにくい欠点があるのです。
組織全体の最適化より各社内カンパニーの部分最適に陥らないよう、横断的なコミュニケーション機会を設けるなどの対策が求められます。
プロジェクト(チーム)型組織体制
プロジェクト(チーム)型組織体制は、特定の目的や課題を解決するために、各部門から専門スキルを持つ人材を集めて一時的なチームを編成する形態です。
このチームは、プロジェクトが完了すれば解散します。IT業界のシステム開発や、新規事業の立ち上げなど、期限が明確な業務に適しています。
最大のメリットは、課題に対して最も適した人材でチームを構成できるため、変化に強く、高い機動力を発揮できる点です。
その一方で、プロジェクトが終了するとチームが解散するため、獲得したノウハウが組織全体に蓄積されにくいというデメリットも指摘されています。
組織体制の整え方
効果的な組織体制を構築するには、現状の分析から移行計画まで段階的なアプローチが重要です。
以下に組織体制を整備する主なステップを紹介します。
順を追って取り組むことで、抜け漏れなく理想の体制に近づけられるでしょう。
現状診断
まず最初に組織の現状を診断します。
現行の組織図や業務フローを洗い出し、どこに課題があるかを客観的に把握しましょう。
主観に頼らず、アンケート調査やヒアリング、各種データ分析を通じて現状を定量・定性の両面から分析します。
例えば、従業員アンケートでコミュニケーション上の問題点を探ったり、部署間の連携頻度を数値で捉えるといった手法です。
部門横断の討議を行うことで、普段見えにくい部署間の断絶やサイロ化の実態が浮き彫りになる場合もあります。
重要なのは、表面的な症状だけでなく根本原因を見極めることです。
離職率が高いのは評価制度か組織風土に問題があるのか、意思決定が遅いのは権限配分やプロセスに原因があるのか、といった点を掘り下げます。
現状診断をしっかり行えば、次のステップである組織設計の方向性が明確になるでしょう。
目的とKPIの設定
続いて組織改革の目的を明確化し、達成度を測るKPIを設定します。
現状診断で判明した課題を踏まえ、「何のために体制を見直すのか」「新しい組織で実現したい目標は何か」を言語化しましょう。
企業としてのビジョンや経営戦略とも照らし合わせ、組織改編の方向性を定めます。
例えば「市場対応力の強化」が狙いなら、よりフラットで迅速に動ける体制を目指す、といった具合です。
目標が定まったら具体的なKPI(重要業績評価指標)を設けます。
新体制導入後に計測すべき定量指標・定性指標を洗い出し、現状値と目標値を設定しておきます。
定量指標の例としては売上高・利益率の向上、人材定着率アップ、意思決定に要する日数短縮などが挙げられるでしょう。
定性指標として従業員満足度や部門間協力の頻度などもバランス良く取り入れます。
これらKPIによって組織体制改革の効果を測り、後述する評価制度とも連動させることで、組織運営をPDCA的に改善していけるのです。
役割/責任/権限設計
組織目的が定まったら、各部署およびポストの役割・責任・権限を再設計します。
現状診断で洗い出した問題を踏まえ、組織のどの部分に変更が必要かを検討します。
具体的には、「どの部門を新設・統合・廃止するか」「各部署のミッションは何か」「部署間の関係性(縦・横の連携)はどうするか」などを設計していくのです。
同時に各役職ごとの責任範囲と意思決定権限を定義します。
誰が何について最終決定できるのか、誰に報告すべきなのかといった指揮命令系統を明確に組み込むことが重要です。
例えば、新体制では部長職には一定の予算執行権限を委譲し、現場判断でできる範囲を拡大する、といった具合です。
こうした職能と役割分担を整理することで、各メンバーが自身の役割に集中でき組織全体として一体感が生まれます。
役割定義にあたっては、人員構成や各人のスキルも考慮し、適材適所となるよう留意します。
会議体/稟議/意思決定ラインの設計
効率的な組織運営には、情報共有と意思決定のプロセス設計が欠かせません。
まずは、目的が曖昧な定例会議や形骸化した会議がないかを見直しましょう。
そして、どのような情報を、どの会議体で、誰が、どのように意思決定するのかというルールを明確に定めます。
稟議プロセスについても、承認者の数や承認ルートが複雑になりすぎていないかを確認し、必要に応じて簡素化します。
意思決定のラインをシンプルにすることで、組織全体のスピード感を高めることができます。情報伝達のルールを明確にすることも重要です。
横断連携の設計
組織再編後に生じがちな弊害として、部門間の断絶(サイロ化)があります。
その対策として、横断的な情報共有と協働の仕組みを設計します。
具体的には、定期的な全社横断プロジェクトや部門長会議、1on1ミーティングやオープンディスカッションの場を設けるなど、部署を超えて情報交換と意思疎通が図れるようにしましょう。
また社内SNSやチャットツール、プロジェクト管理ツールなどITプラットフォームを活用して情報共有のハブを作ることも有効です。
組織図上の構造だけでなく、情報の流れを円滑にする仕組みを組み込むことで、部署間・階層間の連携がスムーズになります。
例えば週次の部門長会議で各部門の状況を共有したり、製品開発など特定テーマで横断チームを常設する、といった取り組みです。
評価や目標も一部は全社共通KPIを設定することで、部門最適ではなく全社最適の意識を醸成します。
こうした横串の連携策を講じることで、新たな組織体制においてもサイロ化を防ぎ一体感を維持できます。
評価制度(OKR等)との整合
組織体制の変更に合わせて、人事評価制度や目標管理制度も整合性を取ることが大切です。
特にOKR(Objectives and Key Results)のような目標管理手法を導入している場合、新組織の構造に合わせて目標設定の階層や内容を見直します。
組織再編によって役割や権限が変われば、各人に求められる成果指標も変化します。
そこで、各部署・各役職のKPIやOKRが組織全体の目標と矛盾しないよう再設定し、評価基準もアップデートしましょう。
例えば、従来は個人単位だった目標をチーム目標に置き換える、あるいは新設部署には新たなKPIを設定する、といった対応です。
キャリアパス制度などとも連動させ、昇進条件や評価基準を明確化することで従業員は自ら目標に向かいやすくなります。
評価制度と組織体制がかみ合っていれば、従業員は自分の役割と目標が会社全体の成功にどう貢献するかを理解しやすくなり、モチベーション向上にもつながります。
権限委譲したにも関わらず評価が旧態依然のままでは現場は萎縮してしまうため、新体制の狙いを反映した人事制度設計が必要です。
移行計画
最後に、新しい組織体制へのスムーズな移行計画を立てます。
組織変更の実施時期を決め、関係者への周知と準備期間を確保します。
可能であれば移行は年度切替や期初など区切りの良いタイミングで行うと混乱が少ないでしょう。
移行計画では、現組織から新組織への配置転換や組織図変更のプロセスを具体的に示し、各ステップの責任者を定めます。
「〇月中に組織変更案内を発出、〇月末までに人事異動内示、翌〇月から新組織運用開始」などとスケジュールを引き、関係部署と共有します。
併せて、変更に伴うリスクや懸念点への対応策も準備しておきましょう。
例えば「権限移譲に不安を感じる管理職に対し事前研修を行う」「一時的な業務停滞を防ぐため○ヶ月は旧組織と並行運用期間を設ける」などです。
必要に応じてパイロットチームやトライアル期間を設定し、小規模にテストしてから全社適用すると安全です。
移行に際しては従業員への丁寧な説明とフォローが不可欠です。
新体制の目的やメリットを繰り返し伝え、不安や疑問に答える場を設けましょう。
組織体制の変更は会社の根幹に関わるため、十分な準備とコミュニケーションを行いながら進めることが望ましいです。
組織体制を整えるのメリット3選
適切に整備された組織体制は、企業に多くの恩恵をもたらします。
ここでは、組織体制を整えることで得られる主要なメリットを3つ紹介し、それぞれがどのように企業の成長に貢献するのかを解説します。
意思決定スピードの向上と責任の明確化
的確な組織体制を敷く最大のメリットは、意思決定が早まり責任所在がクリアになることです。
組織の指揮系統と権限が整備されていれば、「誰が決めるべきか」が一目瞭然のため迷いなく判断できます。
例えば、従業員一人ひとりが自部署での役割・責任を理解し、決裁ルートも明確になっていれば、現場で判断すべきことは迅速に処理できるでしょう。
結果として上層部へのお伺い待ちによるタイムロスが減り、現場対応力や市場への反応速度が向上します。
また「この件は誰の責任か」が明確になるため、業務推進上のモヤモヤも解消されます。
属人的な判断に頼らず、規程に従って意思決定されることで社内の公平性も担保されるのです。
加えて、責任範囲がはっきりしていると各自が自律的に職務を果たそうとする意識が芽生えます。
こうした責任の明確化はチームの結束力を高め、問題発生時も責任逃れなく迅速に対処できる土壌となるのです。
戦略と業務の整合によるリソース最適化/重複排除
組織体制を整えることで、経営戦略と現場業務がかみ合い、リソース配分の最適化が図れます。
戦略に基づいて部署や役割を設計すれば、各部署が担うべきミッションが明確になるため、全社的に見て無駄な業務や人員の偏在が是正されます。
例えば、似たような仕事を複数部署で二重に行っていた場合、体制見直しによりどちらかに集約することで効率化できるのです。
業務の重複排除はそのままコスト削減や生産性向上につながるでしょう。
さらに専門性に応じた配置によって、従業員は自身の強みを最大限発揮できます。
適材適所の人員配置は組織力の底上げとなり、結果として経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の有効活用が実現します。
戦略と業務が整合している組織では、各部署の目標が会社全体の目標に直結するため、無駄な施策に人手や予算を割くことも減るでしょう。
例えば、事業部制で各事業ごとに収支責任を持たせれば、利益に直結しない活動は自然と淘汰され、経営資源が成長分野に集中します。
このように組織体制の整備は戦略的なリソース配分を後押しし、企業全体の効率と効果を高めるのです。
人材育成とキャリアパスの可視化
組織体制を明確にすることは、従業員の成長を促す上でも有効です。
各部門や役職に求められるスキルや役割が定義されることで、従業員は自身のキャリアパスを具体的にイメージしやすくなります。
自分が将来どのようなポジションを目指せるのか、そのために何を学ぶべきかがわかるため、学習意欲や仕事へのモチベーション向上につながります。
例えば、職能別組織では専門性を究める道筋が、事業部制では経営スキルを身につける道筋が見えやすくなるのです。
計画的な人材育成やサクセッションプラン(後継者育成計画)の策定も容易になります。
組織体制を整えないデメリット3選
どんな組織体制にも一長一短があり、メリットの裏には注意すべきデメリットも存在します。
ここでは組織体制に関連して生じやすい代表的なデメリットを3つ挙げ、それぞれ解説します。
あらかじめ弱点を理解し、適切な対策を講じることが健全な組織運営には不可欠です。
サイロ化/情報断絶による横断連携の不足
組織体制が硬直化すると、部門間の壁が厚くなる「サイロ化」という問題が発生しやすくなります。
特に、専門性を追求する職能別組織や、独立性の高い事業部制で顕著に見られる現象です。
各部門が自分たちの目標達成のみを優先し、他部門との情報共有や協力を怠るようになります。
その結果、全社的な視点での最適な判断ができなくなったり、部門間で似たような業務を重複して行っていたりする非効率が生まれます。
顧客からの問い合わせが部署間でたらい回しにされる、といった問題もこのサイロ化が原因であることが多いです。
二重指揮や合意形成に伴う調整コストの増大
マトリックス型組織体制のように、一人の従業員が複数の上司を持つ構造では、指揮命令系統の混乱が生じやすいというデメリットがあります。
二人の上司から矛盾した指示が出された場合、従業員はどちらを優先すべきか悩み、業務が停滞する可能性があります。
また、関係者が増えることで、何かを決定する際の合意形成に時間がかかり、調整コストが増大する傾向もあるのです。
全員の意見を聞いているうちに、市場の好機を逃してしまうことにもなりかねません。
このような体制を機能させるには、明確なルール設定と高度なコミュニケーション能力が不可欠です。
中央集権や形骸化による現場の自律性低下/スピード鈍化
トップダウンの意思決定を重視する中央集権的な組織体制が強すぎると、現場の従業員が自ら考えて行動する自律性が失われる恐れがあります。
すべての判断を上層部に仰ぐ文化が定着し、指示待ちの姿勢が蔓延してしまうのです。
このような状態では、現場で発生した問題への対応が遅れ、組織全体のスピードが著しく鈍化します。
また、一度決めた組織体制が環境の変化に対応できずに「形骸化」してしまうこともあります。
実態に合わないルールや手続きが残り続け、かえって業務の足かせとなるケースも少なくありません。
組織体制に関してよくある質問
最後に、組織体制について多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめます。
組織体制と組織構造は何が違う?
組織体制と組織構造はほぼ同義で使われることが多く、大きな違いはありません。
どちらも組織内の役割分担や仕組みを指す言葉です。
ただ厳密に言えば、組織構造は組織の形そのもの(部署の配置や階層、権限関係など)を表し、組織体制はその構造を含めた運営の仕組み全般を指すニュアンスがあります。
例えば、「組織構造を変える」と言えば組織図の編成替えを意味し、「組織体制を整える」と言えば構造に加え制度やルール面も含め整備する、といった使い分けです。
とはいえ日常のビジネス会話では厳密に区別せず用いられることが多いです。
実際、企業紹介でも「組織構造(組織体制)の種類」というように並記されるケースもあります。
要はどちらも組織の仕組みという大枠の意味だと捉えて差し支えないでしょう。
どの規模なら職能別/事業部制/マトリックスが向く?
一般的に、社員数が少なく事業領域が単一の企業には職能別組織が適しています。
シンプルな構造でトップ主導の運営がしやすいため、多くの中小企業で採用されています。
事業が複数に広がり組織規模が大きくなってきた段階では、事業部制組織の導入が検討されるでしょう。
実際、日本で事業部制を最初に導入した松下電器(現パナソニック)以降、現在では大多数の上場企業が採用するほど一般的な体制となっています。
一方、マトリックス組織は組織規模が非常に大きく、グローバル展開や複数プロジェクトの並行推進など限られた人材を柔軟に配置する必要がある場合に導入されるケースが多いです。
マトリックスは運用が難しく管理コストもかかるため、十分なマネジメントリソースがある大企業や先進的なプロジェクト型企業で採用される傾向にあります。
また、明確な導入目的(例えば製品軸と地域軸の両面で組織効果を出したい等)がない場合はかえって混乱するため、組織成熟度が高い企業でないと効果を発揮しにくいでしょう。
権限委譲や評価制度(OKR等)はどう設計する?
権限委譲や評価制度は、組織体制の目的と一貫性を持たせることが重要です。
権限委譲を設計する際は、まず「どのレベルの意思決定を現場に任せるか」を具体的に定義します。
例えば、一定金額以下の経費使用や特定業務のプロセス改善などは、部長や課長の承認なしで実行できるルールを設けます。
評価制度(OKR等)は、会社の目標から部門、個人の目標へとブレークダウンする形で設計するのです。
これにより、全従業員が会社の目標達成に貢献している意識を持ちやすくなり、組織体制が目指す方向へと行動が促進されます。
体制変更のタイミングと進め方の注意点は?
体制変更を検討すべきタイミングは、事業の多角化、急激な人員増加、M&A、あるいは意思決定の遅延や部門間の対立が顕著になった時などです。
進め方の注意点として、第一に「なぜ変更するのか」という目的を全社で共有することが挙げられます。
目的が不明確なまま進めると、従業員の混乱や反発を招きます。第二に、移行は段階的に行い、混乱を最小限に抑えることです。
最後に、変更後も効果を定期的に検証し、必要に応じて柔軟に修正していく姿勢が、変革を成功に導く鍵となります。
組織体制のまとめ
組織体制とは、企業の目標達成を支えるための役割分担や指揮命令系統の仕組みです。
代表的なものに、専門性を高める職能別組織、事業ごとの迅速な意思決定を促す事業部制、両者を組み合わせたマトリックス型などがあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
自社に最適な組織体制を構築するには、まず現状診断で課題を明確にし、達成すべき目的とKPIを設定することが不可欠です。
その上で、役割・責任・権限を具体的に設計し、会議体や評価制度といった周辺の仕組みも合わせて整備します。
体制変更は大きなプロジェクトですが、計画的に進めることで、意思決定の迅速化やリソースの最適化といった多大な恩恵をもたらします。
本記事を参考に、貴社の事業成長を加速させる、最適な組織のあり方をぜひ見直してみてください。













