ブルーオーシャンの見つけ方!戦略で学ぶ市場開拓ロードマップ
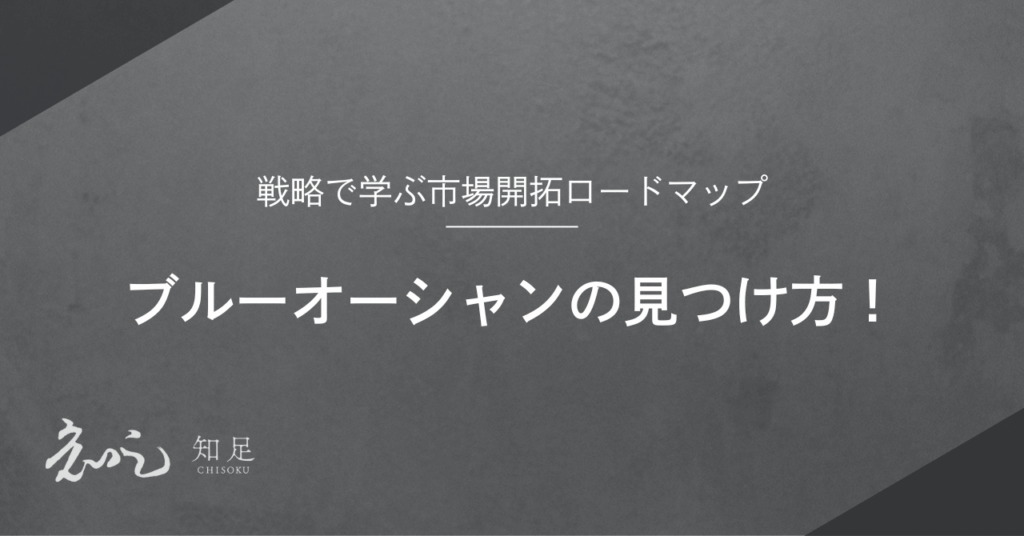
激しい価格競争や終わりの見えない消耗戦に、日々頭を悩ませていませんか。
競合と同じ土俵で戦い続ける限り、利益は徐々に減少し、自社の強みやブランド価値も埋もれていってしまいます。
しかし、競争自体を無意味にする未開拓の市場、「ブルーオーシャン」を見つけ出す戦略があります。
この記事では、ブルーオーシャンを発見するための具体的な準備、実践的なプロセス、そして成功の鍵となるフレームワークまでを網羅した市場開拓のロードマップを解説します。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
目次
ブルーオーシャンとは?
ブルーオーシャン戦略とは、競争の激しい既存市場(レッドオーシャン)を避け、競争のない未開拓の市場空間を創造し、新しい需要を掘り起こす経営戦略です。
レッドオーシャンでは、他社とシェアを奪い合う消耗戦が避けられません。
結果として、価格競争に陥りやすく、企業の収益性は圧迫されがちです。
一方で、ブルーオーシャンは、これまで誰も気づかなかった顧客価値を提供することで、競争自体を無意味にします。
市場の境界線を再定義し、独自のルールで事業を展開できるため、高い収益性と持続的な成長が期待できます。
市場の成熟化や技術のコモディティ化が進む現代において、多くの企業がこのブルーオーシャン戦略に活路を見出そうとしています。
新しい価値を創造し、市場の先駆者となるための航海術、それがブルーオーシャン戦略の本質です。
ブルーオーシャンの見つけ方
本パートを理解することで、市場の全体像を把握し、自社の立ち位置を明確にするための準備が整います。
具体的な分析手法を知り、戦略立案の土台を固めましょう。
PEST分析と5フォース分析で市場を俯瞰
ブルーオーシャンを見つける最初のステップは、自社を取り巻く環境をマクロとミクロの視点から正確に把握することです。
PEST分析は、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)という4つの外部環境が、自社にどのような影響を与えるかを分析する手法です。
これにより、社会の大きなトレンドや将来の変化を予測し、新たな事業機会の種を見つけ出せます。
次に、5フォース分析を用いて業界の構造を理解しましょう。
この分析では「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」「既存競合との敵対関係」という5つの力が業界の収益性にどう影響するかを明らかにします。
業界の魅力度や競争の厳しさを客観的に評価することで、どこにブルーオーシャンの可能性があるかを探る手掛かりを得られるのです。
戦略キャンバスで価値曲線を描く
市場環境を分析した後は、戦略キャンバスを用いて業界の競争状況を視覚化します。
戦略キャンバスとは、横軸に業界が顧客へ提供している様々な価値要素(価格、品質、サービスなど)を、縦軸にそれぞれの提供レベルをプロットしたグラフです。
このキャンバス上に自社と競合他社の現状を描いたものが「価値曲線」と呼ばれます。
この価値曲線を描くことで、業界内で各社がどのような点に力を入れ、競争しているかが一目瞭然になります。
競合他社と似たような価値曲線を描いている場合、それはレッドオーシャンで戦っている証拠です。
ブルーオーシャンを創造するためには、この既存の価値曲線とは全く異なる、新しい形の価値曲線を意図的に描く必要があります。
戦略キャンバスは、そのための思考の出発点となる重要なツールです。
ブルーオーシャンの見つけ方のプロセス
市場の現状分析を終えたら、次はいよいよブルーオーシャンを具体的に創造するための行動に移ります。
本パートを理解することで、アイデアを形にし、事業を成功に導く実践的なプロセスを学べます。
【4アクション】フレームワーク活用術
ブルーオーシャン戦略の中核をなすのが「4つのアクション」というフレームワークです。
これは、既存の価値曲線を変革し、新しい市場を創造するための具体的な思考ツールです。
4つの問いに答えることで、業界の常識を打ち破るヒントが得られます。
- 取り除く(Eliminate): 業界で当たり前とされているものの、顧客価値に直結しない要素は何か?
- 減らす(Reduce): 業界標準以上に過剰品質となっている要素は何か?
- 増やす(Raise): 業界標準よりも大胆に引き上げるべき要素は何か?
- 付け加える(Create): 業界がこれまで提供してこなかった、全く新しい価値は何か?
これらのアクションを通じて、コストを削減しながら顧客への提供価値を高める「バリューイノベーション」を実現します。
>>事業戦略のおすすめ本9選!初心者でも分かりやすいものから名著まで紹介
【6パス】アプローチで視野を横断
既存の市場の枠組みを超えて、新しい市場空間を発見するための視点を提供してくれるのが「6パス」アプローチです。
多くの企業は自社の業界内に視野が限定されがちですが、6パスは意図的にその視野を広げ、新たな気づきを促します。
| パス | 視点 | 概要 |
|---|---|---|
| 第1のパス | 代替産業に学ぶ | 自社の製品やサービスと同じ機能や目的を果たす、異なる形態の産業に着目する。 |
| 第2のパス | 業界内の他の戦略グループから学ぶ | 同じ業界内でも、異なる戦略(例:高級路線 vs. 格安路線)をとるグループからヒントを得る。 |
| 第3のパス | 買い手グループに目を向ける | 製品の購入者だけでなく、利用者や影響を与える人も含めた、一連の「買い手チェーン」全体を分析する。 |
| 第4のパス | 補完的な製品やサービスを見渡す | 自社の製品やサービスと組み合わせて、補完的な製品・サービスの中に、未解決の課題がないか探る。 |
| 第5のパス | 機能的か情緒的か、業界の志向を問い直す | 業界が機能性で訴求しているなら情緒的な価値を、情緒性で訴求しているなら機能的な価値を付加できないか検討する。 |
| 第6のパス | 将来を見通す | 時間軸をずらし、これから主流となるであろうトレンドを先取りし、自社の戦略に組み込む。 |
これらのパスに沿って思考を巡らせることで、凝り固まった固定観念を打破し、これまで見過ごされてきた事業機会を発見できます。
MVP検証とピボット判断のコツ
有望なアイデアが生まれたら、すぐに大規模な投資をするのではなく、まずMVP(Minimum Viable Product)で検証します。
MVPとは、顧客に価値を提供できる最小限の機能を持った製品やサービスのことです。
これを素早く開発し、実際の市場に投入することで、顧客のリアルな反応やフィードバックを収集します。
この検証プロセスを通じて、当初の仮説が正しかったのか、あるいは顧客の本当のニーズはどこにあるのかを学びます。
もし仮説が間違っていたり、より大きな事業機会が見つかったりした場合は、「ピボット」と呼ばれる事業の方向転換を迅速に判断することが重要です。
MVP検証とピボットを繰り返すことで、失敗のリスクを最小限に抑えながら、成功確率の高いビジネスモデルを構築していくことができます。
社内外データ活用で仮説精度を高める
ブルーオーシャンを見つけるプロセス全体において、勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて仮説の精度を高めることが成功の鍵を握ります。
社内データ、例えば顧客の購買履歴やウェブサイトのアクセス解析からは、既存顧客の隠れたニーズや行動パターンを読み取ることができます。
一方で、社外データも積極的に活用すべきです。
公的機関が提供する統計データは、市場の大きなトレンドを掴む上で非常に役立ちます。
実際に、政府統計「e-Stat」の人口動態などのデータを使い、市場規模や需要の予測ができます。
ブルーオーシャン戦略のメリット3選
ブルーオーシャン戦略の実行は、単に競争を避けるだけでなく、企業に多大な恩恵をもたらします。
本パートを理解することで、戦略がもたらす具体的なメリットを3つの側面から深く知ることができ、戦略実行への確信を深めることができるでしょう。
高利益率と価格決定権の確立
ブルーオーシャン戦略の最大のメリットは、高い収益性を確保できることです。
競争相手が存在しない、あるいはほとんどいない市場では、熾烈な価格競争に巻き込まれる心配がありません。
企業は、自らが創造した独自の価値に基づいて価格を設定する「価格決定権」を握ることができます。
顧客がその価値を認めれば、たとえ高価格であっても受け入れられます。
結果として、高い利益率を維持することが可能になり、その利益をさらなる研究開発やマーケティングに再投資するという、好循環を生み出せるのです。
これは、常にコスト削減の圧力にさらされるレッドオーシャンでは実現が難しい、大きなアドバンテージです。
市場シェア独占による参入障壁が味方に
新しい市場を創造した企業は、「先行者」として圧倒的に有利な立場を築くことができます。
最初に市場を切り拓いたことで、市場のルールやスタンダードを自社に有利な形で形成することが可能です。
顧客の頭の中に「この価値といえば、この企業」という強いブランドイメージを植え付けることができます。
一度顧客がその価値に慣れ親しむと、後から参入してきた競合他社の製品に乗り換える際には、心理的・物理的なコスト(スイッチングコスト)が発生します。
このスイッチングコストの高さが、事実上の参入障壁として機能するでしょう。
結果として、後発企業が容易にシェアを奪うことを防ぎ、長期にわたって市場を独占、あるいはそれに近い状態を維持することが可能になるのです。
ブランド独自性と長期的ファン化
ブルーオーシャン戦略は、他に類を見ない独自のブランドを構築する絶好の機会を提供します。
競合との比較ではなく、絶対的な価値を提供することで、企業のビジョンや世界観が際立ちます。
これは、単に製品やサービスが売れるというレベルを超えて、顧客の心を掴むことにつながるでしょう。
顧客は、その企業が提供する独自の価値観やストーリーに共感し、単なる消費者から熱心な「ファン」へと変化していきます。
ファンとなった顧客は、継続的に製品を購入してくれるだけでなく、口コミを通じて新たな顧客を呼び込んでくれる強力な応援団にもなります。
このようにして築かれたブランドとファンの関係は、模倣が困難な最も強力な競争優位性となり、企業の長期的な安定成長を支える基盤となるのです。
ブルーオーシャン戦略のデメリット3選
ブルーオーシャン戦略は大きな可能性を秘めている一方で、実行には無視できないリスクや困難が伴います。
本パートを理解することで、戦略を進める上で直面しうるデメリットを事前に把握し、現実的な計画立案とリスク対策に役立てることができます。
需要創造に伴う初期投資とコスト負担
ブルーオーシャン戦略は、まだ誰も気づいていない新しい市場を創造する活動です。
それは同時に、これまで存在しなかった需要をゼロから創り出すことを意味します。
顧客は、その新しい価値が自分たちにとってどれほど魅力的かをまだ知りません。
そのため、企業は製品開発だけでなく、市場を教育し、新しい価値を啓蒙するためのマーケティング活動に多大な初期投資を行う必要があります。
具体的には、大々的な広告宣伝、PR活動、顧客体験イベントの開催など、市場の認知度を高め、需要を喚起するためのコストが発生します。
この先行投資は、事業が軌道に乗るまでの間、企業の財務を圧迫する可能性があります。
投じたコストを回収し、利益を生み出すまでに時間がかかるリスクは、ブルーオーシャン戦略の大きな課題の一つです。
模倣や後発参入リスク
苦労して新しい市場を創造し、その事業が成功を収めると、必ずと言っていいほど模倣者や後発企業が現れます。
特に、豊富な資金力や販売網を持つ大企業が、成功事例を分析した上で、より洗練された製品やサービスを投入してくる可能性があります。
特許や意匠権などで強力に保護されていない限り、後発企業に市場を奪われるリスクは常に存在するのです。
先行者として築いた優位性も、後発企業の物量作戦の前には盤石とは言えません。
ブルーオーシャンは永遠に青い海であり続けるわけではなく、成功が知れ渡れば、またたく間に競争の激しいレッドオーシャンへと変貌してしまう危険性をはらんでいるのです。
常に革新を続けなければ、その地位を守ることはできません。
市場規模の不確実性と予測困難性
レッドオーシャンであれば、既存の市場調査データや競合の売上などから、ある程度の市場規模を予測することが可能です。
しかし、ブルーオーシャンは前例のない市場であるため、その市場が最終的にどのくらいの規模にまで成長するのかを正確に予測することは極めて困難です。
事業計画を立てる際、売上予測や投資対効果(ROI)の算出が非常に難しくなります。
せっかく多大なコストをかけて市場を創造したにもかかわらず、市場規模が想定よりもはるかに小さく、事業として成立しない「ニッチ過ぎる市場」であったというリスクも考えられます。
この予測の難しさが、投資判断を慎重にさせ、多くの企業が二の足を踏む要因にもなっています。
ブルーオーシャンの見つけ方に関してよくある質問
疑問を解消することで読後に行動へ移りやすくなります。
以下で代表的な質問を整理しました。
ブルーオーシャン戦略は本当に儲かるのか?
儲かる可能性は高いですが、成功が保証されているわけではありません。
競争相手のいない市場を創造できれば、価格競争に巻き込まれず高い利益率を実現できます。
しかし、その前提として、顧客が対価を払うほどの強いニーズが存在することが不可欠です。
需要創造の失敗や市場規模の見誤りといったリスクも伴うため、綿密な準備と検証プロセスを経て、成功確率を高める努力が重要になります。
見つけ方で最初に行うべきことは?
まずは自社が置かれている市場環境を徹底的に分析することです。
特に、戦略キャンバスを用いて、業界の競争要因と自社および競合の現状を可視化することから始めるのをおすすめします。
どこで他社と同じ土俵で戦ってしまっているのか、業界の常識は何かを客観的に把握することが、既存の枠組みから抜け出し、新しい価値を発見するための全ての始まりとなります。
中小企業でも実践できるの?
はい、中小企業にこそ実践する価値があります。
資金力や販売網といった経営資源で大企業に劣る中小企業にとって、同じ土俵での消耗戦は非常に不利です。
ブルーオーシャン戦略は、資本力ではなく、アイデアや着眼点、顧客への深い理解で勝負する戦略です。
大企業では見過ごされがちなニッチなニーズを捉え、小回りが利く点を活かして迅速に事業化することで、独自の市場を築くことが可能です。
競合がいない=成功とは限らない?
はい、その通りです。競合がいない理由は2つ考えられます。
一つは「まだ誰もその市場に気づいていない」というブルーオーシャンの可能性。
もう一つは、より可能性が高い理由として「そこに顧客の需要が存在しないから」というものです。
重要なのは、競合がいないという事実そのものではなく、なぜいないのかを深く考察することです。
そして、顧客が抱える強い課題を見つけ出し、それに対する独自の解決策を提供できるかどうかが成功の鍵を握ります。
ブルーオーシャンの見つけ方まとめ
ブルーオーシャン戦略は、血みどろの競争が繰り広げられるレッドオーシャンから脱却し、競争のない新たな市場を創造するための羅針盤です。
その本質は、競合を打ち負かすことではなく、新しい価値を創造することで競争自体を無意味にすることにあります。
この記事では、市場開拓へのロードマップとして、まずPEST分析や戦略キャンバスを用いた準備段階で市場を俯瞰し、自社の立ち位置を確認する重要性を解説しました。
次に、4つのアクションや6つのパスといった具体的なフレームワークを活用してアイデアを創出し、MVP検証で仮説の精度を高めていく実践的なプロセスを示しました。
もちろん、高い利益率やブランド独自性といった輝かしいメリットの裏には、需要創造のコストや模倣リスクといったデメリットも存在します。
これらの光と影の両面を深く理解し、データに基づいた客観的な分析と、小さな失敗を許容する柔軟な姿勢を持つことが成功の鍵を握ります。
本記事で示したステップを参考に、既成概念の枠を超え、貴社だけのブルーオーシャンを発見する航海へと、今こそ漕ぎ出してみてはいかがでしょうか。










