ペルソナ設計の作り方を5ステップで解説!BtoBで使えるテンプレートと成功事例
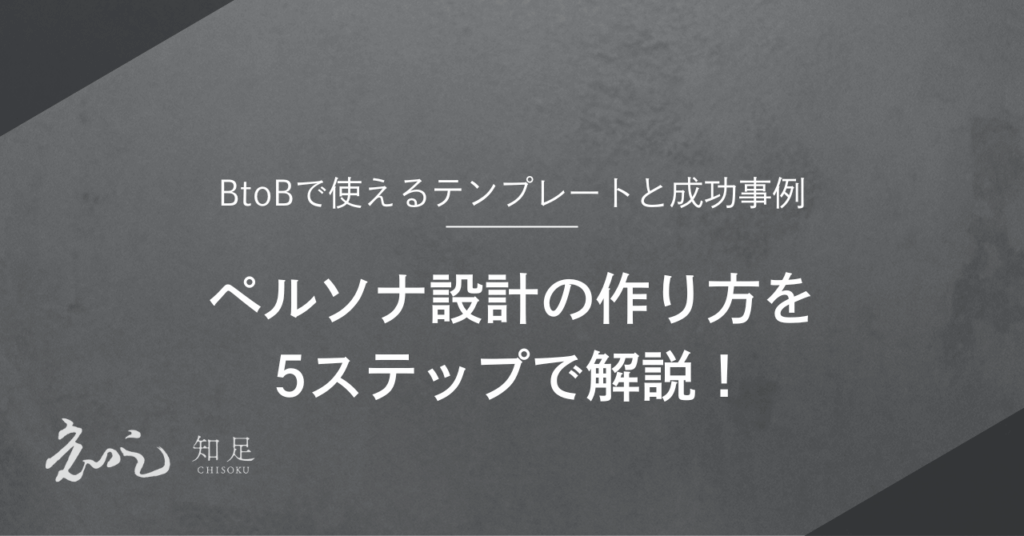
「自社の製品やサービスを、本当に届けたい顧客に届けられていますか?」
マーケティング施策を行う上で、このような課題を感じる方は少なくありません。
本記事では、マーケティングの成果を最大化するための「ペルソナ設計」について網羅的に解説します。
この記事を読めば、ペルソナ設計の理論から実践までを完全に理解し、明日から自社のマーケティングに活かすことができます。
・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。
・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営
・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能
>>N1インタビューとは?成功するやり方とN1分析の進め方を徹底解説
目次
ペルソナ設計とは?

まず、「ペルソナ設計」の基本的な概念と、なぜ現代のマーケティングにおいて不可欠とされているのかを深く理解していきましょう。
ペルソナ設計の基本的な定義
ペルソナ設計とは、冒頭でも触れた通り、自社の商品やサービスの典型的なユーザー像を、具体的な一人の人物として設定することを指します。
ここで重要なのが、よく似た言葉である「ターゲット」との違いです。
| ターゲット | 「30代・女性・東京都内在住・会社員」のように、年齢や性別、居住地などの属性データで区切られた「集団」を指します。 |
| ペルソナ | ターゲットの情報をさらに深掘りし、「大崎景子、32歳。IT企業のマーケティング部門で働く。情報収集はSNSとニュースアプリが中心で、休日はヨガに通う。最近の悩みは、仕事のスキルアップとプライベートの両立」というように、人格やライフスタイル、価値観、悩みまで設定した「個人」を指します。 |
ターゲット設定だけでは、同じ「30代女性」でもライフスタイルや価値観は千差万別です。
ペルソナとして個人のレベルまで解像度を上げることで、顧客のインサイト(行動の裏にある本音)をより深く理解できるようになるのです。
なぜ今、ペルソナ設計が重要なのか?
現代において、ペルソナ設計の重要性はますます高まっています。その背景には、主に2つの理由があります。
顧客ニーズの多様化
インターネットとスマートフォンの普及により、誰もが膨大な情報にアクセスできるようになりました。
その結果、個人の価値観やライフスタイルは細分化し、かつてのように「マス(大衆)」という大きな括りで顧客を捉えることが困難になっています。
ペルソナ設計は、この多様化した顧客の中から「自社が本当に向き合うべき人物像」を明確にするための羅針盤となります。
関係者間での顧客イメージの統一
商品開発、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、事業には多くのチームが関わります。
ペルソナが設定されていないと、各担当者が思い描く「顧客像」がバラバラになり、「Aさんは若者向けだと思っていたが、Bさんはファミリー層向けだと考えていた」といった認識のズレが生じます。
具体的なペルソナを一人設定し共有することで、チーム全員が同じ顧客イメージを持ち、一貫した方針で迅速な意思決定を下せるようになります。
ペルソナ設計がもたらすメリット3選
ペルソナ設計を正しく行うことで、企業は以下の3つの大きなメリットを得ることができます。
顧客理解が深まり、施策の精度が向上する
ペルソナの悩みや欲求、情報収集の方法を深く理解することで、「誰に」「何を」「どのように」伝えれば心が動くのかが見えてきます。
その結果、Webサイトのコンテンツ、広告のキャッチコピー、SNSの投稿内容など、あらゆる施策の精度が格段に向上し、費用対効果の最大化につながります。
コンテンツやプロダクトの方向性が明確になる
「この機能は、ペルソナの〇〇さんにとって本当に必要だろうか?」「このブログ記事は、〇〇さんの悩みを解決できるだろうか?」といったように、ペルソナを主語にして議論することで、開発や企画の方向性がブレなくなります。
ユーザー不在の機能開発や、独りよがりなコンテンツ作成を防ぐことができます。
チーム内の認識統一とコミュニケーションの円滑化
前述の通り、ペルソナはチーム共通の「顧客像」となります。
これにより、「〇〇さんなら、このデザインを好むはずだ」といった具体的な会話が生まれ、主観的な意見の衝突が減り、建設的な議論が促進されます。
部門間の連携もスムーズになり、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。
ペルソナ設計の具体的な作り方5ステップ
それでは、いよいよペルソナ設計の実践編です。
ここでは、誰でも再現できるよう、5つの具体的なステップに分けて作り方を解説します。
ステップ1:情報収集|リアルな顧客データを集める
ペルソナ設計で最も重要なのが、この情報収集のステップです。
リアルなデータに基づいて作成することが成功の鍵です。
収集すべきデータは「定量データ」と「定性データ」の2種類に大別されます。
定量データ(数値で測れる客観的な事実)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アクセス解析ツール | Googleアナリティクスなどで、サイト訪問者の年齢、性別、地域、閲覧ページ、流入経路などを把握します。 |
| 顧客データ | CRMや購買データから、既存顧客の年齢層、購入頻度、平均単価などを分析します。 |
| アンケート | Webアンケートツールを使い、数十〜数百人のユーザーから広く情報を集めます。 |
定性データ(数値化できない個人の感情や意見)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ユーザーインタビュー | 実際の顧客や見込み顧客に直接会い、5〜10人程度に1時間ほどのインタビューを行い、製品との出会いや購入の決め手、日々の悩みなどを深掘りします。 |
| 営業・CS担当へのヒアリング | 顧客と直接接している社内の担当者から、顧客の生の声やよくある質問といった顧客の実像を聞き出します。 |
| SNSやレビューサイトの口コミ | X(旧Twitter)や口コミサイトで自社製品や競合製品がどのように語られているかを調査し、顧客の本音を探ります。 |
ステップ2:情報整理とグルーピング
ステップ1で集めた膨大な情報を整理し、意味のあるかたまりに分類していきます。
この作業には、付箋やオンラインホワイトボードツール(Miroなど)、スプレッドシートが役立ちます。
- 情報の書き出し:収集したデータを「〇〇という課題を持っている」「〇〇というツールを使っている」といったように、意味のある単位でカードやセルに一つずつ書き出していきます。
- グルーピング:書き出したカードを眺め、似たような属性、行動、課題、価値観を持つものをグループにまとめていきます。例えば、「情報収集はSNSが中心」「専門家より友人の口コミを信頼する」といったカードを一つのグループにまとめます。
- パターンの発見:グループ分けをすることで、「Aという課題を持つ人は、Bという情報収集の仕方を好み、Cという価値観を持っている」といった顧客のパターン(セグメント)が見えてきます。
ステップ3:ペルソナの骨格を作成する
グルーピングによって見えてきた顧客パターンの中から、自社にとって最も重要で、象徴的だと思われるグループを一つ選び、ペルソナの骨格を作っていきます。
この段階では、まず基本的なプロフィール項目を埋めていきます。
- 氏名、年齢、性別
- 居住地、最終学歴
- 職業、役職、業種、企業規模(BtoBの場合)
- 年収、家族構成
氏名や具体的な年齢を設定することで、単なるデータのかたまりではなく、一人の人間として捉えやすくなります。
ステップ4:ペルソナに人格とストーリーを与える
骨格に肉付けをし、ペルソナにリアルな人格とストーリーを与えていきます。
ここでの目標は、チームの誰もが「〇〇さんなら、きっとこう考えるだろう」とありありと想像できるレベルに仕上げることです。
ステップ2で整理した定性データを元に、以下の項目を具体的に記述していきます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 性格、価値観 | どんな性格か(内向的、社交的など)、何を大切にしているか(安定、成長、プライベートなど)。 |
| ライフスタイル | 1日のスケジュール、休日の過ごし方、趣味、情報収集に使うメディアやデバイス。 |
| 目標と課題 | 仕事やプライベートで達成したい目標は何か、そのためにどんな課題や悩みを抱えているか。 |
| 自社製品との関わり | なぜ自社の製品を使っているのか(使うとしたらどんな理由か)、製品のどこに満足/不満を感じているか。 |
最後に、ペルソナのイメージに合うフリー素材の顔写真などを設定すると、さらに感情移入しやすくなり、ペルソナがより記憶に残りやすくなります。
ステップ5:ペルソナシートにまとめる
最後に、ステップ3と4で設定した全ての情報を、誰もが一目で理解できるように1枚のシートにまとめます。
これが「ペルソナシート」です。
ペルソナシートに決まった形式はありませんが、基本プロフィール、写真、人格やストーリー、目標や課題などが分かりやすく整理されていることが重要です。
作成したペルソナシートは、PDFやスライド形式で保存し、関係者全員がいつでも閲覧できる場所に保管しましょう。
プロジェクトのキックオフミーティングなどで改めて共有し、チーム全員の共通認識とすることが大切です。
ペルソナ設計にすぐ使えるテンプレートと必須項目
「何から手をつければいいかわからない」という方のために、すぐに使えるペルソナ設計のテンプレートをご用意しました。
まずは、このテンプレートをベースに、自社に合わせて項目をカスタマイズしてみてください。
ペルソナ設計に含めるべき基本項目一覧
効果的なペルソナを作成するためには、以下の項目を網羅することをおすすめします。
BtoCとBtoBで特に重要となる項目が異なります。
【基本情報(共通)】
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 顔写真 | (フリー素材の女性の顔写真など) |
| 氏名、年齢、性別 | 大崎景子、32歳、女性 |
| キャッチフレーズ (ペルソナを象徴する一言) | 仕事もプライベートも充実させたいIT企業のマーケター |
| 居住地、家族構成 | 東京都世田谷区、夫と二人暮らし |
| 最終学歴 | ●●大学 経済学部卒業 |
【BtoBで特に重要な項目】
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 会社情報 | 株式会社〇〇、IT、従業員数500名、情報システム部 |
| 業務上の役割 | 課長、システム導入の企画・推進、決裁権あり |
| 業務上の目標(KGI/KPI) | 業務効率〇%向上、年間コスト〇万円削減 |
| 業務上の課題・悩み | 既存システムの老朽化、部門間の連携不足、予算獲得の難しさ |
| 情報収集 | IT系ニュースサイト、セミナー、業界団体の勉強会 |
| 利用ツール/サービス | Windows PC、Slack、Salesforce |
ペルソナ設計で失敗しないための注意点3選
ペルソナ設計は強力なツールですが、やり方を間違えると効果がないばかりか、かえって方向性を見誤る原因にもなりかねません。
ここでは、よくある失敗例と、それを避けるための注意点を3つご紹介します。
思い込みや理想像で作成しない
これは最も陥りやすい失敗です。
「自社の顧客はこうあってほしい」「こんな人が使ってくれたら嬉しい」といった作り手の願望や理想像をペルソナに反映させてしまうケースです。
データに基づかないペルソナは、単なる「都合の良い登場人物」に過ぎません。
ステップ1で解説したような定量・定性データに基づき、事実を積み上げてペルソナを構築することを徹底してください。
ペルソナを1人に絞りすぎない
「ペルソナは1人に絞るべき」と解説されることもありますが、これを鵜呑みにするのは危険です。
明らかに異なるニーズを持つ主要な顧客セグメントが複数存在するにもかかわらず、無理に1人に統合してしまうと、誰にも響かない中途半端な人物像になってしまいます。
その場合は、無理に統合せず、複数のペルソナを作成しましょう。
例えば、「価格重視の若年層ペルソナ」と「品質重視の富裕層ペルソナ」といった形です。
ただし、無闇に増やしすぎると施策が分散してしまうため、まずは優先度の高い2〜3人に留めるのが賢明です。
作って終わりにしない(定期的な見直しと活用)
時間と労力をかけてペルソナシートを作成し、チームで共有した瞬間に満足してしまい、その後キャビネットの肥やしになってしまうケースも少なくありません。
ペルソナは「作成すること」がゴールではなく、「活用すること」がスタートです。 さらに、市場や顧客のニーズは常に変化します。
最低でも半年に1回、できれば四半期に1回はペルソナが現状と乖離していないかを見直し、必要であれば新しいデータに基づいてアップデートしていくことが不可欠です。
作成したペルソナの活用方法
作成したペルソナは、マーケティング活動のあらゆる場面で活用できます。ここでは代表的な活用方法を3つご紹介します。
コンテンツマーケティング(ブログ・SEO)への活用
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| キーワード選定 | 「ペルソナの〇〇さんなら、どんな言葉で検索するだろう?」と考えることで、顧客の検索意図に沿ったキーワードを選定できます。 |
| 記事テーマの企画 | ペルソナの課題や悩みを起点に、読者に本当に役立つコンテンツテーマを企画できます。 |
| 文章のトーン&マナー | ペルソナの人物像に合わせて、文章の語り口をフレンドリーにするか、専門的にするかなどを決定できます。 |
広告運用への活用
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 広告媒体の選定 | ペルソナが日常的に利用するSNSやWebメディアに的を絞って広告を配信することで、無駄な広告費を削減できます。 |
| 広告クリエイティブやコピーの作成 | ペルソナの写真を見ながら、クリック率やコンバージョン率の高い広告を作成できます。 |
商品・サービス開発への活用
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 新機能のアイデア出し | 「ペルソナの〇〇さんは、こんな機能があればもっと喜ぶはずだ」という視点から、顧客に本当に求められる機能のアイデアが生まれます。 |
| UI/UXの改善 | 「〇〇さんにとって、このボタンは分かりやすい位置にあるだろうか?」「この操作方法は直感的だろうか?」とペルソナの視点でサービスを評価することで、ユーザーにとって使いやすいインターフェースに改善できます。 |
ペルソナ設計に関するよくある質問
最後に、ペルソナ設計に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
ペルソナとターゲットの違いは何ですか?
ターゲットは年齢や性別といった属性データでセグメントされた「集団」を指します。
一方、ペルソナはそこからさらに踏み込み、趣味、価値観、ライフスタイル、具体的な悩みまで設定した、実在するかのような「個人」の人物像です。
ペルソナの方が、より顧客視点での施策立案に役立ちます。
ペルソナは何人くらい作成すれば良いですか?
一概には言えませんが、主要な顧客層に合わせて3〜4人程度が一般的です。
ただし、あまり多すぎると施策の焦点がぼやけてしまうため、まずは最も重要と思われる顧客層のペルソナを1人作成することから始めるのがおすすめです。
作成するための十分なデータがありません。どうすれば良いですか?
最初から完璧なデータが揃っている必要はありません。
まずは既存の顧客情報、現場担当者へのヒアリング、競合調査など、今ある情報から「仮説」としてのペルソナを作成しましょう。
そして、事業を進めながらアンケートやインタビューでデータを収集し、徐々に精度を高めていくことが重要です。
作成したペルソナは、どのくらいの頻度で見直すべきですか?
市場環境や顧客のニーズは常に変化するため、一度作成して終わりにするのは危険です。
最低でも年に1回、ビジネスの変化が速い業界であれば半年に1回は見直しを行い、ペルソナを最新の状態にアップデートすることをおすすめします。
ペルソナ設計のまとめ
本記事では、マーケティングの成果を飛躍させる「ペルソナ設計」について、その重要性から具体的な作り方、テンプレート、活用法までを網羅的に解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- ペルソナ設計とは、データに基づき、具体的な「個人」として顧客像を設定すること。
- 作り方は、①情報収集 → ②整理 → ③骨格作成 → ④肉付け → ⑤シート化 の5ステップ。
- 成功の鍵は、「思い込みで作らない」「作って終わりにしない」こと。
- 作成したペルソナは、コンテンツ、広告、商品開発などあらゆる場面で活用できる。
ペルソナ設計は、顧客という存在を、単なる数字やデータの集合体ではなく、血の通った一人の人間として深く理解するための強力な手法です。
顧客が見えれば、あなたのビジネスが本当に進むべき道も見えてきます。
まずは本記事でご紹介したテンプレートを使い、あなたの会社の「理想の顧客」の顔を思い描きながら、最初のペルソナ設計に挑戦してみてはいかがでしょうか。
知足CHISOKU
今だけ!
開講記念特典!
\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/
開講記念特典!
柴田の壁打ち(30分×6回)を
プレゼント!
※法人契約の場合、受講生にプラスして、
同法人の方2名(合計3名)まで参加可能









